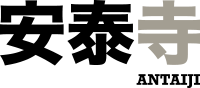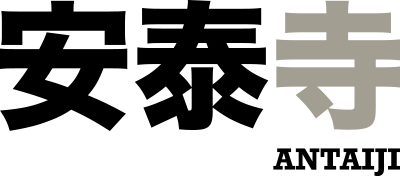キリスト教、仏教、そして私・その15
ABCの仏教
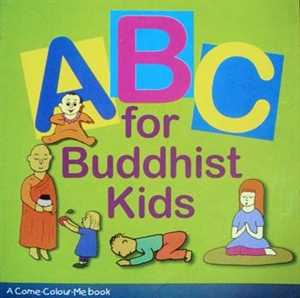
仏教Bは、それまでブッダになるための準備段階としか考えてこられなかった菩薩の実践に注目します。仏教Aでは、菩薩はこれからブッダ になろうとして、修行に励んでいる人を指します。今はまだ完全に目覚めていませんが、生々流転して菩薩の実践を続ければ、いずれの生にはブッダとなれるは ずです。菩薩はブッダになるために自らの執着を徐々に減らそうとしますが、他人のために尽くすことがその近道です。しかしながら、他人のために尽くす目的 はあくまでも自分の解脱です。換言すれば、仏教Aの菩薩は他人のためには何もしていないことになります。他人のために尽くしても、相手の執着を減らせない からです。減らされるのは自分の執着だけですから、仏教Aの菩薩は「他人のため」ではなく、「自分のため」に実践しているだけです。ですから、そういう人 は本当の菩薩とは言えませんし、他人を救うどころか本人すら自分の執着から自由になることはできないでしょう。「解脱したい」という思いが、もっとも欲深 い執着なのですから。
仏教Bのアプローチは真逆です。仏教Bの菩薩は自分の解脱を後回しにして、もっぱら他人の救いを考えています。「私ひとりは、救われな くてもよい。それよりも、一人でも多くの者を救いたい」というのがそういう菩薩の願いです。とうぜん、仏教Aの菩薩からこういわれそうです。
「救われてもいないあなたは、どうして他人が救えるのか?まず自分が救われてから、ものを言え!」
一見疑いようのないこの考え方が執着の塊なのです。その「まず自分から」という思いがあるからこそ、解脱ができません。そういう思いで いくら修行に励んだとしても、解脱から遠ざかっていくだけだというのが仏教Bの主張です。逆に「私ひとりは救われなくてもよい」と心から思っている菩薩 は、実はすでに解脱しているのです。そういう人は「解脱したい」という執着からも自由になっているのです。
菩薩の概念の違いをもういちど整理する、次のようになると思います。
仏教Aでは、菩薩はこれから解脱しようと励んでいる人。すでに解脱を果たした人のみがブッダ。菩薩はまだ生死(サンサーラ)の中で輪廻 転生し続けているが、涅槃(ニルヴァーナ)を得たブッダはこの世から永遠に消えていく(この世と違う場所に涅槃と言う別世界があるわけではなく、完全に消 えた状態こそ「涅槃」の意味)。仏教Bでは、菩薩は自分の解脱を忘れて、他人の解脱だけを願っている人。ところが、そういう人こそ解脱していたというのが ポイント。つまり、菩薩こそこの世に生きているブッダの姿だった。そうすれば、菩薩の生死こそブッダの涅槃を意味することになる。私たちが生きているこの 世がすでに涅槃だったというのが仏教Bの主張。
上の引用では、ダライ・ラマはイエスについて「菩薩もしくは覚者」というふうに言葉を濁していましたが、仏教Bの立場から考えた場合 で、菩薩とブッダの違いがあいまいになってくるのは事実です。ダライ・ラマ自身は、英語の報道では“living Buddha”などと称されたりしますが、チベット仏教の考えでは観世音菩薩の生まれ変わりだとされています。いっぽうダライ・ラマよりワンランク下のパ ンチェン・ラマはなんと阿弥陀仏の化身だそうです。仏より菩薩のほうが位が上だと言うのは、仏教Aの立場では考えられないことですが、仏教Bならどっちも どっちです。無我を悟るのがブッダ、その実践をするのが菩薩です。
仏教Bの特徴をまとめておきましょう。
執着の根本は「まず自分」という思い。解脱したい、再び生まれ変わりたくないというのも執着だから、自分のために修行している人は解脱 できない。自分の解脱を忘れて人のために修行している人こそ解脱している。そういう人は菩薩でもあり、ブッダでもある。生死を生きていながら、涅槃を得て いる。
この仏教解釈にも、創造主・救世主や贖いの概念は不要です。しかし、無我を悟って他人のために実践している各々の菩薩はある意味では、 イエスのような働きをしているといえなくもありません。また、仏教Aが完全な自力を説いているのに対して、仏教Bはこの点についてあいまいです。菩薩の実 践をしなければならないのは自分ですが、そのためには自分を忘れなければなりません。自分のためであってはいけないのです。ではその力はどこから来ている のか、という問題があります。仏教Bの答えは革命的です。
「それが仏の力ほかならない」
この答えの背景にあるのは、「仏性」の教えです。「仏性」という言葉のもともとの意味は、誰でもブッダになる可能性をもっているという ことでした。この一生ではだめでも、生々菩薩の修行を続けていれば、いずれは誰でもブッダになれるというのはすでに仏教Aが説いています。仏教Bでは、そ れがこう変わってしまいます。
「あなたが気づいても気づいていなくても、すでに仏性を生きている。だからブッダや菩薩として生きようと思えば、今すぐにできる」
そういわれると、気が引ける人もいるでしょう。
「まさか、こんな私が……」
日本仏教の中でも一番よく知られている経典の一つを頼りに、その当り前の疑問に対する答を探ってみましょう。
西洋では前章で見てきた放蕩息子の比喩は有名ですが、有名な『法華経』の中にも「長者窮子(ちょうじゃぐうじ)」という似た話が出てきます。そのテーマは、まさに先の疑問です。
「こんな自分にも、菩薩ましてやブッダの実践ができるのだろうか」
大事な話なので、まずその内容を自由に要約しながらここで紹介したいと思います。
ある人は長い間、今でいえば「自分探し」をし世界中を放浪した。やがて持っていたお金を使い果たし、ただの乞食になってしまった。お金もなく、仕事もなく、よりどころは何もなかった。家に帰ろうとしたが、
「私はどこの生まれ?お父さんは誰?お母さんは誰?」
……それすら思い出せない。旅の途中、ある村の大きな家の前を通ったときだった。実は、そこは彼の父が住んでいる家だったのだが、彼にはそんな覚えがない。門を覗き見しながら、彼は思った。
「立派そうな豪邸だ。場違いなところに来てしまった」
彼はその家にいる大金持ちの長者を見て素通りしようとしたが、すでに遅かった。長者はハッと気づいていたのだ。
「この子だ」
しかし、泥棒とでも間違われたと思っていた息子はあわてて逃げた。
「そのまま逃げてしまえば、一生この村に戻ってこないかもしれない」
と思った父は雇い人にその後を追わせた。
「おい、オマエのためにいい仕事があるから、ついてこい」
恐怖のあまりに失神していた彼は結局、父の家まで運ばれた。気がついていたら、その家で雇われることになっていた。最初の仕事はトイレ 掃除だった。そこでバケツと雑巾を持ってきて、掃除の仕方を指導したのはなんと長者自身だった。しかし本来の格好をしていれば、息子には信頼されないだろ うから、長者はわざとみすぼらしい服装を着て自分の顔には泥まで塗っていた。
トイレ掃除をいっしょに掃除しながら、長者は息子にいう。
「オマエはよく働くから、しばらくはここにおったらどうだ。お金が足りないなら、いつでもいってくれ。お小遣いもやるし、寒かったらこのぼろい上着もやる。何かがあったら、ワシのことを父代わりだと思っていつでも相談してくれ」
長者は非常に注意深かった。「父だ」といわず「父代わりだと思え」といった。そういわなければ、信頼されないのが分かっていたからだ。 息子はまさか自分が長者の息子であるという思いがないから、その家が自分の家だということにも気づかない。彼にとっての父もただその家の善良な「雇い主」 にすぎない。しかし、居心地が悪くないので、しばらくそこで働くことにした。そしていろいろな仕事を任せられるようになり、時間の経過と共に長者に信頼も されるようになった、と息子の目には映っていた。いつの間にか、彼は長者の右腕になり、本当の父と息子のような関係になった。最後に長者が病気になり、彼 に真実を明かす。
「この家は、オマエの家だよ。後は任すよ」
「いや、長者さん。ここは私の家ではないし、私にはとても荷が重過ぎる。今までどおり、一生けんめい働きますけど」
「わしがいっているのは、そういう意味ではない。オマエがずっと捜し求めていた家、それがこの家なのだ。ワシはオマエの本当の父、お父 さんだよ。ワシのためによく働いたから、譲るというのではない。最初から、ここはオマエの家だったのだ。オマエはワシに雇われ、働いたのではない。オマエ の家を、オマエ自身がこの長年の間、守っていただけなのだ。」
聖書の「放蕩息子」のテーマは父に背いた息子の回心でしたが、「長者窮子」は自覚の物語です。聖書の場合、父は息子を赦しますが、そこ にはまだ一線が画されている気がします。いっぽうの『法華経』の比喩の場合は、あの一線が最初からなかったということがポイントです。ここで出てくる長者 は言うまでもなくブッダのことです。しかしその子はイエスのように、過去に生きていた人物ではなく仏の教えを聞いている一人ひとりのことです。私とあなた のことです。私とあなたが生きている人生そのものが「仏の家」なのです。なのに、その中の主人公が自分であるということに、私たちはなかなか気づきませ ん。先ほどの「クリスチャニティ・トゥディ」のインタービューアーは「ブッダなら、うそをつかないだろう」と言っていましたが、『法華経』は釈尊こそ方便 の名人だったと主張しています。『法華経』によれば、釈尊は「永遠のブッダ」なのです。
仏教Aから見れば、とんでもない話です。釈尊はこの世の苦しみに気づいて、発心・修行をし、悟りを開いてから法を説いた人間です。八〇 歳で食事中毒でなくなったのも、あまりにも普通すぎる死に方ではありませんか。その釈尊のどこが「永遠のブッダ」なのでしょうか。長者が自らの顔に泥を 塗って、息子と並んでトイレ掃除をしていたように、釈尊も一芝居を売ったに過ぎないというのが『法華経』の教えです。どうしてそこまでしなければならない のかと言うと、あの窮子のような疑い深い人が多いからです。ようするに、仏教Aしか受け付けられない信仰心の薄い者を納得させるために、永遠のブッダはわ ざわざ有限の人間の身体で現れたというわけです。そして永遠のブッダが二五〇〇年前に釈尊として現れていたと同じように、今ここでは私とあなたとして現れ ているというのが仏教Bの教えです。
ですから、仏教Bの理屈でいけばイエスももちろんブッダでした。そして歴史上の釈尊とイエスとどちらが方便を使っていたといわれれば、 ダライ・ラマにものを申すようで恐れ入りますが、イエスではなく仏教Aを説いた釈尊です。イエスの次の言葉は、まさに仏教Bの「長者窮子」の比喩の種明か しに聞こえます。
「わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない」(ヨハネによる福音書(口語訳)#14:6)
キリスト教とは、自分をよりどころとしません。イエスをよりどころとします。イエスをよりどころとすることは、イエスのように生きるこ とでしかありません。イエスが神への通路ですから、イエスのように生きている者は自らイエスとなり、神の子であると気づくのでしょう。少なくとも、私はそ ういうふうに読むしかありません。しかし、クリスチャンは口が曲がっても「私は神の子」とは言わないでしょう。
あの紛らわしい三位一体の教えだけは、いくら探しても仏教には見当たらない、と思っている人もいるかもしれません。実は、それも仏教B にはあります。キリスト教が一神の三つの位格を説いているように、仏教ではブッダの「三身」すなわち法身・報身・応身を説きます。その中での従来のブッ ダ、つまり仏教Aの「仏」に当てはまるのは応身です。釈尊のように、具体的な人間の形で現実に表れているブッダです。
その裏には永遠の仏性があります。それが法身です。仏教Aでは、法身は可能性としての仏性に過ぎません。その法身には本来、名前も形も ありませんが、『法華経』では釈尊が法身を同一視されています。後の密教では大日如来がこの法身の役割を演じ、浄土教では阿弥陀仏が無量光・無量寿として の法身です。つまり、キリスト教でいう「父」が仏教の法身、キリスト教の「子」は仏教の「応身」。そして報身というのは仏性の自由な働きによって、この世 の中で現れる超人的な現象です。観音さんの働きも、地蔵さんの働きも、阿弥陀さんのそれも、みんなブッダの報身の働きです。釈迦が不在の世界に、ブッダの 唯一の働きかけです。キリスト教でいえば、聖霊の働きほかならないでしょう。
ここまで来ると、仏教Cまであと一歩です。仏教Cでは、ブッダの働きと自分の働きを分けて考えます。この世で自分が仏になることがすで に不可能だとされていますから、自力は完全に否定し阿弥陀仏の他力を頼むことを説いています。その考えの鍵となるのはいわゆる末法思想ですが、末法につい ては後述します。とにかく、仏教Cは修行を説きません。いくら修行をしても、ブッダになれないからです。他人を救うことも、仏教Cの立場から見ればとんで もない思い上がりです。他人を救えるのはブッダのみですから、自分の実践は不必要になってきます。すべてを阿弥陀仏にお任せし、阿弥陀仏の救いを信じるこ とだけが大事です。
仏教Cでは、救いの内容も変わってきます。仏教Aでは個人の解脱が目的であったことに対して、仏教Bでは他人の救いを目指しながら生死 を繰り返すことことこそ解脱と見なされていました。仏教Cでは、死んでから「極楽」と言われる阿弥陀仏の浄土に往生することが目的です。厳密にいえば、仏 教Cにもいろいろなバリエーションがあり、西方にある阿弥陀仏の「極楽」の外には、東方にも薬師如来の浄瑠璃世界があり、霊山には釈尊の浄土あり、毘盧舎 那仏(びるしゃなぶつ)の蓮華蔵世界あり、さまざまな浄土があるのですが、とにかく阿弥陀仏の浄土に入るためのハードルが一番低いのです。阿弥陀仏はその 名前を称えるだけで救ってくれるのだそうです。
自分が菩薩となり、生死をそのまま涅槃と心得る仏教Bでは、キリスト教との違いが見えていますが、仏教Cは限りなくキリスト教の信仰に 近いと思います。「イエス・キリスト」という名前と十字架のシンボルこそそこにはありませんが、全て神・仏にお任せし天国・極楽に入るという意味ではまっ たく同じです。
(ネルケ無方、2013年6月9日)