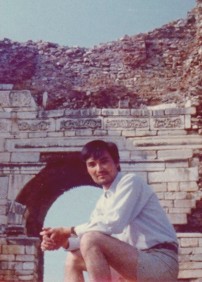カーン、カーン、カーン 静かな朝のジャングルに鐘の音が吸い込まれていった。その音に賢二は我に帰った。
ベットの上に横たえられていた。高いアーチ型の天井には十二使徒伝のフレスコ画が目に止まった。そしてそれが彼にはよけい分からなかった。何でこんな所にいるのか、いったいどうしたのだろう。
ぼんやりとする意識の中で彼は必死に記憶をたどっていた。それは彼が船に乗った時の事であった。
デカン高原をさまよって原因不明の熱病にかかり、やっとボンベイまでたどり着いたが何も分からず、ただ海の冷たさが心引くままに目に止まった客船に乗ってしまったのであった。行先などどうでもよかった。乗船するやいなや、風通しの良い上部デッキに出てそのまま救命筏の上にひっくり返ってしまった。
夕方涼しくなって目がさめると、ちょうど右舷のアラビア海に夕陽が沈んでいく所だった。群青色の海と空、その中に焼けただれた鉄球がポチャンと落ちていくようで、何か月世界か、果ては宇宙のどこかにでも来ているような不思議な光景だった。それを見ながら再び彼は意識を失ってしまった。
悪夢にさいなまれてどのくらいたったのだろう、人々のざわめきに現実に引き戻された時は朝であった。なだらかな台地状のインド大陸の上に、色あせた、ボヤッとした朝日が昇ってきた。朝の風が熱でうかされた賢二の体をなでてくれていた。
その頃から船は進路を直角に変えて、朝日に向って進み出した。それにつれて陸地が近くなり、赤茶けた陸地が迫ってきたーインド大陸。しばらく進むと入り江らしきものがみえ、どうやら船はそこに向っているらしかった。入り江に近ずくにつれて、その岸には巨大な要塞が見えて、旧式のキャノン砲がいくつもたいくつそうにその口をあんぐりと開けて我々を出迎えた。
そこを過ぎると両岸の景色は急に緑が多くなった。熱帯のジャングルが続きヤシ林が海辺までせまってきていた。入り江と思ったのはどうやら河口らしかった。朝日に映える鏡のような川面をすべるように船はゆっくりと遡っていった。
賢二はそんな風景を薄れていく意識の中で眺めながら、つい前日までの熱砂のデカン高原が地獄なら、今彼は天国の入り口にでもいるような気持ちだった。
賢二の記憶はそこでプッツリと切れていた。どう考えてもそこから今彼がこうしてベットの中で横になっているまでが空白であった。いったいどうなったのだろう、彼は思った。
起き上がろうとしても熱っぽい体は鉛のように重くベットに縛りつけられたかのように動かなかった。
どうやら彼は教会の一室か、そんな類の所にいるらしかった。それも中世のそれで、まるで彼が知らないうちに時間を飛び越えて中世のヨーロッパにでも引き戻されたように思った。彼の伏しているベットは部屋の窓寄りにあり、窓が高いので外はよく見えなかったが、青い空が見えブーゲンビレアの花が彼を覗き込むように窓にせまっていた。
賢二はまだ彼が夢の中にいるように思えてしかたなかった。ただ彼の身を包んでくれている糊のきいたリンネンのベットシーツが肌に気持ちよく、その感触をたどりながらしばし放心していた。
どのくらいたったろうか。突然ドアの開く音がして人の気配に我にかえった。とっさに目を閉じた。 恐かった。急な変化が恐かったのである。
しかし賢二は知りたかった。それが彼をうす目を開けさせた。
若い女がドアを閉めてこちらに向き直った処だった。二十四五歳の小柄な娘で、ゆるいウエーブのかかった栗色の髪がえり首にたれていた。薄い藤むらさきのワンピースに白い大きなエリが豊かな胸もとを包んでいた。しばらくその女も賢二の様子を伺っているようであった。しかし賢二が動かないのを確かめると女はつかつかと部屋を横切って、一隅に設えられた祭壇に向かって額づいた。長い祈りだった。
やおらその女は立ち上がって賢二の横に立った。事ム的に彼の腕をとり脈を見て、次に額に手をあてた。賢二にはその手が柔らかく冷たくて気持ちが良かった。
彼はゆっくりと目を開けた。
「オオ、気が付かれたのね、まあ、まあ。」
女は言いながら賢二の額から手を引いたがそのやり場に困ってしまったのか両の手を交差したり、互いに指をもそもそいじっていた。
「よかったわ。二日間ずっと意識がなかったのですよ。ただ熱に浮かされてうわ言ばかり言って。」
言葉は英語だったがその発音から彼女がイタリア人かその母国語の人である事は容易に察せられた。
賢二はそんな事を言われても何が何やらわからず、最初に口にでたのはこうであった。
「ここはいったいどこですか。」
「セイントパウロ寄宿学校よ。私はここの教師の一人です。」
「ええ、ヨーロッパ、確か私はインドにいたのに。」
「貴方はまだここがどこか知らなかったですね。もちろんインドですよ。ここはゴアの町、貴方は船でここに来られたんでしょう。」
彼女はあきれたようにそう言ってから、まだ彼が正気でないかのようにまじまじと賢二をながめていた。賢二には、彼の失った時間にやっと一つの糸口が見えてきた。彼が最後に船から見たのはゴアへの入り口だったのだ。
「ゴアか。」
賢二は呟いた。インドの西海岸にある町、ゴア。かつては数世紀にわたってポルトガルの植民地で、東洋貿易の拠点として栄えた処、でも今はインドの州の一つとなり、かつての栄光は深いジャングルの中へ埋もれてしまった。彼はそんな事を思いながら独言を呟いた。
「どうして今私がここにいるのですか。」
その女は賢二が何も知らないのを見てとると決心したように話し出した。
「貴方は船に乗ったのは覚えていらっしゃるでしょうね、まさかそれも知らないなんて事はないでしょうね。その船がゴアの港に着いた時、貴方は上部デッキの上で苦しんでいたの。たまたま同じ船に乗っていたテレサ、この学校の校長ですわ、彼女が見つけて医者に連れていき、その足でここへ運んできたの。
それがちょうどおとといの朝でしたわ。その後だんだん熱は下がり始めたけれども貴方は今まで意識がなかったのですよ。」
賢二は失われた自分がやっと一本の糸の上に見えてきた。そして突然不思議な気持におそわれた。それは助かった、命びろいしたという気持でもなければ、昨日までの苦しかった我身でもなかった。
ただ「ああ私は今こうして息をしている。私が知らなかった何日間も、そのまた以前と同じように息をしていたのだろう。」そう思うと安らかにベットの上に横になっている彼が別人のように思えた。
そして脳裏に浮かんだのは、もし死後の世界があるのなら案外こんな感じじゃなかろうか、そこには以前と何のかわりもない、別に何もかわった事もない、ただ生前と死後という時間の区切りを通り過ぎたに過ぎない。
「気分は良くなられまして」
彼女の声に賢二の思いは中断された。
「何かめしあがりますか。この二日間何も食べていないのですよ、冷たいジュースでも持ってきますわ。あ、そうそう、うっかりしていた。テレサにこの事を知らせなくっちゃ。」
言いながらドアの取っ手に手をかけたが、思い出したように振り返って言った。
「それと私の名前はカロリーナ、用があったらそう呼んで下さいね。」
ドアの向こうで小走りにかける音が遠ざかっていくと同時に、「テレサ、テレサ。」と呼ぶ声が伝わってきた。賢二はそれを何かずっと遠く離れた所のでき事ででもあるかのように聞きながら目を再び閉じた。
そんな彼を見守るように、窓辺のブーゲンビレアがそよ風になびいていた。
賢二がベットを離れたのはそれから二日後だった。もう熱はすっかり引いていたが、体中が虚脱状態で力が入らなかった。
その間カロリーナはほとんどつきっきりで看病してくれた。何もない時はベットの脇にいて世間話をしたり、この学校やゴアの町の様子を話してくれた。
どうやら今賢二がいる処は昔はカソリックの修道院だった処で現在は寄宿学校になっているらしかった。ゴア州はもちろん、インド各地から中流家庭の子女が二百人ほど来ているらしかった。
でも今は休暇中で生徒は全員家に帰って、先生も国に帰ったり旅行にでて、校長のテレサとカロリーナが留守居役でいるだけだった。
後でわかったのだが、どうやら賢二をここに連れてきたのはテレサの図らいで、留守居役で暇を持て余しているカロリーナに丁度いい仕事と思っての事らしかった。
カロリーナの案内で賢二は部屋を出た。彼の目をまず奪ったのはその学校の建物だった。かつての中世の修道院そのままで、よく茂った中庭を囲んで棟が並びその庭に面して広い回廊が巡っており、その白い柱が熱帯の青い空とヤシの緑に映えて美しく、きれいな幾何学模様を作り出していた。
シーンと静まり返った大建築の中はひんやりとして薄暗く、まぶしい太陽の屋外と対照的であった。
カロリーナと賢二の靴音だけがコツコツと高いアーチ天井に吸い込まれていった。
その建物は小高い丘の中腹にあった。植民地時代はこのあたり一帯が行政府として、また貿易都市として栄えたのであろうがそれも今は廃墟と化し、いつしか深いジャングルの下に埋もれてしまっていた。
人々もそれと共に河口の新しい町に移り住み、ここのオールドゴアはいくつかの歴史的建築物を史跡として保存してある他は荒れるがままになって、ジャングルの下に静かにー眠っていた。
カロリーナの手厚い看護で賢二はみるみる元気を回復し、やがて落ち窪んだ目や頬も元に戻り見違えるようになった。
彼はすぐにでもここを出るつもりだったが、テレサやカロリーナに学校が休みだから遠慮せずにもっと養生したらと言われ、賢二も世話になったお礼に何か手伝いでもしようとしばらく留まることにした。
巨大な建物は長い年月にその傷みもひどく、壁や天井のペンキを塗り変えたり、きしむドアや窓を直したり、伸び放だいの植え込みを刈り込んだり草取りをしたり、男の賢二のする仕事はいくらでもあった。
賢二はカロリーナと共に朝早くから夕方暗くなるまで働いた。夜は涼しくなったベランダでテレサを交えて話をしたり、トランプに打ち興じた。
テレサはもう七十歳を超えていたが信仰に生きる女らしく、明るく澄んだ瞳は生き生きとしていかにも人の良さそうな感じであった。
そんな彼女も昔はいろいろとあって、ポルトガル人の父とイタリア人の母の間に生まれたが、彼女の幼い頃に両親が離婚して母と共にローマに帰った。でもみじめな生活の中でテレサはぐれて、一六七の時にはもうローマの裏町では有名なスリと売春婦に身を落としていた。そんなテレサを信仰の道に導いたのがゴアの司教で今は亡きソレム神父だった。以来彼女はこの修道院に入り、学校となった今もこうして神に仕える身として子女の教育にあたっているのであった。
カロリーナをゴアに呼びよせたのも彼女であった。
そのカロリーナもここに来てはや四年になる。彼女はミラノの生まれだったが大学時代に同じクラブの男性と恋におち結婚まで考えたが、両親に反対され家を飛び出した。そんな彼女を諭してくれたのがテレサであった。
そんな二人だから親子よりも親密で、明けすけな雰囲気だった。いつしか賢二の心も知らず知らずにその中に溶けこんでいった。
こうした生活が重なるにつれ、三人の間には一つの家族のような親しさになっていったが、しかしそれにも増して賢二とカロリーナの間にはそれとは別の気持ちが急速に芽を伸ばしていった。
それは賢二がここに来てから二週間にもなろうとした頃の事であった。その夜は月のきれいな夜であった。
三人ともいつもより少し早く床についたが、賢二は窓より入ってくる月の光に目が冴えてねつかれず、中庭に面したベランダに出た。
深い眠りについたジャングルを中天の月が静かに照らしていた。
中庭を挟んだ向うのベランダにふと白い影が目に止まったが、それが誰であるか賢二にはもう疑う余地もなかった。カロリーナであった。
静寂の中で二人はしばらくたたずんで石のように動かなかったが、やがてどちらからともなく中庭への階段をおり始めた。中庭の植え込みはヤシやパパオの木々が茂り、月の光も届かず深い海の底にでも入ったように冷んやりとしていた。
二三日前にこの庭の下刈をしたので賢二には、ちょうど魚が住みなれた海を泳ぐように林をぬっていった。
中程にある大理石のベンチにカロリーナは来た。木の間からもれる月の光に中に彼女の白いナイトガウンがゆっくりと泳ぐように進んできた。
二人とも無言だった。いや、もはや言葉など必要ではなかった。まるで何かにあやつられているかのように二つの影が近ずいて一つに重なった。
二人の燃ゆる思いなど知らぬかのように、青いサロメの月の下、ジャングルの夜は深く、そして静かに更けていった……。
愛というものは不思議なものである。
それには時もなく、形もなく、大きさもない。この世の一切を包みこんでしまうかと思えば遠いいにしえの昔に投げかけられることもある。
母が子を思い、子が友を思う愛もある。神に誓う愛もある。しかしその量り知れない愛の中で男が女を思い女が男をしたう心程不可思議なものはないであろう。
若い二人に間にふと燃え上がった炎は、人の世の掟も、己が命さえもってしても、もはや消す事はできない。ただ燃えつきるのみである。それが一瞬であれ一年であれ愛に変わりはない。
愛は時もなく、形もなく、大きさもないのである。
カロリーナが賢二を丘の上にさそったのはもう学校の休みも終りに近ずいた頃のことであった。
薄暗いヤシの林を少し登るとそこは古い教会の跡だった。かつては幾千の人が集い祈りをささげたであろうここも、今は荒れるがままに朽ち果て崩れ落ち、ジャングルの下に埋もれていた。
「ここは私の一番好きな所よ。学校の生徒もこないし、もちろん観光客など知らないわ。」
賢二の手を取りながらカロリーナは言った。
「ほら見て、あのヤシの林の上に突きでた建物、尖塔の一部がまだ崩れずに残っているの。でもいつ倒れるか分からないから風のある日など近ずかないの。」
二人はその尖塔の下を抜けて西側に出た。
「ここに私だけの祈りの部屋があるの。誰も来たことがないわ、貴方が初めてよ。」
言いながらカロリーナは崩れかけた瓦礫の上を横切って、低い潅木の茂みを押し分けて進むと、倒れかかった壁にぶつかり、その割れ目から身をよじらせて中に入ると小さな部屋に出た。
「此処は以前神父の控え室だったらしいの、散歩の途中で私は偶然見つけたのだけど、気に入ったので瓦礫を片付けて掃除したの。」
彼女は言いながら部屋の一面に残っている祭壇に向って十字を切った。それから壁ぎわにある長椅子に腰を下ろした。ステンドグラスを通して入ってくる光を身に受けてそれを楽しむように椅子の背にもたれた。再び沈黙が訪れた………。
「私は時々自分がわからなくなるの。」
カロリーナはしばらくして思い出したように呟いた。
「私がクリスチャンであることよ。」
「それは君と僕の関係をいってるのかい。もしそうだったら僕も君にはすまない事になったと思っている。
「いいえそうじゃないの。そのことならむしろ反対で私は良かったと思っているわ。
私が分らないのは、今までの私が本当にクリスチャンとして生きてきたのかどうかよ。
以前にも言ったと思うけど、私の父も母もクリスチャンだったし、彼らの両親もたぶんそうだったでしょう。私が物心ついた頃にはすでにクリスチャンだった。いやクリスチャンにさせられていたと言えばいいのかしら。町の人々も全員そうだったし、他教の人々はその社会には入れなかったわ。
私の幼な友達のダニエルの場合だってそうだった。彼はカソリックを捨てたとたん会社をやめさせられた。ただ宗派が違うという理由だけで。
そして次が私の番だったわ。私がミラノの大学に入学して同じクラブでボーイフレンドができ、卒業したら結婚する約束で付き合っていたの。その人はカソリックじゃなかった。そうと分った私の両親は猛反対したわ。私自身はいくら宗派が違っても結婚してうまくやっていけると思い彼にもその事を打ち明けたの。
その時彼は言ったわ、『もし子供ができたら私の方の洗礼を受けさせていいのなら、君に対する私の愛情に変わりはない。』でもそんな事、私の両親が絶対に許さなかったわ。それからは頼りにしていた彼までがだんだん私から遠ざかっていったわ。
私はそれがくやしかった。私達の愛情なんてそんなに薄っぺらなものだったのか、男ってそんなものなのか。私はそれに耐え切れなくてとうとう学校もやめ、家を飛び出してしまったの。」
カロリーナはそこまで言うと、昔の古傷を握り返されたように賢二から顔をそむけた。ステンドグラスを通して入ってくる光が彼女の頬を染めた。そこにはキラリと光るものがあった。
賢二は何も言わずにカロリーナの手を取って膝の上に重ねた。カロリーナは大きく肩で息をして再び語り始めた。
「その後私はローマに行って仕事を転々としていたの、そんな時だったわテレサに会ったのは。彼女は会議でローマに来ていたの。そして私を此処に連れて来たの。
当時の私は誰も信用できなかった。しかしそれ以上に何か頼れる人に飢えていたのね。テレサはその頼れるものがマリアさまだと言ってくれたの。
ここに来てからの私はいっしょうけんめいに祈ったわ。ただマリアさまを信じて、良い子になろうと毎日毎日祈ってきた。でも、何か満たされなかった。何かしらしっくりといかなかった。どれだけ長く祈ってもその後には何か私の心の中の一部に石でも置き忘れたようにすっきりしなかった。
でも、今は違うわ。貴方に会ってやっとそれが何だか分ったの。」
カロリーナはそう言って言葉に詰まった。その詰った言葉を表そうとするかのように賢二の目をじっと見つめた。でもその瞳には先程までとは違った明るい安らぎを滞びていた。
「私の今までの祈りは本当の私の祈りでなかった。」
カロリーナはしっかりした口調で話し始めた。
「今まで私は良い子になろうと努めてきた。少しでも神に近ずこう、神の前に潔白でありたかった。そして私は自分がだんだんそうなっていくと思ってそれが嬉しかった。でも貴方を知ってからは完全にそれが打ち砕かれてしまった。貴方は私を人間の世界に引き戻してくれたの。私が人間であることを教えてくれたの。私の体の中に温かい血が流れている事を教えてくれたの、だから今私はマリアさまの前に祈ることができます、人間として、神の前に罪深い小さな人間として対する事ができる。今までの私はそれを忘れてただ祈っていたのです。」
言い切るなりカロリーナはその高ぶった気持を投げ出すように賢二の胸に飛び込んできた。彼の広い胸に狂おしいばかりに頬を押さえつけた。
賢二には彼女の体が小さく震えているのが感じられた。それをなだめるように彼はカロリーナの背に腕をまわした。その中でカロリーナは、今にも張り裂けんばかりの風船の空気が突然抜けていくように、大きく息をしたと思うとそのすべてを出し切った。それと共に体中から全部の力が抜けて賢二の腕の中で小さくなっていった………。
静かな世界の中にもう西に傾いた陽の光がステンドグラスを通って二人を包み、柔らかいシルエットを浮かびあがらせていた。
どのくらい経ったろう、どちらからともなく立ち上がって窓辺により、二人でそのステンドグラスの窓を押し広げた。淀んだ室内に夕風が入ってきた。それがカロリーナの栗色の髪をなでて、甘い香を誘い出した。窓の外にはヤシの林が見下され、なだらかな起伏となってどこまでも続き、その向こうには、今にも落ちんとする夕陽を反射して静かに流れる河口があった。
次の日の朝であった。賢二はそこを出る決心をした。テレサに別れを言いに行った。早朝だったがテレサは校長室にいて、もうすぐ始まる新学期の準備をしていた。
私が去ることを伝え、カロリーナの事について言おうとすると彼女は何もかも分かっているかのように私をなだめていった。
「後の事は心配しないように、カロリーナには本当に良い休暇だったもの。」
カロリーナは礼拝堂にいた。ずっと祈りつづけてそのまま眠ってしまったのだろう。聖書に顔を埋めたまま軽い寝息をたてていた。その横顔には満ち足りた安らぎがあった。
賢二は起こさないように彼女の髪に別れの口づけをしてそのまま退いた。
テレサに見送られて外に出るとヤシの林の向こうに朝日が昇ったところだった。
澄んだ朝の空気が気持ちよかった。石畳のゆるい坂を下りながらふり返るとブーゲンビレアの咲き乱れるその向こうに朝日を受けて光る尖塔が見え、カーン、カーン、カーンと澄んだ音がジャングルにこだましていった。
第七回 文芸ノンノン新人賞受賞作品!
『ロザリオの丘』
文芸ノンノン〈非常にえがった。他だ一つの欠点は欠点がないことだ。〉
平凡パンツ 〈この露骨までの性描写は読者に強い感動と美しい夢を与えるだろう〉
赤旗日曜版 〈大企業本位の体制側の小説と違い労働者を力ずける真の小説だ〉
白旗連休版 〈ぜひうちの三文版の連載させてほしい〉
禅の友 〈これを精読したならば必ずや大悟徹底たちどころに尿意を催すだろう。〉
まみず 〈ただただ涙涙…涙。ロザリオの丘に涙しております。〉
読者の声
A〈作者がスケベだということがよくわかる。〉
B〈スケベなのは作者なのだとわかった〉
ゆかり〈なんて美しく悲しいお話なんでしょう信雄さん!〉
ジキョウ〈愛は不毛だと信じていたが目を開かれた思いだ。やはりどちらかというと私も不毛のある愛が好きだ〉