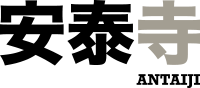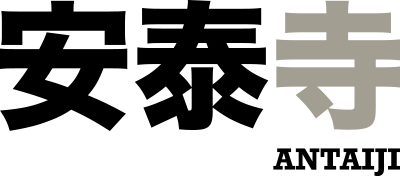澤木興道老師の生涯とその心
櫛谷宗則著

澤木老師の言葉は、みな禅から湧きあがった風のようです。それは懊悩するわれわれの涼風であり、心にしみるそよ風であり、時にナマクラなわれわれに鉄槌を下す暴風雨となり、宇宙いっぱいの青嵐ともなって吹きわたるでしょう。それに従来の自分を吹き飛ばされ、ふと目を上げれば、もはや風は跡形もなくただ坐禅からの静かな光が満ちているだけです。
澤木興道老師は、明治十三年三重県津市新東町に、多田惣太郎の六番目の子として生まれました(姉二人兄一人以外は早逝)。幼名を才吉といい、幼い頃からとても腕白だったようです。五歳(以下年齢はすべて数え年)で母しげ、八歳のときに父が急逝。それで叔母の元にやられたのでしたが、その連れ合いである叔父が半年後に亡くなり、結局知り合いの提灯屋とは名ばかりで、博奕打ちを渡世としていいた一身田町の澤木文吉さんの養子にもらわれていきます。
実にその界隈は遊廓の裏町であり、詐欺師、香具師、博徒、巾着切り等、およそ世の中の吹きだまりのような環境で、老師はそこで改めて九歳から一身田小学校に編入し、賭博の見張り番をさせられたり、寄席の下足番をしたり、十三歳で学校を卒業(当時は四年制)してからは本業である提灯屋に精を出して、およそ働くことのない養父母を養って働きます。あるとき近所の遊廓の二階で、孫のような若い遊女を買った五十男が急死するという事件がありました。これを目の当たりに見て、初めて老師は骨の髄まで無常を感したといいます。道を求める心が芽生えていました。
しかしそんな環境のなか、隣で細々と表具屋を営む森田宗七さんの一家は、教養もあり不思議なほど清らかな生活をしていて、老師はよく遊びに行っては長男の岩吉(千秋)さんから『十八史略』や『日本外史』から始めて『大学』『中庸』『文選』等を教えてもらいました。世の中には肩書やお金や享楽よりもっと真実なものがある。この一家の生き方が、老師の道を求める心の核になっていったようです。
やがてその求道の志と現実との矛盾は、もうどうしようもないほどに煮詰まり、十六歳のときに大阪の友達のもとへ家出、しかしすぐ連れ戻されてしまいました。それで翌年とうとう永平寺へ向かって家出します。所持品は小田原提灯、なま米二升、金二七銭だけで四日四晩、なま米と買ったそら豆を噛み噛み福井県水平寺まで歩き続けたのでした。永平寺ではすんなり坊主にしてくれるはずもなく「帰れ」と断わられますが、二昼夜飲まず食わずで頼みこみ、作事部屋の男衆として置いてもらうことが許されました。そのときの嬉しさといったらなかったそうです。
お盆になって維那和尚の自坊である福井県竜雲寺へ男衆の一人として手伝いに行ったときのことです。寺の行持がみなすみ「もう何もせんでええからゆっくり休め」と言われ、一人奥の座敷へ入って坐禅していました。するといつも人をこき使っているお婆さんが、お椀や食器を仕舞おうとその襖をあけてアッと驚き、坐禅している老師を仏さまより丁寧に拝んだといいます。これによって坐禅の高貴を知らされ、坐禅こそ自分の一生涯をかけてすべきものであると決定したのでした。
そして事実生涯を貫き通す、この坐禅に対する信の純真さ・・・坐禅に対するこの深い信仰から老師のすべてが調い、生み出されていったように思います。
やがて縁が巡って天草宗心寺住職、沢田興法和尚について念願の得度を受け「興道」の法名を頂いたのは十八歳、成道会の日でした。その後二十歳になって雲水として兵庫県圓通寺に安居。そこから出向いた戒会で西有穆山禅師の高弟、笛丘凌雲方丈と出会い見込まれ、老師もその清らかな人柄に魅せられて方丈の自坊、京都府宝泉寺ついで掛川市法泉寺で二十一歳の終わり兵隊にとられるまで随身しました。短期間とはいえ、ここで『学道用心集』『永平清規』『坐禅用心記不能語』の講義を一対一で受け、祇管打坐への信仰の根本的基盤が深く育まれたのでした。
明治三十三年十二月に入営、三年後満期除隊となった途端に日露戦争が勃発してすぐ召集。一時瀕死の重傷を負って戦線を離れますがまた戻り、結局三十九年(二十七歳) 一月に内地へ凱旋、除隊。
その年、仏教を勉強したい一心だった老師は一身田町の真宗高田派専門学校に入学。翌々年には大和法隆寺勧学院に移り、貫首佐伯定胤僧正について唯識教学を中心にただただ勉強のなかに明け暮れる日々を送ります。そんなとき如法衣を搭けていた慈雲尊者ゆかりの尼僧と出会い、それがお袈裟を研究するきっかけとなります。
大正元年(三十三歳)十二月、ほぼ仏教教学の概要を学びおえた老師は、勧学院を出て松阪市養泉寺で単頭の役につき、その後は宗乗の参究のため西有門下随一の丘宗潭老師の会に参じるようになりました。そして大正三年(三十五歳)から足かけ三年、斑鳩町成福寺に一人こもって坐禅に全身心をもって打ち込まれます。
大正五年(三十七歳)丘宗潭老師に引っ張りだされ、熊本市大慈寺僧堂の講師として赴任。そこでは志を同じくする道友を得て大いにその禅風を振るいました。またヤンチャな自然児、第五高等学校の学生との交流が始まり、自身の既成宗教の型を引っぱがされ、生きた言葉で語るという新たな転機にもなりました。
丘老師遷化後の大正十一年(四十三歳)大慈寺を出て借家に大徹堂と名づけ住しますが、半年ほどで熊本市万日山に移ります。武道家が出入りするようになったのもこの頃です。そして以後昭和十年(五十六歳)までの十三年問、万日山に独居しつつ全国各地の坐禅会を乞われるまま巡るようになり、祇管打坐の実際を世に広めていかれました。
昭和十年四月には駒澤大学教授に就任。十二月大本山総持寺後堂に任ぜられ、さらに老師の身命を顧みない大車輪のごとき活躍が始まります。それは大学や本山に止まらず、それまでの参禅会は継続し更なる要望にも精一杯応えて全国各地を巡り、問いかけ、道を説き、共に坐り、時をこえた祇管打坐の新たないのちをわれわれに吹き込まれたのです。
いつも全力で生きねばならない場に自らを置き、日々新たに生きねばならない今に自ら立たれ、老師の生き方はつねに全身心を尽くしておられました。接心では誰よりも早く坐り夜遅くまで、時に伽藍全体がゆれるほどの雷を落とし、老師の威力がピーンとすみずみまで恐いくらいに張り詰めていたといいます。
昭和十五年(六十一歳)栃木県大中寺に天暁禅苑を開単、その後も止まることなく各地に参禅道場を開き、また昭和二十一年(六十七歳)には静岡県大洞院専門僧堂堂長、京都市妙説庵尼僧堂堂長に就任。しかもとうとう一生自分のお寺を持つことも、妻をめとることも、組織を作ることもなく、移動叢林と称してお弟子と共に一所不住、まるでその一生が一夢の坐禅であるかのように生き方そのものをもって、何にもならない無所得の坐禅を徹底されました。そして禅といえば臨済宗の悟るために坐る公案禅のみが盛んだった当時の仏教界に、坐禅をただ純粋に祇管打坐として生き生きと甦らせたのです。
昭和三十八年(八十四歳)向こうをむいて行くばかりだった歩みも、もう足が弱られてこれ以上の巡錫は無理と断念。以後安泰寺で参禅会を続けながら静養につとめられます。「よい人気が続くな。木戸銭いらずに、こんな気持ちのいい日が続くとは」「有難いやら、勿体ないやら。衲みたいに幸せなものがあろうかい」、ご自分の役目を精一杯果たされた後のやわらかな祈りの一時が訪れていました。昭和四十年十二月二十一日、一山の人々に見守られるなか八十六歳で遷化。
澤木老師は風貌いかにも昔来の禅僧らしく、その気迫や度胸、自らを省みない侠気や心遣いで、会う人たちに強い印象を与えられたようです。老師に出会う人はみな、その視線もお心もただ自分一人だけに注がれていると感じたはずです。内山興正老師は人を引きつけるその人問的魅力を「澤木老師は多面的な巨人」とよくおっしゃっておられました。老師のなかにはとんでもない凡夫が蠢いておられたのではないでしょうか。それなればこそ、あんなにも厳しくまた爽やかに生きられたのではないでしょうか。その凡夫から見たら、われわれのようなケチ臭い凡夫の心など、初めからお見通しなのです。そのご自分のなかのどうしようもない凡夫を老師は慈しんでおられました。襖悩する才吉に手を伸ばすように、われわれにこうして道を説いて下さったのでした。
それは同時に、澤木興道自身のなかから真実を引っぱりだすことでした。いつも求道する真っ只中にある老師の言葉は固定していません。動いているいのちです、深まっていく大地です。われわれもその言葉を全身心、その生き方をもって受け取らねばなりません。自らを耕し、自らの真実の言葉を生みださなければならないでしょう。
あるいは読んでいくうちに同じようなことをくどくどと繰り返していて、飽きてしまうという方がいらっしゃるかも知れません。でもこの書はいわば現代のお経なのです。仏教経典が同じようなことをずらずら繰り返し、山川草木が永遠に変わらぬことを日々新たに説いているお経であるように、われわれは一句一句初めて見る自己のように出会わなければならないでしょう。何度も似たような真実語に触れているだけで、知らないうちに何か呼び覚まされてくるものがあるでしょう。
老師の言葉は坐禅から立ち現れてきたいのちの書葉、表現です。坐禅の暖皮肉です。老師はその真実の言葉を説いてきたばかりでなく、その真実から一生を坐せられ禅せられてきたのでした。老師の言葉には妄想を坐断する切っ先があります。坐禅へいざなう力量があります。どんなときでも老師には坐禅がありました。それは生きる力であり、誓願であり、老師の生きる意味そのものだったのです。

安泰寺門前、引退された沢木興道老師(一番左)と弟子達(横山祖道、笠井浄心、佐藤明臣、内山興正など)
All Rights Reserved.