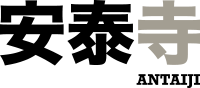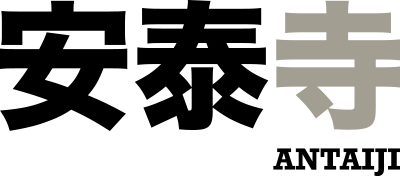塚村
鹿が教えてくれた念佛
安泰寺ではよく鹿肉を食べている。安泰寺を日頃サポートしてくださっている猟師さんが、害獣駆除で捕まった鹿を頻繁にくださるからだ。
しかもただ単に食べるだけではない。安泰寺では鹿の解体精肉まで自分たちで行なっている。その光景はいささかショッキングなものではあるが、しかし自分たちがいただく食物に向き合う貴重な機会になっているとも言える。今年の秋に安泰寺に来たばかりのわたしもまた、鹿からそのことを教わったひとりだ。
南無阿弥陀佛。
鎌倉時代、法然上人の布教以来爆発的な広がりを見せた専修念佛だが、実家が近くの浄土宗の寺の檀家だったこともあり、わたしは幼い頃から念佛に親しんで育ってきた。毎年お盆の時期になると、わたしの家では小さな鐘を鳴らしながら家族全員で念佛を唱えるのが恒例だった。
「な〜むあ〜みだ〜ぶな〜むあ〜みだ〜ぶ」
このフレーズが今でもわたしのなかに染みついている。
初めて鹿を解体精肉したとき、それはわたしにとっても初めての経験で、やはりハードな作業に違いなかった。そしてそのときわたしの内から聞こえてくる声があった。
「ああ、こんなことやってたらぜったい地獄に落ちるよな。南無阿弥陀佛…」
幼い頃から染みついていた念佛が、不思議と再び蘇ってきた。
なぜ鎌倉時代以降、専修念佛が爆発的な広がりを見せたのか、そのとき何となくわかったような気がした。
昔の人の生活は、身近なところに生き死にがあるものだった。自分が生きていくために自分で魚を殺し、動物を殺し、植物を殺す。今みたいにスーパーマーケットで肉のブロックや魚の切り身が売ってあるわけではない。あるいは戦などで、自分が殺されないために相手を殺す場合だってあっただろう。
昔の人が生きていくためには、自分で直接他者の命を奪う必要があった。そんな状況で、殺生を繰り返せば地獄に落ちるなどと言われれば、昔の人は恐らく本気で信じただろう。だからこそ、念佛を唱えれば極楽浄土に往生できると説く専修念佛に縋ったのだろうし、専修念佛が爆発的な広がりを見せた理由もそこにあるのだろう。われわれ現代人が思う以上に、彼らは切実だったのだ。
わたしは猟師さんと一緒に鹿の止め刺しを行なったこともある。止め刺しとは、罠にかかった鹿の、最期の息の根を止める作業のことだ。
猟師さんと一緒に現場へ向かってみると、前足が罠にかかって身動きがとれないでいる雌鹿がいた。わたしと猟師さんが近づいてくると、その雌鹿はなにか縋るような、怯えるような鳴き声を発した。近づいてくる人間たちに微かな期待を抱いたのか、それともこれから自分自身の身に起こる過酷な現実を予知したのか。
猟師さんに介添えしてもらいながら、槍のような刃物で心臓をめがけて一突きしたとき、雌鹿は悲鳴のような鳴き声をあげ、激しくのたうち回った。血が次々と流れ出、明らかに苦しそうに、身をよじらせる。しかし徐々に動きは大人しくなり、やがて動かなくなる。意識も遠のいていっているようだった。まさに今、眼の前で、命が失われようとしている。
只事ではないと思った。ひとつの命が失われるということは只事ではない。しかも手をかけたのはわたし。只事ではない。
鹿の解体精肉が終わったら、残った鹿の死骸をさらに部位ごとに分割し、軽トラに積んで山奥へ捨てに行く。適当なところで軽トラを停め、道路沿いの谷底目がけて鹿の部位を放り投げる。
放り投げている最中、雌鹿の皮にきれいな斑点模様があることに気づく。そう言えばアニメのキャラクターかなんかで、斑点模様がある雌鹿のキャラクターがいたことを思い出した。ああ、こういう斑点模様ってほんとにあるんだな、などと思いながら雌鹿の部位を放り投げた。
わたしが今放り投げている物体は、鹿と呼ばれる生き物だった。ほんの何時間か前、その体内には血液が巡り、野山を駆け廻っていたはずだ。それが何の因果かこうなった。美しい斑点模様は流れ出た血で赤黒く染まり、谷底へと消えていく。
なんと罪深いことをしているのだろう。
わたしは鹿を殺し、その体をバラバラにし、今はこうして谷底へ放り投げている。このときも念佛を唱えずにはいられなかった。
ところでわたしは一体誰のために念佛を唱えているのだろうか。自分のため?自分が地獄に落ちるのが嫌だから?もちろんそれもあるだろう。
それとも鹿のため?どうかこの鹿が安らかに眠ってくれますように、成佛できますように。そういった鹿に対する懺悔の気持ちを含んだ念佛でもあっただろうか。
あるいは誰かのため、何かのためではなく、一連の出来事を経て自然に湧き起こってきた念佛だったのかもしれない。
しかしこんなことを言っているわたしも、いずれは慣れてしまうのだろう。忙しい安泰寺の生活のなかでは、いちいちこんな感傷に浸っている暇はない。鹿を解体精肉する作業も、慣れてしまえばそれこそ単なる“作業”でしかなくなるだろう。残った死骸を山奥に捨てに行くのだって、安泰寺の敷地の外に出られるまたとないチャンスだし、マニュアル車を運転する気分転換のドライブでしかなくなるかもしれない。
だからわたしは己に課することにした。今後、鹿の作業に携わるときは、必ず心のなかで念佛を唱えること。今このときの気持ちを忘れないために、義務として自分自身に課した。
いや、何もそれは安泰寺でいただく鹿だけの話ではない。スーパーマーケットに並んでいる肉のブロックや、パッキングされた野菜にしたってそうだ。わたしたちは何かしら他者の命を奪わない限り、自分自身の命をつなぐことはできない。
どうかそのことを忘れないように。
南無阿弥陀佛。