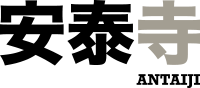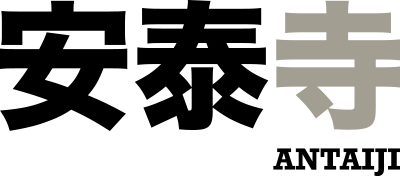Die Liebe zur Mitte hin und die Liebe aus der Mitte heraus
2-5
Ich: Was denkst du über die Liebe?
Penetre: Es gibt zwei Arten der Liebe: Die Liebe, die vom Rand der Welt auf deren Mitte gerichtet ist, und die Liebe, die aus der Weltmitte bis an den Rand reicht. Angenommen, du bist in ein Mädchen verliebt. Dann liebst du so wie einer, der vom Rand der Welt in die Mitte blickt.
Ich: Das kann ich nicht beurteilen, denn so verliebt war ich noch nie. Aber das, was du über den Rand und die Weltmitte sagst, erinnert mich an etwas anderes: Wenn ich für mich allein Musik höre, fühle ich mich manchmal sehr einsam, wenn mir bewusst wird, dass ich in dem Augenblick wahrscheinlich der einzige Mensch im Universum bin, der diese Musik hört. Deshalb sehe ich lieber fern oder höre Radio. Denn selbst wenn das Programm total uninteressant ist, habe ich doch die Gewissheit, dass ich nicht allein bin: Unzählige andere sehen oder hören in demselben Augenblick dasselbe Programm. Ich finde es tröstend, mir das bewusst zu machen. Irgendwie fühle ich mich dann mit der Welt verbunden.
Penetre: Das Zeitgeschehen, an dem wir durch Fernsehen und Radio teilhaben, verbindet uns auch in einem gewissen Sinn mit der Welt – wenn sich beispielswese etwas Wichtiges auf der Welt ereignet, wird es sofort live übertragen. Aber ich meine etwas tieferes, wenn ich von der Weltmitte spreche. Die Weltmitte ist der Ursprung, aus dem alle Dinge ihren Sinn beziehen. So nah du auch am Zeitgeschehen sein magst, du kannst trotzdem noch das Gefühl haben, nicht mit der Weltmitte verbunden zu sein. Wenn du dagegen das Gefühl hast, in einer Person der Weltmitte zu begegnen – dann liebst du diese Person.
Ich: Du hast aber auch gesagt, dass es eine Liebe gibt, die von der Weltmitte aus an den Rand reicht.
Penetre: Genau! Wenn du die Sicherheit in dir selbst gefunden hast, mit der Weltmitte verbunden zu sein, und diese innere Sicherheit auch mit den Menschen ganz am Rand der Welt teilen willst, dann ist das ebenfalls Liebe.