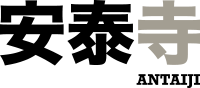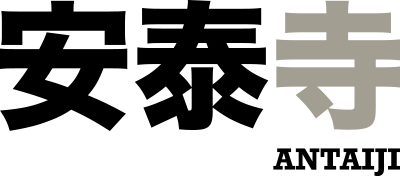キリスト教、仏教、そして私・その24
仏教と人権
キリスト教の物語はクリエーションから始まりますが、仏教のコスモロジーでは創造主を問題にしません。「この世界は誰の手によって創造されたか」と問われれば、「それは各々のカルマによって作られている」と答える仏教の哲学者もいるかもしれません。あるいは、人間社会がいわば自然発生した過程を微笑ましく描いている『起世因本経(Agganna Sutta)』という古いお経があります。それによれば、宇宙がビッグバーンとビッグクランチを繰り返している合間に、人類は進化の結果ではなく、執着と堕落の結果として発展しました。しかし世の始まりについて、ブッダ自身は沈黙していたはずです。あるいは聞き返していたかもしれません。「世界は神によって創造されたとあなたは言うけれど、その神は誰の手によって創造されたのだろうか」
いや、そんなことを考えているのは、私だけでしょう。それはともかく、仏教の場合はブッダの教えを信じるかどうかではなく、それを実践するかどうかがポイントです。ブッダは神の存在にも、死後の世界にも言及しておらず、もっぱら私たち人間が自らブッダになる方法だけを説き続けていました。一神教では人間が逆立ちしても神にはなれませんが、仏教では誰でもブッダになれるのです。その意味でも仏教は「レリジョン」というより、人間が人間のために説く、もっとも人間らしい生き方です。
インドで仏教の復興のきっかけをつくったのはアンベードカル博士(1891年~1956年)。「不可触民解放の父」が着目している宗教は、カースト制度を支えてきたヒンズー教ではなく、また欧米のキリスト教でもなく、本場で長い間絶えていた仏教なのです。欧米の自由・平等・命といった人権の考えが、人間が神により近い存在とするキリスト教に立脚していますが、仏教と人権の相性はいかがなものでしょうか。
仏教と人権には深い関わりがないと思われるかもしれませんが、とんでもない。カースト制度が神々によって決められていたと頑なに信じられていた昔のインドで「それは根拠のない迷信だ!」と喝破したのが実は釈尊でした。
『起世因本経』のポイントも、いかにして世界が成立しているかというような自然哲学的なものではありません。釈尊は本当は目の前にいる人間の生き方にしか感心がありませんでした。『起世因本経』の背景にあるのは、ほかでもなく社会差別です。先ほど要約したテキストの前後の文脈を注意深く読めば、それが分かります。
お経の序文に当たる文書で、釈尊は二人の弟子に声をかけています。
「あなた方はバラモンの出身らしいが、周りのバラモンからの中傷は受けていないか」
「受けています」
「それはたとえどんなものだろうか」
「彼らはいうのです、『バラモン階級こそ最上のカーストであり、下級のカーストとは違う。バラモンは清い、下級は穢れている。バラモンはブラフマー(梵天)の子であり、ブラフマーの口から生まれた。君たちはどうしてバラモンを捨て、最下級のシュードラ(隷属民)となんらかわらない出家の身分を選んだのか。彼らはブラフマーの足から生まれたものに過ぎないではないか』」
「もしバラモンたちがそういうならば、彼らは自分の足元を見失っているはずだ。バラモンの女性は月経もあれば、妊娠をすることもあるのではないか。赤ちゃんを産み、自分の乳を与えているのではないか。女性の股から生まれたはずなのに、どうしてブラフマーの口から生まれたというのだろうか。彼らはブラフマーを冒涜していて、うそをついているのだ」
カースト制度由来である、ヒンズー教の物語をはっきりと「うそ」といい、バラモンといえども同じ人間の子ではないかという鋭い指摘からこのお経が始まっています。それなら、現在の不可触民がブッダの教えをよりどころにするのも頷けます。
続いて、前述したように世界の成立が説かれます。やがて人類がおいしいものに目を奪われ、性に目覚め、堕落する。かようにして浮気・盗み・うそ・殺しなどの諸悪は「発明」される。そこで人々が相談し、警備隊を作ろうと決めた。それはクシャトリヤという武士のカーストの由来。また、善悪に目覚めた以上、人々の間に善を普及させ、悪をやめさせるのがバラモン階級。他にも商いにかけているもの、手先の器用なものなどが仕事分担をした。
そうしてカースト制度が出来上がったというのがこの『起世因本経』の教えです。出家をするためには、カースト制度の枠を突破しなければなりません。釈尊の弟子の中にはバラモン出身のものもいれば、シュードラ(隷属民)もいたのですが、出家している以上、皆平等でした。同じ人の子です。それぞ れが自己をよりどころとし、自由でした。日本のお坊さんがいまだにお布施の額によって戒名を決めて、あの世にまで階級をつけていることを考えれば、釈尊は今日の僧侶よりもはるかに進歩的だったといわざるを得ません。
(ネルケ無方、2014年8月6日)