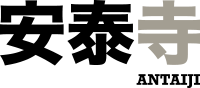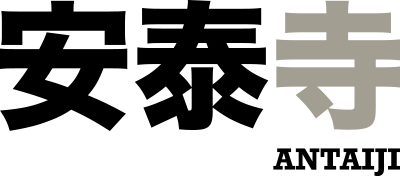キリスト教、仏教、そして私・その26
愛という名のバトルフィールド
ラブ・アンド・ウォーよきにつけ悪しきにつけ、私の精神成長に多大な影響を与えてきた「愛の宗教」ことキリスト教。英語には ”All is fair in love and war” ということわざがあります。その意味は「勝てば官軍」に近く、愛と戦争は手段を選ばないというものです。ユダヤ・キリスト教の歴史を見ても、まさにそんな感じです。このエッセイでは聖書を紐解きながら、ユダヤ・キリスト教で語れる「愛」の裏を読んでみたいと思います。
キリスト教で使用されている聖書は二つの部分からなっています。旧約聖書と新約聖書です。『旧約聖書(The Old Testament)』にあたるものは、ユダヤ教で『タナハ』と呼ばれている聖典をそのまま受け継いだものです。なぜ旧約聖書と呼ぶかといえば、この中で取り交わされた神と人間の契約を旧いものとするからです。キリスト教の考えでは、イエスの到来によって契約が更新されたため、福音書やパウロの手紙などを新約聖書と呼ぶのです。ではなぜ旧い契約を捨てなかったのか。それはキリスト教にとって旧約聖書が捨ても捨てきれないルーツ(根っこ)だからです。
旧約聖書はユダヤ民族の歴史書でもあり、詩集でもあり、預言集でもあります。さらに律法の立脚点にもなっているこの書物は、中近東の文明史を背景に成立したことはあえていう必要もありません。エジプト・シリア・メソポタミア・ペルシア・インドの文明にはそれぞれのコスモロジーと生活のルールがあったのです。今からやく四〇〇〇年前、世界の広い地域でほぼ同時に、人々は世界の成り立ちや人類のルーツから、民族のアイデンティティや生活のルールまでについて、いろいろと考えはじめていたようです。その当時の聖典は、そのまま世俗の法律という性質もあった。また硬貨がそのころから流通し始めたのも、けっして偶然ではないと思います。既に見てきたとおり、聖書のいたるところにも「シケル」すなわちお金の話が出てきます。お金が絡んでくれば、人間は法律を持ち出します。
その聖書はなぜ作られたのか。ひとつの目的は、エジプトを始め、すでに影響を発揮していた古い文化との差別化だと私は思います。つまり、聖書は独立宣言の性質が強い。イスラエルの内部に向けても、律法すなわち法令という側面があります。それから歴史書でもあり、民族の万世一系の証明という意味でアダムとイブの代から系図を詳細に記されています。 不思議な家族
ユダヤ人の祖先については諸説ありますが、アラビア半島を旅していた遊牧民という可能性があります。しかし民が自らのアイデンティティを見つけたのはそのあとです。ユダヤ教の発祥地とされているのは、現在のイスラエルです。今は再びユダヤ人が住んでいますが、デイアスポラといって民が故郷を追放されて千数百年ものあいだ世界中に撒き散らされた歴史があるのです。そこに至るまでの一列の事件も聖書に書かれています。イスラエルを四方を囲んでいる現在のアラブ諸国はイスラム教圏です。一方のキリスト教はイスラエルからスタートし、主に欧米に広まりました。
ユダヤ教、キリスト教とイスラム教は仲が悪いと言われています。同じ一神教徒同士はどうしてあんなに激しく戦わなければならないのか、不思議に思う日本人も少なくないでしょう。いや日本人でなくても、私だってそう思います。
ところが、三者のルーツは同じ、神も同じ、聖典もほぼ同じです。簡単にご説明しましょう。
キリスト教のポジションから見れば、新約聖書は旧約聖書の「パート2」と呼べるものです。その中にある「イエスこそ神である」という主張こそが、ユダヤ教とキリスト教を隔てる決定的なものです。ユダヤ教の『タナハ』には、イエスの「イ」の時も出てきません。ユダヤ教徒は今もメシアの到来を待っているのです。むろん新約聖書を認めるわけがありません。
しかしイエスをはじめ初期のクリスチャンは、自分たちが正統的なユダヤ教徒であるという自負があったようです。イエスは、自ら「キリスト教徒」と名乗ったことはもちろん一度もありません。「クリスチャン」という名称が使われるようになったのは、どうやら一世紀の中頃、イエスがなくなった後のことです。それでも新しく誕生したキリスト教の教会は旧約聖書をけっして否定しませんでした。イエスこそ旧約聖書(つまり『タナハ』)の中で約束されていた救世主だ、と主張していたからです。キリスト教はつまり、ユダヤ教の聖典を立脚点にしているのです。その一方で、ユダヤ教徒はイエスのことを救世主として認めてはいません。彼らは今も救世主の到来を待っているのですから、イエスによって新しく交わされた契約である新約聖書をユダヤ教徒が認めるわけがありません。
では、キリスト教と対立しているように見えるイスラム教はどうでしょうか。
イスラム教の聖典である『クルアーン』(『コーラン』とも)には、実はイエスが登場します。「イーサー」という名前で、やはり処女マリアの息子として生まれ、神(イスラム教では「アッラーフ」という呼び方にこだわっているらしい)の言葉を語っています。新約聖書と同じように、多くの奇跡を働いた後、天に昇ったことになっています。また、最期の日にイーサーが再びこの世に現れてくると、復活を予言する教えも、キリスト教と同じです。
キリスト教がユダヤ教の聖典に新約聖書を足したように、イスラム教は両方の聖典に、『クルアーン』を加えた形になっています。その『クルアーン』の中には、何度も「『クルアーン』は『聖書』の正しさを証明するためにある」とあるそうで、イエスの教えを否定しているわけではありません。
ところが、イスラム教とキリスト教に大きな違いがあるのも事実です。イスラム教では、イエスが預言者として位置づけられているのです。つまり、イエスはムハンマドと同様、神ではありません。それは唯一無比の神に子どもがいるはずがないからです。イエスが十字架で人類の罪を贖ったという教えも、イスラム教にはありません。そんな力が、預言者にはないからです。
つまり、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教はいずれも同じ唯一神を中心につくられていますが、イエスが登場するのはキリスト教とイスラム教だけ。そのなかで、イエスを神だとするのはキリスト教しかありません。
これが、ごくごく簡単に説明したユダヤ教、キリスト教とユダヤ教の関係です。家族の例えで言うと、「僕は99%、お父さんの息子」というのがキリスト教。「でも、お父さんは年をとっていたから、今は世代交代」
一方でイスラム教は「アニキは威張っているけど、お父さんの意思を受け継いでいるのは弟の僕だよ」
そして「そんな二人、オレは知らん」と親子関係を断固認めないというのがユダヤ教。 「モーセ五書」―一神教との共有財産
さて、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教に共通しているのが、「モーセ五書」と呼ばれる『創世記』『出エジプト記』『レビ記』『民数記』『申命記』です。ユダヤ教での名称は「トーラー」、その意味は立法です。伝説ではモーセが書いたことになっていますが、ほとんどの学者はそれを否定しているようです。
「モーセ五書」を読むのは、小学校一、二年生の時が多いです。グリム童話をはるかに超えるその酷さに、私は息を飲んでいたことを今も鮮明に覚えています。ここでその概要のみをわかりやすくまとめたいと思います。
『創世記』ではまだ遊牧民の神話の影響が強く残っています。クリエーション(世界創造)の話からスタートし、ノアの方舟やスカイツリーよろしくバベルの塔の崩壊を経て、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の太祖と言われているアブラハムとその子孫の話で終わります。アブラハムには八人も息子がいましたが、その最初の二人について、ユダヤ・キリスト教とイスラム教では記述がかなり食い違っています。イスラム教によれば、エジプト人女性のハガルとのあいだに生まれた長男イシュマエルは父と二人で聖地メッカのカアバ神殿を建てました。
一方のユダヤ教の伝記でアブラハムは妻サラの声に従い、イシュマエルとハガルを砂漠の中に追放し、次男イサクにあとを継がせました。そしてイシュマエルはアラブ人の祖先、イサクはユダヤ人の祖先になりました。イサクの次男ヤコブはやはり母と共謀し、長子の権利を横どった男です。彼には一二人も息子がいましたが、一一番目のヨセフを事の他に可愛がっていたことが災いし、その子が上の一〇人にいじめられて、やがて奴隷としてエジプトに売られてしまいした。
ヨセフはエジプトでめげることなく、自力で叩き上げた男。幾度の苦難を乗り越えて大祭司の娘と結婚し、やがて天下を取ります。その手口がまたすごい。
ヨセフは夢の告げで、凶作に備えてたくさんの穀物を蓄えていた。そこまではいいのですが、それを困っていた農民に法外な値段で売っていた。金のない者には家畜を売らせ、家畜のなくなった者には土地を売らせた。やがて土地を全部なくした農民がどう生きながらえてか。答えは簡単。
「ヨセフはエジプトの国境のこの端からかの端まで民を奴隷とした」(創世記47:21)
悪徳商法の元祖に思えるヨセフの〝サクセス・ストリー〟で、『創世記』が締めくくられています。
『出エジプト記』―一神教のシネマスコープつづく『出エジプト記』の主人公はモーセです。内容はタイトルのとおり、モーセが率いるユダヤ人のエジプトからの脱出です。その際、「葦の海の奇跡」が起きました。紅海の岸で行き止まりになっていたとき、困っていたモーセたちの前で水は左右に割れて、エジプトで虐げられていた民は危機一髪で助かった。あとから追いかけてきたエジプト人が波に飲み込まれるのは映画の名シーンにもなっています。
聖書の宗教的な意味合いが濃くなるのは、ここからです。モーセはシナイ山の山頂で神に会い、その名前を訪ねます。神の答えは、「わたしは、有って有る者」。
「有って有る者」の言語はYHWHです。ヘブライ語を書くとき、母音は表示されないので、発音については諸説があります。また、YHWHは神の名前だから、ユダヤ教ではそれを汚さないために口にしないのが原則です。それほど厳格ではないクリスチャンは「エホバ」とも「ヤハウェ」とも言います。発音はバラバラで、YHWHの意味についても諸説はありますが、「わたしは有る者」という言葉は存在そのものと解釈できます。
そこでモーセは神より石に彫った戒めを受けます。「わたしのほかに神があってはならない」殺してはならない」「姦淫してはならない」といった、例の十戒です。そして住む場所のなかったイスラエルの民にカナンという「乳と蜜との流れる地」を約束します。その条件は、命令に絶対服従すること。次は契約を結ぶ、大事な場面です。
「見よ、わたしは契約を結ぶ。わたしは地のいずこにも、いかなる民のうちにも、いまだ行われたことのない不思議を、あなたのすべての民の前に行うであろう。…[中略]…あなたが行く国に住んでいる者と、契約を結ばないように、気をつけなければならない。…[中略]…むしろあなたがたは、彼らの祭壇を倒し、石の柱を砕き、アシラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名を『ねたみ』と言って、ねたむ神だからである」(出エジプト記34:10~14)
YHWH以外の神と契約を結んではいけないというだけなら、話はまだわかります。しかしここで神が言っているのは、隣国の人々とも契約を結んではいけないということです。ほかの神を信じる者とお仲良しするだけでもダメだ、とうわけです。なぜなら、神の本質が「妬み」だからです。
「モーセ五書」を小学校の宗教授業で教えるのは、せいぜいここまでです。ここからは、ハリーウッド映画にも例のない露骨なバイオレンスが始まるからです。
戒めを手に入れたモーセが山を下りると、待ちきれなかった民が金の子牛を拝んでいるのではありませんか。ご存知のように、それこそ神が一番嫌っていることです。仲間を自分の集めて、モーセは命じました。
「イスラエルの神、主はこう言われる、『あなたがたは…[中略]…おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ』」(出エジプト記32:27)
『レビ記』―細かすぎる生活マニュアル
「モーセ五書」の三番目である『レビ記』はキリスト教であまり重要視されていません。そこにはもっぱら、後のキリスト教で無効とされた律法が書かれているからです。『レビ記』はつまり、ユダヤ教徒のための実践マニュアルです。祭壇の供え物から性交に関する決まりまで、細則に記せられています。豚肉とタブーとしているのも『レビ記』です。同性愛にたして、死刑は定められています・
「女と寝るように男と寝る者は、ふたりとも憎むべき事をしたので、必ず殺されなければならない」(レビ記20:13)
獣姦をした者が殺されるだけではなく、犯された動物まで殺さなければならないなど、納得しづらい部分も多々あります。これらの決まりの中には、日本の神道に近い「汚れ」に対する恐れを感じます。
「女に流出があって、その身の流出がもし血であるならば、その女は七日のあいだ不浄である」(レビ記15:19)
キリスト教には「汚れ」の概念がありません。それはイエスによる贖いと関係しているかもしれません。キリスト教の考えでは、イエス自身が供え物です。神が人類の罪を贖うために自ら捧げた供え物、それがイエスの正体。そのため、人間が神に供え物を捧げる必要はなくなりました。一方のユダヤ教とイスラム教では、神に捧げることが大事です。それは日本の神道も同様。仏教では本来、ブッダに供え物を捧げるよりも、みずからブッダになる(つまり、自分自身を仏道に捧げる)ことが大事にされます。かと言って、お寺の本堂に何を供えてもいいというわけではないらしい。
私がまだペーペーの頃です。参禅者から頂き物があった場合、叢林で消耗するまえに、まず本尊にお供えすることが鉄則ですが、ある日はたくさんのトイレ・ペーパーをもらいました。「本尊だって、用を足すこともあるかもしれない」という思いから、私はそれ当たり前のように本堂の須弥壇にお供えしました。師匠にカンカン怒られたのは今も覚えています。
つづくのが『民数記』。その名称は、人口調査の記述が多きことから来ています。数字の羅列はいくら私でもややくどく感じられますが、すさまじい記述もあります。約束の地カナンに向かって民が砂漠をさまよっている途中、いくたびもほかの民と戦争をします。神の力のおかげで、イスラエルの民は負けることを知りませんでした。
「主がモーセに命じられたようにミデアンびとと戦って、その男子をみな殺した。…[中略]…またイスラエルの人々はミデアンの女たちとその子供たちを捕虜にし、その家畜と、羊の群れと、貨財とをことごとく奪い取り、そのすまいのある町々と、その部落とを、ことごとく火で焼いた」(民数記31:7~10)
捕虜とかすめた戦利品を見て、モーセはなんといったと思いますか。
「あなたがたは女たちをみな生かしておいたのか。…[中略]…子供たちのうちの男の子をみな殺し、また男と寝て、男を知った女をみな殺しなさい。ただし、まだ男と寝ず、男を知らない娘はすべてあなたがたのために生かしておきなさい」(民数記31:15~18)
従軍慰安婦の強制連行ではありませんが、昔から戦争と性は背中合わせになっていたようです。ここで注目すべき点は、虐殺が神の命令とされていることです。「殺してはならない」という戒めが適応されるのは、神に忠実なユダヤ人のみです。それ以外の敵なら、たとえ女や子供であれ、殺しても構わないというわけです。
『申命記』―モーセの遺言「モーセ五書」の最終書である『申命記』では、死ぬ間際のモーセは三つの説話でもう一度、神との契約を繰り返しています。
「あなたの神、主が嗣業として与えられるこれらの民の町々では、息のある者をひとりも生かしておいてはならない」(申命記20:16)
こう言った「神の命令」は今の言葉で言えばジェノサイド(大量虐殺による抹消行為)でしかありませんが、ヘブライ語では「へーレム」と言います。その言葉は「聖絶【ルビ せいぜつ】」と日本語に訳され、「ささげられたもの」と同時に「のろわれたもの」をも意味します。
微笑ましい決まりもたくさんあるのもまたユダヤ教です。コスプレ禁止から建築の安全対策まで、気配りが行き届いています。
「女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。…[中略]…鳥の巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥がその雛または卵を抱いているならば、母鳥を雛と一緒に取ってはならない。…[中略]…新しい家を建てる時は、屋根に欄干を設けなければならない。それは人が屋根から落ちて、血のとがをあなたの家に帰することのないようにするためである。…[中略]…身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない」(申命記22:5~12)
もしイスラエルの民がこれらの約束を守れば、神はその栄光を保証するとしています。万が一のために、守れなかった時の呪いも具体的な言葉で述べられています。
「あなたは盲人が暗やみに手探りするように、真昼にも手探りするであろう。あなたは行く道で栄えることがなく、ただ常にしえたげられ、かすめられるだけで、あなたを救う者はないであろう。あなたは妻をめとっても、ほかの人が彼女と寝るであろう。家を建てても、その中に住まないであろう。ぶどう畑を作っても、その実を摘み取ることがないであろう。…[中略]…あなたのむすこや娘は他国民にわたされる。あなたの目はそれを見、終日、彼らを慕って衰えるが、あなたは手を施すすべもないであろう。あなたの地の産物およびあなたの労して獲た物はみなあなたの知らない民が食べるであろう。あなたは、ただ常にしえたげられ、苦しめられるのみであろう」(申命記28:29~33)
リストはこのあとも延々と続きます。
「モーセ五書」は約束の地カナンの占領の手前で終わってしまいます。モーセ自身はカナンに入ることを神に許されなかったからです。その理由は、モーセは神の目に臆病者に映っていたたからです。そう、神が望んでいたほど、モーセとその仲間が好戦的でなかったようです。
カナンの占領は「モーセ五書」に続く『ジョシュア記』の中で描かれています。まず古代オリエントの中でも古いと言われている「エリコ」という町が滅ぼされてしまいます。
「祭司たちはラッパを吹き鳴らした。民はラッパの音を聞くと同時に、みな大声をあげて呼ばわったので、石がきはくずれ落ちた。そこで民はみな、すぐに上って町にはいり、町を攻め取った。そして町にあるものは、男も、女も、若い者も、老いた者も、また牛、羊、ろばをも、ことごとくつるぎにかけて滅ぼした」(ジョシュア6:20~21)
「アイ」と可愛らしい名前の町の運命も同じでした。
「ヨシュアはアイの住民をことごとく滅ぼしつくすまでは、なげやりをさし伸べた手を引っこめなかった。ただし、その町の家畜および、ぶんどり品はイスラエルびとが自分たちの戦利品として取った。主がヨシュアに命じられた言葉にしたがったのである」(ジョシュア8:26~27)
その残虐極まりない武勇伝はいつまでも続きます。
一神教と排他主義ここで誰しも疑問を持つでしょう。
「この民が信じているYHWHは一体なにものなのか」
ユダヤ・キリスト教の神は唯一、絶対、全知全能であったはずです。しかしその割には、このYHWHはあまりにもお粗末な神ではありませんか。
この疑問はユダヤ教の成り立ちを理解するための手がかりとなっています。実は、ユダヤ教はそもそも一神教ではなかったのです。世界のあらゆる宗教がそうであったように、ユダヤ教も最初は複数の神々を認めていたとされています。YHWHはその一人にしかすぎません。ところが、たくさんいる神々のうち、どうもYHWHは一番力強いとユダヤ人が気づいた(思い込まされた?)時から、ほかの神々の崇拝は次第に白い目で見なされるようになりました。日本の神道でも神々が喧嘩をすることがあるそうですが、YHWHももともと、喧嘩好きな神だったのです。
その神はまた事の他に嫉妬深いので、「わたしのほかに神があってはならない」というのを一番目の戒めとしていたのです。その時点ではまだ全知全能でも、唯一でもありません。そうではなくて、たくさんいる神々の中、YHWH以外を拝んでは池ないないということだったのです。
そういう宗教を、学者は「一神崇拝(monolatry)」と呼んでいるそうです。一神崇拝と一神教の違いは、ほかの神々の存在を認めるかどうかという点にあります。一神崇拝はほかの神々の存在を認めた上で、それらの崇拝を禁じてしまいます。さらに排他的になれば、それらたの神々の祭壇を破壊し、その信者を根絶させようとします。それができるのは、一神崇拝です。
では、一神崇拝いつ一神教になったのか。私はイエスの頃まで、YHWHはユダヤ民族の氏神という色合いは濃かったと思います。そう、私はイエスが信じていた神が、今日のクリスチャンが信じている神とは違うと思います。神がYHWHという氏神から脱皮し、普遍的な神になったのはイエスの十字架のあとだと私は思います。
一神崇拝と一神教はどちらも排他的ですが、その排他性は違った形で表れています。たとえば、一神崇拝が布教をしないのに、一神教の信者はやたらミッションに力を入れています。一神崇拝は「民の神」を拝んでいるから、それを他の民に信じてもらおうという発想はそもそも湧いてこないのです。ほかの民を殺しても、回心させようとしないのが一神崇拝。一方の一神教は、扉は広く開いているように見えます。誰でも入信できますが、入信しない者が迫害されることは歴史が示しているとおりです。 宗教界の「ヒットラー」と「スターリン」
一神崇拝と一神教の関係をわかりやすく説明するなら、ヒットラーとスターリンのようなものです。
ヒットラー率いるナチスは思想というより、民族の運動でした。その信念は「ゲルマン民族は一番」。ゲルマン人以外は存在価値がないから、ほかの民族は虐殺しても良いという理屈にもなります。ドイツでナチス運動が起こった当初、実は少数ながら党員の中には「愛国心あるユダヤ人」もいたのです。彼らはユダヤ人でありながら、ドイツを愛し、ヒットラーを慕っていたのです。
彼らがホロコーストを免れなかったのはいうまでもありません。それはナチスが一神教ではないからです。ユダヤ人に生まれていれば、逆立ちしてもナチスには認められませんでした。
いっぽうスターリンは徹底した粛清を行い、数百万人をグラグ(強制収容所)に送り込んでいます。それも抹消行為には変わりありませんが、その主な理由は思想犯です。スターリンの目標は共産主義をソ連のみならず、世界のすみずみに広げることでした。ヒットラーの民族浄化と違い、そのために多民族を殺す必要はありません。殺すのではなく、革命によって世界諸国を共産主義にし、反革命家のみをグラグに送り込めばいいのです。それがまさに、一神教のやり方です。
しかし一神教が排他的になるのは、考えが浅いからだと私は思います。一神教が徹底していれば、排他的にはならないはずです。一神しか存在しないなら、どうしてほかの宗教の神々を否定し、その信者を責める必要があるのでしょうか。神が一人(一神)なら、世界の宗教が崇拝している神々は実は同じものの違った形でしかなかった、いうのが徹底した一神教の結論でなければなりません。あるいは東洋の宗教のように、《そのもの》をたとえ「道」と言い、「無」といい、「天」といい、それらはみな同じはずです。
ユダヤ・キリスト教は今日まで、そこまで徹底した一神教には発達してきていません。私の目には今でも、中途半端な一神教に見えます。中途半端な一神教とはどういうものか。神を唯一としながら、ほかの神々と否定とする。神の一存で、ある特定の民族や特定の個人が損した利得したりと思うこと。そもそも神に人格のあることも、私には不徹底しているように思えます。
では、これから本当の意味でも一神教に発達できるかと問われれば、残念ながら、それも疑わしい気がします。すなくとも、人格神へのこだわりを捨てなければ、排他性から出し得ないと思います。 バビロン捕囚―ユダヤ民族のアイデンティティ・クライシス
先を急がず、聖書の成り立ちとユダヤ民族の歴史に戻りましょう。
旧約聖書のそれぞれの書は、そのときそのときの現場中継のような形で書かれたわけではありません。エジプトからの脱出にせよ、そういう事実があったかどうかということじたいは定かではありません。歴史学者によれば、カナンの占領は紀元前一二五〇年ごろから行われていたそうです。カナンのユダヤ人が国家を作り上げたのは紀元前一〇世紀前後。日本では「イスラエル」といえば国名、「ユダヤ」といえば民族もしくは宗教を指すことが多いですが、実は現在のイスラエルの国土の南方にはユダヤ、北方にはイスラエルという二つの国があったようです。最初は栄えましたが、やがて旗色が悪くなり、隣国の餌食にされたようです。豊な土地のあるイスラエルはアシリアに滅ぼされてしまい、南のユダヤも紀元前六〇〇年頃にはバビロンに占領されました。その時、ソロモン王が紀元前一〇〇〇年ごろ建てたエルサレムの神殿が崩壊されたことはユダヤ人にとって何よりものショックだった数です。
敗戦したユダヤ人はバビロンに捕虜として連行されました。いわゆる「バビロン捕囚」です。それは当時のバビロン王国が用いた制度で、占領された国民のエリートだけを首都バビロン(現在のバグダードよりやく九〇キロ南方)で生活させるといったものでした。徳川時代の参勤交代のようなもので、ただしこの場合は「交代」がありません。それがなんと六〇年間も続いたそうです。ユダヤ民族がすべてバビロンに連れられたわけではもちろんなく、上流階級のみが故郷を離れてすまなければならなかったようです。
彼らにとって大きなクラシスとなったこの六〇年間は、後のイスラエルを定義付けることになっています。といいますのは、「モーセ五書」を含む旧約聖書のほとんどの書は、この時代に再編集され、書き直され、もしく新しく書かれているとされています。いつの時代のどの国でもそうですが、イスラエルの歴史もまたあとから人工的に「作られた」歴史です。その歴書でもある旧約聖書に表れているのはれ歴史的事実ではなく、ユダヤ人の自己理解なのです。その時に彼らの胸の中には、望郷と憎しみが背中合わせだったようです。バビロンでは、こんな詩も歌われました。
「われらはバビロンの川のほとりにすわり、シオンを思い出して涙を流した。…[中略]…
われらを苦しめる者が楽しみにしようと、『われらにシオンの歌を一つうたえ』と言った。われらは外国にあって、どうして主の歌をうたえようか。…[中略]…
破壊者であるバビロンの娘よ、あなたがわれらにしたことを、あなたに仕返しする人はさいわいである。あなたのみどりごを取って岩になげうつ者はさいわいである」(詩篇137)
「みどりご(嬰児)」という耳慣れない日本語は、生まれたばかりの赤ちゃんのことです。
神と契約を結んでいたユダヤ民族は虐殺に虐殺を重ね、国を勝ち取ったと思えば、やがてバビロンの属国に成り下がってしまいました。仏教的に考えれば、それは自業自得な話です。そこで怒りの心を忘れて、これからは隣国と平和に暮らそうと思い立っていればいいのに、「私たちがこんな目にあっているのは、神との契約を守らなかったからに違いない」とユダヤ人は解釈したようです。
ユダヤ教の中で終末論が盛んに称えられるようになったのも、この時からです。一方で、メシアの到来を預言する者も現れました。
ここでまずメシアとは何か、ということを考えなければなりません。「救世主」という日本語訳からは、「メシア=神」という印象を受けますが、メシアの本来の意味は「油を塗られた者」で、祭司や王を指すことが多い。ペルシアの王だったキュロス二世が紀元前五三九年にバビロンを征服し、ユダヤ人たちを開放したっため、やはり「メシア」という名称で呼ばれています。メシアはつまり、ユダヤ人の助っ人といった位の意味です。
ユダヤ人がバビロン捕囚から解放されたあとからも、ユダヤ人はアレクサンドロス大王に征服されたり、やがてローマ帝国の属国になってしまいました。紀元直前に、ヘロデ大王の傀儡政権が支配をふるっていました。ヘロデは二番目の妻と二人の息子を始め、気に入らない者を躊躇することなく排除するような男でした。聖書の中でも彼が登場し、イエスが生まれた時に幼児虐殺を命令したことになっています。
ヘロデ大王亡き後のイスラエルは三つの地区に分けられ、いずれもローマ帝国に傘下に置かれました。当時の様子を考えれば、現在のアフガニスタンやイラクのような無法地帯を創造します。「おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ」というモーセの言葉の通り、ローマ帝国の役員とその手下は現状を維持するために手段を選ばない。神殿の祭司や律法学者は宗教を武器に、自らの権力だけを守ろうとする。いっぽう、様々の武装グループが立ち上がり、独立運動を起こす。そして一般市民はこのパワー・ゲームになるべく巻き込まれないように、じーっと忍んでいたのではないでしょう。旧約聖書に書かれている「世の終わりが近い」「メシアは今にも到来する」と言ったメッセージが彼らに素直に受け取られたのも無理がありません。
(2014年8月11日、ネルケ無方)