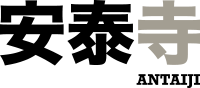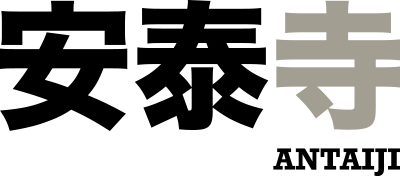キリスト教、仏教、そして私・その28
イエスとその愛
エロスとアガペー、そしてフィリア新約聖書の原語はギリシャ語です。その中で愛を表すために最もよく使われている言葉は「アガペー」です。
ところが、愛を意味する言葉はギリシャ語にいくつもあります。
母子愛のように、生理的な愛情は「ストルゲー」。「お袋の味」から、生まれ育った故郷に対する愛情までが「ストルゲー」の中に含まれています。愛の対象を意識的に選択しないのがこの種類の愛の特徴。血に逆らえないのがストルゲー。
一方、「友愛」とも訳されるフィリアは同じ目的に向かっている同朋を結ぶ。それは血縁ではなく、自らの意思に基づいた選択です。この愛は相手に向けられているというより、双方を超えた理想に向けられていることが多い。
日本でもよく知られている「エロス」という言葉は、恋愛という意味。男女のロマンスはその典型。
そして神の愛、それがアガペー。そこから転じて、キリスト教では人が神へ向けている愛も、そして隣人愛もアガペーと言われるようになりました。フィリアと違い、アガペーは同志にとどまらず、敵まで及びます。敵・見方の溝を超え、宇宙全体に向けられているのがアガペーです。
アガペーはエロスと引き合いにされることも多いのです。エロスは肉体的かつ自己中心な愛として描かれることが多い。欲望を満たすために相手を自分のモノにしたい、それがエロス。いっぽう、アガペーは精神的な愛、自己犠牲を惜しまない愛。相手のために自分のすべてを与える愛、見返りを求めない愛、宗教的な愛です。
新約聖書の中で愛といえば、ほとんどの場合は「アガペー」です。「エロス」という言葉は一度も出てきません。アガペーこそキリスト教的な愛といえます。
一方で「フィリア」という言葉は聖書の中でも使われています。イエスと使徒の間の師弟愛こそが「フィリア」です。血縁があったのではなく、生理的に好きだったのでもありません。イエスとその使徒は神という同じ方向を向いていたから、師弟となったのです。
しかしフィリアという愛は排他的です。ひとつの方向を選ぶということは、それ以外の方向を捨てることを意味するからです。すでに見てきたとおり、イエスは「わたしのために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨て」ることを勧めています。フィリアをとるか、ストルゲーをとるか、という二者択一しかありません。イエスの次の言葉にも、その排他性が強く表れています。
「自分の十字架をとってわたしに従ってこない者はわたしにふさわしくない。自分の命を得ている者はそれを失い、わたしのために自分の命を失っている者は、それを得るであろう」(マタイ10:38~39)
イエスが使途たちの絶対的な信頼を期待していたように、彼も使途を絶対に信頼していたでしょう。愛弟子のペテロにはこう言っています。
「あなたはペテロである。そして、わたしはこの「岩」の上にわたしの教会を建てよう」(マタイ16:18)
イエスは以前からペテロを「ケファ」というニックネームで呼んでいたようです。「ケファ」をギリシア語に訳すと、「ペテロ」になりますが、意味は「岩」です。この発言からもわかるように、ペテロは「イエスの右腕」とも呼ぶべき重要人物です。イエスが彼を「ペテロ(ケファ)」と呼んだのは、彼を初期クリスチャン・コミュニティーの礎石と見なしたからでしょう。日本的な言い方をすれば、ペテロこそ弟子たちの中の大黒柱であったのです。
一方でイエスを裏切ったユダという使徒がいます。銀貨三十枚と引き換えに、イエスと対立していた司祭たちにその身柄を引き渡した人です。彼はその後、首吊り自殺をするのですが、これは実は裏切りではないというちょっと面白い説があります。ようするに、ユダこそイエスに一番忠実な弟子だったというわけです。なぜならユダがいなければ、イエスが磔に付せられることよって人類の罪を贖うこともできなかったはずです。ですから、神の計画を全うするためにイエスとユダは共演し、聖なる〝スクリプト〟に従ったに過ぎないというのです。イエスはズーパースター、そしてユダは自ら進んでヒール役をかったそうです。
面白いといえば面白い説ですが、『ルカによる福音書』では「ユダに、サタンがはいった」と書いています。イエスはユダに裏切られるのを前を持って知っていて、最後の晩餐の時も使徒に告げました。
「わたしと一緒に食事をしている者が、わたしを裏切ろうとしている…[中略]…その人は生れなかった方が、彼のためによかったであろう」(マルコ:18~21)
それを聞いた使徒達は口を添えて、「先生、まさか、私ではないでしょう」といった。そしてイエスの右腕とも言えるペテロはさらに主張した。
「たとい、みんなの者があなたにつまずいても、わたしは決してつまずきません…[中略]…たといあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは、決して申しません」
そんなはずはないと、イエスは愛弟子ペテロを見抜いていた。
「よくあなたに言っておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度わたしを知らないと言うだろう」
その日の夜、街を歩いていたイエスにユダが近づいて、接吻をしました。それがイエスを祭司たちに売り渡す合図でした。その時に様子を福音書は次のように伝えています。
「イエスは言われた、『ユダ、あなたは接吻をもって人の子を裏切るのか』。イエスのそばにいた人たちは、事のなりゆきを見て『主よ、つるぎで切りつけてやりましょうか』と言って、そのうちのひとりが、祭司長の僕に切りつけ、その右の耳を切り落した。イエスはこれに対して言われた、『それだけでやめなさい』」(ルカ22:48~51)
わが神、どうしてわたしをお見捨てたのか逮捕された祭司長の家で詰問され、つばきまでかけられた。しまいには顔をこぶしでボコボコにされた。その一部始終を中庭から眺めていたペテロに、通りかかりの人に三度も聞かれた。
「あなたも、あのイエスと一緒だった?」
それに対して、ペテロは「あなたが何を言っているのか、わからない」「そんな人は知らない」と、再三否定してしまった。
イエスはそれをあらかじめ知っていたということになっています。神の台本をイエスが承知していたはず。ならば、逮捕される前のイエスの動揺をどう説明すればよいか。
最後の晩餐のあと、イエスは使徒たちとゲツセマネという所に行って、彼らに頼んだ。
「わたしは悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、わたしと一緒に目をさましていなさい」(マタイ26:38)
それにもかかわらず、使徒たちはぐっすり寝てしまったのだ。その時、イエスは神に再三祈った。
「わが父よ、もしできることでしたらどうか、この杯をわたしから過ぎ去らせてください」(以上、マタイ26:21~39による)
ユダと共演したどころか、神に計画の変更をお願いしていたのです。そしていよいよ十字架に磔されたイエスの口から、次のセリフも出ます。
「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マタイ27:46)
私にはこうしたイエスのうめき声がとても芝居には思えません。「誰でもいいから、助けてくれ!」、それが人間イエスの本音だったと私は思います。そう思えるのは、私がキリスト教徒ではないからです。イエスが死んだあとに復活したというのも、私の中の「無方」にはとても信じることのできない話です。しかし、キリスト教徒にとってイエスは神です。イエスと神として復活させなければいけなかった必要があったのです。その心理はわかりますが、それを真理として受け止められるかと言われれば、私には無理です。
あなたは、わたしを愛するか私が信じていようが信じていまいが、福音書によればイエスは復活をしました。それ以降の話もまた、なかなか興味深い。漁に出ていたペテロたちは一匹も魚を捕れないところに、イエスは岸の方から「舟の右の方に網をおろして見なさい。そうすれば、何かとれるだろう」と叫んだ。そうしてみると、一五三匹も魚が網に引っかかったそうです。私が住んでいる日本海側の港町も、そんな程度の〝奇跡〟はしょっちゅう起きていますが、復活したイエスが自分のそのような形でアピールしなければならなかったことはなんとも微笑ましく感じられます。
使徒たちが船を陸にあげている間、イエスは炭火を起こして魚を焼き始めた。そして皆でパンを食べながらバーベキューをしているその時、イエスはペテロに聞いた。
「あなたはこの人たちが愛する以上に、わたしを愛するか」
あなたは私を誰よりも愛しているかどうか、ということですね。「この人たち」というのはほかの使徒のことです。彼らの前でそんなことを聞くイエスは何を考えていたのでしょうか。誰でも母親に愛されたいという思いがあるともいますが、兄弟のいる前で「弟たちより僕を愛しているか」とは聞かないでしょう。しかしペテロはためらいもせず答えた。
「主よ、そうです。わたしがあなたを愛することは、あなたがご存じです」
イエスはその答えに満足していたのか、彼にほかの使徒の指導を頼んだ。
「わたしの羊を飼いなさい」(ヨハネ21:15~17)
「愛するか」「ご存知のように」という奇妙な問答は三度も続くのです。三度も同じことを聞くので、ペテロは心を痛めたと福音書に書いてあります。ペテロはイエスが逮捕されたあと、師匠を三度も否定したからこそ、イエスはペテロの愛をやはり三度も確認しなければならないという説もありますが、私はそうではないと思います。イエスの言っている「愛」とペテロの言っている「愛」は別次元のものだと、私は思います。同じように「愛」と訳されている言葉の言語は「アガペー」と「フィリア」で、それぞれ違っているのです。イエスの一回目と二回目の問いでは、ペテロに「アガペー」があるかどうかを確かめようとしているのです。ところが、ペテロの答えは、「フィリアなら、あります」。
聖書の口語訳では、この温度差は全く表現されていません。日本には文語体の聖書訳もありますが、こちらも「愛」という訳語で統一されています。ところが、インターネット上での自由な利用を目的とした電網聖書では、問答はこう訳されています。
イエス「わたしを愛しているか」
ペテロ「わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」
そして三回目の問いかけにようやく、イエスはペテロの地平線まで降りていきます。
イエス「あなたはわたしに愛情を抱いているか」
ペテロ「主よ、知っておられます。わたしがあなたに愛情を抱いていることを、あなたは知っておられます」
ここで「愛情」として訳されている原語は「フィリア」ですが、それよりも「ストルゲー」が愛情の意味に近い。それはともかく、イエスのいう愛とペテロの言う愛のレベルの違いは「愛」と「愛着」という表現の温度差で実感できます。ペテロを始め、使徒たちはひょっとしてイエスにアガペーでもなく、フィリアでもなく、たんなる愛着で慕っていたかもしれません。
それもそのはず、イエスの愛のベクトルがどこ向いたかは、彼ら使徒には見えていなかったのではないでしょうか。あの中では一番優秀と噂されているユダは師匠を裏切り、魚の取れない漁師だったペテロは師匠のことを再三「知らない」という。それ以外の使徒もボンクラの仲良しグループと言ったら言葉はすぎるでしょうか。しかし使徒を悪者扱いするのもかわいそうな気がします。私が読んでいても、「福音書」からはイエスの愛の要求こそ伝わりますが、彼のビジョンがいまいち汲み取れないのです。
肝心のイエスは一体、どういうビジョンを持っていたのでしょうか。
イエスの生涯の中、学者が歴史的事実として疑わないイベントは二つしかありません。それイエスが三〇歳代で磔に伏せられたことと、それより二、三年前にヨハネという預言者から洗礼を受けたことです。その詳細は不明ですが、ヨハネは砂漠で数週間も断食をするといった苦行を実践しなが、「メシアの到来が近い」という切羽詰ったメッセージを発信していた宗教活動家だったようです。
「わたしは水でおまえたちにバプテスマを授けるが、わたしよりも力のあるかたが、おいでになる。わたしには、そのくつのひもを解く値うちもない。このかたは、聖霊と火とによっておまえたちにバプテスマをお授けになるであろう」(ルカ3:14・16)
「バプテスマ」とは言うまでもなく洗礼のこと。今もこのムーブメントは政治的権力のみならず、既得階級の祭司たちや律法学者とも対立していたはずです。イエスの周りにいた仲間には、律法の解釈に絶対的な自身をもつ彼こそメシアではないかという噂が広まったではないでしょうか。しかしヨハネから洗礼を受けた当初では、イエスは自分のことを救世主と思っていなかったはずです。そういう思いがあれば、ヨハネについて行く必要はなかったでしょう。
ところが、ヨハネはイエスを洗礼した直後、ヘロデの息子アンティパスの離婚と再婚を「姦淫」と呼んだため死刑にされます。紀元三〇年頃のことです。その後、イエスは独立をするのですが、十二の使徒もヨハネのムーブメントの影響を受けていたはずです。彼らの中には兵卒など、武装した者も少なからずいたようです。
イエスの使徒の中には「熱心党のシモン」という一人がいます。熱心党とはローマ帝国からの独立のために戦っていた、現代で言えば北アイルランドのIRAのようなテロリストだったのです。シモンの他にも、ユダはこのグループに属していたのではないかと言われています。
それなら、イエスが逮捕された時に祭司長の僕に剣で挑んだ者がいたのも納得できます。ほかでもなく、イエス自身は暴力をふるったことがあります。いわゆるエルサレム神殿事件です。そこでイエスが「なわでむちを造り、羊も牛もみな宮から追いだし、両替人の金を散らし、その台をひっくりかえし、はとを売る人々には『これらのものを持って、ここから出て行け。わたしの父の家を商売の家とするな』」(ヨハネ2:15~16)と叫んでいるのです。イエスも結局、憎しみの宗教を脱ぎ捨てきれなかったようです。他にも例があります。
「地上に平和をもたらすために、わたしがきたと思うな。平和ではなく、つるぎを投げ込むためにきたのである。わたしがきたのは、人をその父と、娘をその母と、嫁をそのしゅうとめと仲たがいさせるためである」(マタイ10:34~35)
「わたしは、火を地上に投じるためにきたのだ。火がすでに燃えていたならと、わたしはどんなに願っていることか」(ルカ12:49)
これはとても「だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてやりなさい」と宣伝していた口から出た言葉とは思えないですが、「福音書」の物語を信じれば、イエスは羊の皮をかぶった狼であったか、そてともきわめて情緒不安定だったことになります。どうやら、使徒の武装化を命じたのも、イエス本人でした。
「つるぎのない者は、自分の上着を売って、それを買うがよい」(ルカ22:36)
どう考えてもイエスを仏教徒と呼ぶには、いささか無理があります。私たちがイメージしがちな「優しいイエス」とその実物はだいぶ違っていたようです。彼はガンジーやマザーテレサではなく、ジョン・レノンのようなヒッピーの元祖でもなく、むしろチェ・ゲバラ的なカリスマではなかったでしょうか。
保守的な良民の目には、イエスを始め初期クリスチャンはローマ帝国に抵抗するゲリラに映ったのでしょう。若者たちの間では彼らにアップライジング(蜂起)を期待していた者も少なくなかったと思いますが、イエスはそのプロミスを果たせなかったし、使徒たちも当初は一貫したビジョンを持っていなかったと思います。
それぞれの使途がイエスの教えを自分なり受け取ったのは仕方のないことです。イエス本人の言動がかなり矛盾に満ちているわけですから、各地で活躍していた使途もさまざまな「イエスの教え」を語ったはずです。そこにペテロのイエスもいれば、ユダのイエスもいたでしょう。アンデレもマタイも、みんなそれぞれ「自分のイエス」を持っていた。
イエスの教えを人間を中心に語る使徒もいれば、神を中心に語る者もいたでしょう。「隣人を愛せよ」と、「世の終わりが近い」というのでは、メッセージが違います。
武力行使の是非から、女性の立場、性の問題など、ユダヤ教の従来の律法の位置づけについても、初期クリスチャンの間で議論されたはずです。
イエスの周りにいた人たちのうち、特に気になる人物がいます。それは『フィリポによる福音書』の中でイエスの「伴侶」として紹介されているマグダラのマリアです。
[主は]マ[リヤ]を[すべての]弟[子]たちよりも[愛して]いた。[そして彼(主)は]彼女の[口にしばしば]接吻した。他の[弟子たちは] 主が[マリ]ヤ[を愛しているのを見た。]彼らは主に言った。「あなたはなぜ、私たちすべてよりも[彼女を愛]されるのですか?」救い主は答えた。「なぜ、私は君たちを彼女のように愛せないのだろうか」(荒井献、大貫隆ら 『ナグ・ハマディ文書II 福音書』 岩波書店、1998年、ウィキペヂアより引用)
この一文で、イエスの人間的な葛藤を垣間見ることができるのではないでしょうか。彼のいう愛がはたしてアガペー、フィリアそれともエロスなのでしょうか。
『フィリポによる福音書』は一九四五年にエジプトのナグ・ハマディに発掘された一書。一九世紀の終わりには『マリアによる福音書』という文書も見つかっています。その中では、マグダラのマリアはほかの弟子と一緒になってイエスと問答をし、後半ではペテロはマリアに「「救い主が他の女性たちにまさってあなたを愛したことを、私たちは知っています」と呼びかけ、マリアがイエスの啓示を語ります。ところが、ペテロとアンデレはその内容を信用しようとしないから、マリアは泣いてしまいます。マタイは二人をたしなめ、使途たちが宣教に出発するところで話は終わってしまいます。
この文書は二世紀頃に著作された外典とされていますが、ハーバート大学の聖書学者ヘレン・キング教授はイエスが生きていた頃の文献である可能性もあると推測しています。どちらにせよ、初期キリスト教を語るときには「正典」と「外典」を区別するのはナンセンスです。なぜなら、「正」と「外」を区別したのが後ほど中央にいた人たちだからです。それぞれの福音書の中で、マグダラのマリアがイエスのもっとも親しい人の一人として十字架に立会い、そして復活したイエスを最初の目撃したのもマリアとされています。にもかかわらず、その後に著された使徒行伝の中には、マリアの「マ」の字も出てきません。
誰かの手によって、これら正典とされている福音書が書き換えられたことも十分に考えられます。そして「外典」のラベルを貼られたのは、マリアのようにアウトサイダーとされてしまった者でしょう。二〇一二年になって、ヘレン・キング教授はさらに衝撃な文書を紹介しました。その名は『イエスの妻の福音書』。その中ではなんと、イエスが結婚していたことが書かれています。バチカンはもちろん、この書をにせものとして否定していますが、一九八二年にすでにベルリン自由大学のエジプト学科で信憑性のある文献として言及されています。
ひょっとして、マグダラのマリアがイエスの妻? 古くから、二人の関係はいろいろと噂をされてきました。ポピュラーなものではミュージカル『ジーザス・クライスト・スーパースター』、マーティン・スコセッシ監督の映画『最後の誘惑』、そして最近では特にイエスとマリアの間に子どもまでいたとする『ダ・ヴィンチ・コード』が話題を呼びました。
ところが、中世の神学ではマグダラのマリアはイエスの妻どころか、実は娼婦だったという説が広く支持されていました。その根拠となったのは『ルカによる福音書』に出てくる「罪の女」の話です。イエスがあるパリサイ人の家で食事をしているを聞いて、その女性が泣きながら近づいて、涙でぬらしてしまったイエスの足を自分の髪の毛で拭いて、キスをしてから高い香油を塗ったそうです。パリサイ人はそれを見て、心の中で「もしこの人が預言者であるなら、自分にさわっている女がだれだか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから」と思ったそうです。イエスはそれを察していたのか、こう言いました。
「この女を見ないか。わたしがあなたの家にはいってきた時に、あなたは足を洗う水をくれなかった。ところが、この女は涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でふいてくれた。あなたはわたしに接吻をしてくれなかったが、彼女はわたしが家にはいった時から、わたしの足に接吻をしてやまなかった。あなたはわたしの頭に油を塗ってくれなかったが、彼女はわたしの足に香油を塗ってくれた。それであなたに言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪はゆるされているのである」(ルカ7:44~47)
「罪の女」とは娼婦の隠語らしい。ユダヤ・キリスト教の世界でもっとも罪深いとされているこの職業の女性をイエスは「多く愛したから、その多くの罪はゆるされている」と褒め称えているわけです。回心による赦しのメカニズムを説明するのに、パワーのあるエピソードです。その主人公である女性が実、あのマグダラのマリアだったとなると、なおさら想像力が働かされるのは確かです。しかし、マグダラのマリアと「罪の女」を同視したのは中央権力の独断でした。それはマグダラのマリアが象徴する反対勢力への弾圧だ、という声もあります。はて、マグダラのマリアはどんな「イエス」を自分の中で持っていたのだろうか。そして彼女の名を打ち消そうとしたのは誰か。腹の黒いユダか? 「岩」と言われながら、イエスを見捨てたペテロか? それともほかにも、自分の存在をアピールするため、マリアを排除したいと思っていた使徒がいたのでしょうか。
しかし十二使徒のどれをとっても、ぱっとしません。マリアが初期クリスチャンの中でどういうポジションを持ったかは現在では誰も知ることはできませんが、そのままでいけば、イエスの十字架の後で残されたほかの使徒は烏合の衆となり、ムーブメントが歴史に忘れられたと私は思います。
しかし、そうはなりませんでした。その理由を探すためには、初期クリスチャンたちの愛と憎しみのドラマにさらに深入りする必要がありますが、その前にはまず私自身の話に戻りたいと思います。
(2014年8月17日、ネルケ無方)