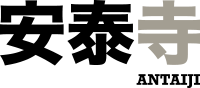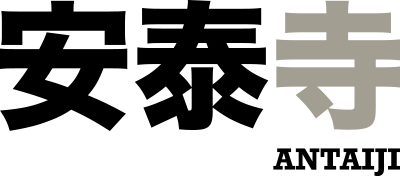キリスト教、仏教、そして私・序章
菩薩の夢
「あなたの夢は何ですか」キリスト教の国に生まれ、幼い頃に洗礼を受けました。その時に授けてもらった「クリスティアン(Christian)」というミドル・ネームは今も、私のパスポートに載っています。日本で使っている実印は「無方」です。そのどちらが本当の私といわれれば、どちらも本当の私です。自分の意思で日本に渡って、自分の意思で仏教で出家得度を受けました、依然と自分の中にキリスト教の影響が強く残っているのも、事実だと思います。
安泰寺という檀家のない、自給自足の禅寺の住職になってから、幾たびかメディアの取材を受けたことがあります。「山奥のドイツ人住職」というラベルを貼られ、ものめずらしい動物のような扱いをされることがほとんどです。それなのに、日本人が面している現実問題を解決すべき、私から何らかのヒントが導き出そうとする記者もいるようです。そういう記者が決まって知りたがるのは、私の「夢」です。正直言って、困った質問です。何しろ、仏教は人々に夢を提供する宗教ではなかったはずです。夢から目覚めることが仏教の眼目ですから。 有名な「いろは歌」は
浅(あさ)き夢(ゆめ)見(み)じ 酔(ゑ)ひもせず
という一節で終わりますが、夢を酔いとして否定的にとらえているところはいかにも仏教的です。
そもそも、「夢に向かって生きよう」という発想はどこから来たかといえば、近代の進歩主義ではないかと思います。西洋の科学文明もこの「夢の発想」をなくしては語れないと思います。そしてその背景にキリスト教の物語があるのは、いうまでもありません。夢の実現に向かっての努力は人類に物理的な豊かさを与えましたが、人類を含むこの惑星という生命体の存在そのものを危うくもしています。近代の「夢」は欲の膨張にすぎないということに、若い人々は気づきつつあるのではないでしょうか。このごろ、「宇宙飛行士になりたい」という子供が少なくなったといわれていますが、それは子供に夢が足りないからではなく、大人の提唱する「夢」の胡散臭さを見破いているからだと思います。
私もこれまで「夢ごとき、とっくにない」とつっぱってきました。しいて言えば、一人でもいいからしっかりした仏弟子を育てて、安泰寺の跡を継がせたいというのが夢のようなものですが、ダメならダメで、自分の代で安泰寺を滅ぼそうというあきらめに近い気持ちもどこかにあります。一ヶ寺を守るために、私は日本に渡ってきたわけではないし、安泰寺がつぶれたからといって、仏の教えが消えるわけではないので、お寺を死守しよういう気にはとうていなれません。それでも寺のために、仏教のために私にできることは全部するつもりですが、それを「夢」という言葉で表現することには違和感を感じています。現代っぽく言えば「夢なんて、うざい」です。
「夢」の人気が落ちていますから、マーケットが今度は「忘れかけたものを取りもどす」方向に動き始めているようです。近年の「仏教ブーム」もそれとは無関連ではないはずです。これからは「夢」よりも、「本当の生き方」なのでしょうか。私自身は最近よく「日本人より日本人らしい」「昔の日本のこころをこよなく愛している」「少欲知足を実践している外国人」などと紹介されることがありますが、これはその辺の政治家の表現を使うなら「きわめて遺憾」です。
安泰寺では今も薪割をして、カマドの火の上で自分たちで使った里芋や大根を料理をしています。まるで明治時代の初期のような暮らしですが、私は何も「古き良き日本に帰りたい」と思っていません。近代の浅き夢を追うつもりはないのですが、逆に古臭い文化財のような「仏教」にも興味がありません。
最近では、むしろ自分のルーツにあるキリスト教に再び感心がわきました。そこには、「神の国を自分の手で作ろう」という夢を感じているからです。かといって、子どものころから感じていたキリスト教への違和感も依然としてあります。ですから、今はむしろ「仏教的な夢」の可能性について検討するようになりました。安泰寺に来ていた当初はまだ、そんなものを考えもしませんでした。多くの参禅者がそうであるように、山に上っていた私は自分のことで精一杯でした。世界のことなんて、どうでもよかったのです。最近になってから、仏教が世界からの脱出ではないことにようやく気づきました。仏教と世界が無関係ではないばかりではなく、これからの人類が自然と共生し、あらゆる文化圏の人々が協和するために、仏教こそヒントを与えてくれるのではないかと、思うようになったのも最近のことです。そして、その時に安泰寺の修行生活が単なる浮世離れした「仙人ごっこ」ではなく、共生のモデルとなることが今の私の夢です。
このテキストは、そういう問題意識に基づいて書きました。仏教とキリスト教のそれぞれの世界観を比較しながら、これからの世界に向けての道しるべを見つけようという試みです。観念論で終わらせないためにも、仏教界やキリスト教界の問題ではなく、今の私の問題として考えて見たいと思います。
仏教には「末法」の教えがありますが、ABCの仏教すべてが採用しているわけではありません。また、仏教で言われている「末法」は世の終わりではありません。あるいは、この世から仏法が消えるかもしれません。しかしたとえそうなったとしても、いずれはまた誰かが生・老・病・死の苦しみに目覚め、苦しみからの解脱を求め、目覚めるであろうというのも仏教の教えです。実際に、一万年もすれば仏の教えが完全に消えてなくなりという教えは経典の中に書かれています。そしてその次にブッダとなるのは、弥勒菩薩と言う人です。今はまだ人間の世には現れないで、天上界で待機している「未来の仏」です。
過言すれば、仏教は消えてもいいわけです。いや、どっちみち消えるのです。いったん消えて、遠い未来にリサイクルされるだけです。
一神教は、そんな落ち着いたいません。旧約聖書の世界観を受け継ぐユダヤ教、キリスト教とイスラム教はいずれもハルマゲドン(世界最終戦争)の思想を持ち、「世の終わりが近い」と警鐘を鳴らしています。
その世の終わりは特に『新約聖書』のなかで、非常に具体的な言葉で語られています。
「すると、いなずまと、もろもろの声と、雷鳴とが起り、また激しい地震があった。それは人間が地上にあらわれて以来、かつてなかったようなもので、それほどに激しい地震であった。大いなる都は三つに裂かれ、諸国民の町々は倒れた。神は大いなるバビロンを思い起し、これに神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。島々はみな逃げ去り、山々は見えなくなった。また一タラントの重さほどの大きな雹(ひょう)が、天から人々の上に降ってきた。人々は、この雹の災害のゆえに神をのろった。その災害が、非常に大きかったからである。」
これは黙示録16章18-21の口語訳です。リアルな言葉の背景にあるのは、世界文明の発祥地とも言われる中近東のメソポタミア、バビロニア、ペルシアやエジプトのそれぞれの民族の興亡の歴史ではないでしょうか。紀元数千年前から、人と人が対立し、国と国が対立して権力争いを繰り返していたのです。『聖書』という書物は、隣国に虐げられていたイスラエル民族の自伝のようなものでもあるのです。
それは楽園からの追放からはじまりますが、その後も災難続きです。アダムとイブの間に生まれた長男カインは弟アベルを殺害し、神にはうそをついたため、さらに遠くへ追放されてしまいます。その後の旧約聖書はもっぱら飢饉、疫病の流行、終わりのない戦、天災、洪水や渇水、害虫の大発生といった災いの記録です。それらの多くはまるで現在の出来事のようです。人類が大洪水にのまされた記録もあれば、人間のおごりから計画されたバベルの塔の崩壊とそれに関連している人間同士のコミュニケーション・ギャップの話も出てきます。二〇〇〇数年前から、自然との共生、多文化の共生がいかに難しかったかが伺えます。出エジプト記やバビロン捕囚という強制移住と捕虜生活の生々しい記録もあれば、ソドムとゴモラの物語では二つの大都会は天からの硫黄と火の雨によって滅ぼされます。具体的な理由については諸説ありますが、どうやら住民の性の乱れが大きな原因であったようです。それが同性愛をはじめ、オーラルセックスやアナルセックスなど生殖に結びつかない性行為を指しているようですが、現在の欧米で「ソドミー」といえば主に動物との性行為という意味です。それはともかく、旧約聖書は近未来SFとして読んでも意外と面白いかもしれません。
ところが、イエスというユダヤ人が活動していた紀元前後には、アレキサンダ大王の征服の後でそれらの国々の多くはすでに影響力を落としてしまっていたのです。時代はすでにヘレニズムに変わり、そしてローマの時代に変わろうとしていました。ローマ帝国の鎮圧によって、やがてイスラエルの本当の悲劇が始まりました。二〇〇〇年も近い間、民族は離散生活を強いられ(ディアスポラ)、自国はありませんでした。やがてナチス・ドイツでホロコーストに遇いましたが、イスラエルは中近東で再興しました。しかし、その地方はいまだに安定することはなく、かつてのメソポタミアはいまやイラク、ペルシアにはイランがイスラエルとにらめっこをし続けています。
今のエジプトには、そのピラミッドしか栄えたころの華やかさを語るものはありません。そのエジプトを押さえたギリシャも、ギリシャを鎮圧したローマも、ヨーロッパ文明の発祥地と称しながら、いまやヨーロッパの足をひっぱっているとすらいわれています。南米のインカ文明を滅ぼし、一時期世界を征服しているように見えたスペインとポルトガルも、まったく同じです。その後、オランダやイギリスが幅を利かすようになりましたが、やがて「分家」のアメリカがいばり始め、世界はアメリカン・スタンダードで動くようになりました。しかしそのスタンダードも、今は危うい。
「いまにみてろよ、二一世紀のリーダーはニッポンだ」
日本人のその声も、今は聞こえなくなってしまいました。アメリカを超えそうになったのは日本ではなく、中国です。「アジアの時代」といえども中国、はたまたインドが注目されています。
日本で「末法」といえば終末論的なもの、「この世の終わり」と捉えることが多かったようです。人類が滅亡するかもしれない、と本気で信じていた人たちは昔の日本にもいたのでしょう。例えば、「方丈記」の著者として知られている鴨長明が生きていた時代はそうだったと想像します。しかし、戦乱や天災の時代にこそ現実感を持ちえた末法思想を、多くの日本人はその後の長い間、他人事のように思っていたのではないでしょうか。末法思想はおろそか、宗教そのものが日本人にとって無用の長物のように扱われてきました。なるほど、平和で豊かな時代ほど、宗教は景気が悪いのです。
ところが、どうでしょう。宗教を他人事と思える平和な時代はもう過ぎ去ってしまったかもしれません。3・11の大津波をテレビで見て、数日後に福島の原子力発電所の爆発を見たとき、私の脳裏にイエスのオリブ山での説法の言葉がうかびました。
「また、戦争と戦争のうわさとを聞くであろう。注意していなさい、あわててはいけない。それは起らねばならないが、まだ終りではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに、ききんが起り、また地震があるであろう。しかし、すべてこれらは産みの苦しみの初めである。
そのとき人々は、あなたがたを苦しみにあわせ、また殺すであろう。またあなたがたは、わたしの名のゆえにすべての民に憎まれるであろう。そのとき、多くの人がつまずき、また互に裏切り、憎み合うであろう。また多くのにせ預言者が起って、多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。
そしてこの御国の福音は、すべての民に対してあかしをするために、全世界に宣べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべき者が、聖なる場所に立つのを見たならば(読者よ、悟れ)、そのとき、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。屋上にいる者は、家からものを取り出そうとして下におりるな。畑にいる者は、上着を取りにあとへもどるな。その日には、身重の女と乳飲み子をもつ女とは、不幸である。あなたがたの逃げるのが、冬または安息日にならないように祈れ。その時には、世の初めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が起るからである。」
(マタイによる福音書、24:6~21)
今も世界のトップニュースを見れば、世界人口の増加、食糧不足、資源の欠乏、エネルギー問題。自然破壊、異常気象の発生。金融危機、貧富の格差、世代間の不信感。宗教戦争や人種差別……。
「聖書に書いてある通りではないか、人間がやっていることは」というシニカルな人もいれば、「最後の審判が近い、今こそが悔い改めの時」と声を大にする人もいます。あるいは自分自身を振りかえってみて、今一度、宗教的な生き方を問い直そうではないかという人もいるでしょう。そして、その問題意識を共有しているのは、なにもアブラハムの宗教といわれているユダヤ教、キリスト教とイスラム教ではないでしょう。
キリスト教の終末論の中心的な概念には「患難時代」「携挙(クリスチャンが空中で神と会うこと)」「(イエスの)再臨」「死者の復活」「千年王国」「最後の審判」「天国と地獄」「神の国」などがありますが、実はそれらの中身ははっきりせず、その前後関係も定かではないため、患難時代の前に携挙が興ると信じる人もいれば、その逆を言う人もいます。千年王国が終わった後にイエスが再臨するという主張と、再臨と同時に千年王国が始まるという主張が並立しています。また、最後の審判はミケランジェロの画で有名ですが、世の終わりに初めて人間が天国と地獄に振り分けられるのも変な話です。なぜならば、イエスは福音書の中で、自分を信じるものは死後すぐに天国にいけるといっています。つまり、キリスト教の教えでは、審判は二回行われることになっています。死後すぐの個人的な審判(それを専門用語で「私審判」といいます)と、「公審判」ともいわれる最後の審判です。それでも、三年目、七年目、一三年目、三三年目で繰り返される、日本で信じられている閻魔さんのよりはすんなりですが、どうして一回の審判で天国へいけないでしょうか。あるいは、一回目の審判で「天国ゆき」と認められたものでも、二回目の公審判で地獄へ落とされることもあるのでしょうか。
実は、これもキリスト教の歴史の中でいろいろと議論され、スカーッとした解決はありません。
これからは、私個人のポジションを述べたいと思います。決してキリスト教のいずれの教会の公式な立場ではありません。私の考えでは、「最後の審判」はすでに始まっています。今がまさに「千年王国」のときです。今ここにイエスを再臨させ、神の国を実現させるのは私たち人類なのです。天国も地獄も、私たち次第です。お坊さんがよく法話で使う話をご存知でしょうか。大きな食卓の上には、おいしそうなご馳走が盛ってあります。しかしその食卓を囲んでいる人々は、自分の腕よりも長い箸しか持ていません。その箸では、食事を口まで運ばれないのです。そこで互いにイライラし、やがて箸で殴りあいに展開してしまうのでは地獄です。「そうか、自分の口には運ばれないが、テーブルの向こうに坐っている人に進めることができる」と気づき、互いに食べさせて上げられば天国でしょう。
今ここの世界が天国であるか地獄であるか、それを決めるのが「最後の審判」だと私は思います。その判決が下されるのは、個人ではなく、人類そのものです。一人だけの天国もなければ、一人だけの地獄もありません。
「天国は、パン種のようなものである。女がそれを取って三斗の粉の中に混ぜると、全体がふくらんでくる」
(ルカによる福音書、13:33)
ここでいう「パン種」とは、天然酵母のことでしょう。酵母は混ざっていますが、パンの生地を膨らませなければならないのは、私たち人間です。仏教ではややもすれば、現世への感心が薄せれてしまう危険を私は感じています。仏教Aではそもそも、輪廻転生からの個人的な解脱が目的ですから、この世を仏国土にしようという発想は沸いてきにくいかもしれません。いっぽうの仏教Cでは極楽浄土を完全に死後のものと見なしてしまいます。禅の世界ではむしろこの世を涅槃と見なしますが、それはややもすれば怠慢な現実肯定でしかありません。仏教徒が今、キリスト教から見習わなければならないものの一つ、それはこの世を少しでも仏国土に近づけることだと思います。
そのために一つのキーワードとなるのが「菩提心」です(「道心」ともいいます)。菩提心を起こすきっかけとして、まさに「終わりが近い」という覚悟があるのです。しかし、それは何も人類の滅亡、世の終わりではありません。世が終わらなくても、私自身は数十年以内に、必ず死にます。あなたもそのはずです。それは明日、いや今日かもしれません。明日まで生きていたとしても、明日の私はもはや、今日の私ではありません。今日の私は、今日だけ生きています。今日が最初で、最後です。この自覚から菩提心が発し、この世を変えるなら今だ、私だ、という動機につながるはずです。
道元禅師は菩提心は「無常を観ずる」ことから始まるといっています。私を含むすべてのものには有限である、という気づきです。言葉を変えれば、それは「無我」の真実でもあるのです。私には実体がない、ということです。キリスト教の場合、終末論という形では世の無常こそとかれていますが、逆に各々個人の「無我」はあまりいわれていません。
12章で吟味する予定の『起世因本経』では、人類にはそもそも「所有」という概念がなく、「蓄える」という発想もなく、個人個人の対立もなかったのですから、盗みも浮気も、うそも殺し合いもなかったのです。人類暦学的に考えれば、サルが二本の足で歩き出したすぐのころの話でしょうか。あるいは縄文時代あたりまで、そんな感じだったかも知れませんん。
現代人の世界は対照的です。すべてにおいて、「私、わたし」が先走りして、世界は「自分のもの」とそうでないモノに分類されてしまっています。金銭や物は勿論、皆「所有者」がいるのです。配偶者も子供も、「自分のもの」になってしまいました。しかし一番身近な「自分の」夫や妻子でさえ、自分の領域を侵しかねないと警戒するようになっている人が増えているのではないでしょうか。現代人は時間や空間まで、「ワーク・タイム」と「ファミリータイム」とは別に、自分だけの「マイ・タイム」と「マイ・スペース」がなければ落ち着かなくなってしまいます。
現実ではどうでしょうか。「集団より個人、家庭よりもわたし」という根性は、「自由」「責任」「人権」などの理念を生み出した近代の個人主義の陰の部分です。その陰が問題視されて久しい。人間がエゴの芽生える以前の状態へのノスタルジアも、近代の風に吹かれてこそ強くなったのではないでしょうか。ルソーの「自然に帰れ!」という叫びではその典型です。ただ、「帰れ!」といわれても帰り道を知らないのが現代人です。
フランス革命の前夜から今日に到るまで、新しい社会論が次々と誕生し、革命と反革命も何度となく起こり、人類全体を巻き添えにして試行錯誤が続けられてきました。その過程の中の重大な論点の一つは経済学です。そしてそれと関連しているのが、やはり「所有」という概念。アナーキズムの父と言われるピエール・ジョゼフ・プルードンの主著『所有とは何か』の中で打ち出されている「所有は盗みである」というテーゼはあまりにも有名ですが、この言葉は実は約一〇〇年前に活動していた、同じフランス人の政治思想家ジャック・ピエール・ブリッソーの書物の中ですでに表れています。不必要なものを使用せずに蓄えることは、それを必要としている人たちからの盗難である、という主張です。盗みは所有の裏返しに過ぎないと、二〇〇〇年以上前に分析した初期仏教と驚くほどよく似ている発想です。
アナーキズムとは違う立場で、マルクスも似たような結論に達します。方法論こそ違いますが、マルクスが夢見た共産主義社会では「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」という基準が実現するはずだったのです。それは「働かざるものは食うべからず」という言葉と対照的な、高い理念ですが、八十年間続いていたソ連をはじめとした東欧諸国の社会主義というハードな「社会実験」でついに実現できなかったのです。
しかし、人類はもっと公平な、もっと幸福な社会制度の夢をいまだに捨ててはいません。いろいろな提案がある中、最近世界中で注目を集めている「ベーシック・インカム(基本所得)」は比較的にソフトなアプローチといえるのではないでしょうか。すべての国民に生きるために必要な、最低限の額を無条件に支給するというアイデアは約二〇〇年の歴史を持っていますが、最近ドイツでは革新的な「海賊党」から保守的な「キリスト教民主党」まで、支持者は増えています。生活保護・失業保険・年金・子供手当てを全て一本化したようなものです。当然の問題として、「そのお金はどこから」というのが挙げられます。ある提案者は「消費税相続税100%」といい、別の人は「相続税100%」といい、あるいは「所得税をあげればいい」「政府紙幣を発行すればいい」と、さまざまな案があるようです。
ただでお金がもらえるならば、そもそも仕事をする人はいるのだろうか、という疑問を持つ人も多いでしょう。しかし、「いる!」という人もいます。人間にとって、何もしないことが一番苦痛なのです。子供を見ても、ジーとしていられないのは普通です。大人もそうです。坐禅をすれば、実感できるものです。そして、必要とされたいというのも人間です。ですから、働かなくても食えるという社会の中でも、「働きたい!」という気持ちが当然生じてくるはずです。食うために働くのではありません。働くことによって、人に生かされていること・人を生かせていることを実感できるから、働くこと自体・仕事自体が報酬となりえるのです。働くのではなく、働かせていただくのです。少なくとも、理屈の上では・・・。
「現代の経済学者は労働や仕事を必要悪ぐらいにしか考えない教育を受けている。雇い主の観念からすれば、労働はしょせん一つのコストにすぎず、これは、たとえばオートメーションを採り入れて、理想的にはゼロにしたいところである。労働者の観点からいえば、労働は「非効用」である。働くということは、余暇と楽しみを犠牲にすることであり、この犠牲を償うのが賃金ということになる。したがって、雇い主からすれば、理想は雇い人なしで生産することであるし、雇い人の立場からいえば、働かないで所得を得ることである。」
ところが、彼がビルまで目にしたのは「仏教経済学」はまるで違っていました。そのキーワードは八正道の「正命」すなわち正しい働きによって営まれる生活です。その観点から、欧米では負の意味しかない仕事の三種類の意義が見えてくるとシューマッハがいいます。まず、働くことによって人間は自分に内在する能力を発達させ、表現することができます。それから人々と共同に、一つの目的に向かって働くことによって、自分のエゴを捨てることができます。そして最後には、社会生活をするために必要な物資を生産しおよおびサービスを提供することができます。ですから、仏教経済学の観点から見た場合、オートメーションによって労働量を減らすことは必ずしもいいことではないのです。肝心な「人間」を不必要なものにしてしまうからです。現代の経済学はもっぱら生産を問題にし、人間と自然環境を見失っているのがシューマッハの主張。政治家も消費を促しながら、そもそも何のために消費するのかを考えていません。足ることを知らなくなった現代人は幸福を追求しているつもりで、実は経済成長という回し車の中で走り続けているネズミでしかないのです。
私が考えている日本仏教の新しい形を英語では「エンゲージド・ブッディズム」といいます。日本語訳として「社会参画仏教」が一般化したようですが、中国では「入世仏教」といいます。最初に提案のは中国で仏教を改革した太虚(一八九〇~一九四七)やその弟子である印順(一九〇六~二〇〇五)だそうですが、それを広く世界に知らしめたのは「台湾のマザーテレサ」と呼ばれる釈証厳や欧米でダライラマに次ぐもっとも有名な仏教僧であるティク・ナット・ハン(釈一行)。出世間だけを狙ったのでは、仏教には将来がないと彼らは悟りました。いまや、欧米の仏教のほとんどがその影響を受け、瞑想や経典の研究だけではなく、仏教に根ざしたボランティア活動もさかんに行われています。私が安泰寺でやっている活動もその一環となれば、と願っています。
私は今から約二十年前に、曹洞宗と臨済宗とそれぞれの二つの認可僧堂で修行したことがあります(詳しいことは、『迷える者の禅修行』をご参照ください)。どちらにも一年間ほど安居【ルビ あんご】しましたが、お葬式に参列したことは一度もありませんでした。お盆の棚行にも、檀家の月参りにも参加していません。それは、私が特別に生意気だったという理由からではなく、単に「外国人」だからでした。僧堂に言い分としては「私たちは何もあなたがたを差別しているつもりはない。ただ、檀家さんの気持ちを考えると、青い目の雲水を法事に生かすもちょっと…。『雇われ外国人』ではあるまいし、あなたがただって葬式のノーハウを学びに来たではないだろう。仏教を修行をしに来たはずだ」
なるほど、僧堂でも「葬式法要は仏教ではない」とちゃんとわきまえた上でやっているわけです。お葬式はいわばアルバイトであって、仏教の修行は別にあるのです。残念ながら、アルバイトであったはずのものがいつの間にか本業になってしまい、「修行をしている暇はない」ということになってしまいました。僧堂でも、お葬式が重ねれば禅堂の中で坐禅をしているのは外国人だけになってしまいます。ですから、日本人の修行僧がいざ父親のお寺に帰れば坐禅を続けるはずも有ありません。
「坐禅なんて、外人のためにあるのでは?」
ということになってしまうのです。
若さにある僧堂では、私のほかにはカナダ人・アメリカ人とドイツ人という三人の「二十年選手」がいました。彼らは修行暦こそ日本人のだれよりも長かったのですが、日本人の修行僧が卒塔婆【ルビ そとば】の書き方を学習していた時間には、私を含め彼ら外国人は台所で料理をしたり、老師の犬を散歩させたりしていました。
「犬を散歩させるくらいなら、葬式法要のノーハウを教えてもいいのではないか」
とそのとき思いましたが、前述したように教えるほどのことは何もないということを後で分かりました。ただ、犬の散歩が修行なのに、葬式法要だけは(外国人には)修行にならないというのもどうでしょうか。
それはともかく、私のように仏教を学びに日本に来ている外国人たちがあまり葬式法要に関心を持たないというのも事実です。だからこそ、安泰寺のような檀家ゼロの自給自足の修行道場にも来るのです。彼らが本国に帰ってからどうしているのだろうか、と不思議に思う人もいるでしょう。
私は、実はそんなことを一度も考えたことがありません。安泰寺で修行をして、ドイツで坐禅道場でも作ってみようという思いはありましたが、そのためにの資金くくりとか、生活をどうするかは考えていませんでした。
「坐禅をしていれば、生活は何とかなるさ」
というようなのんきな態度でした。そして、安泰寺を出て大阪城公園で「ホームレス雲水」をやっていたときも、まさにそんな生活でした。ドイツでも同じことをやればいいではないか……そう思っていたものです。あるいは、たまたま安泰寺の後を継ぐことになっていなければ、今ころドイツのどこかで橋の下でも坐禅していたかもしれません。
ですから、安泰寺で修行したほかの外国人が本国に帰って、はたして生活できるのだろうかという心配も、私はしていません。最後には私の弟子になって、今は国に帰っている弟子たちの活躍についてすこしご説明したいと思います。
多くの人は、国に帰ってから以前の職業に戻って生活しています。安泰寺でたとえ出家得度を受けたとしても、普通の格好で在家生活を営んでいます。ただし、坐禅だけはつづけているのです。自分で坐禅道場を開いた人も少なくありません。「道場」といっても、自分が住んでいるアパートのリビングだったり、裏庭にある「ガーデン・ハウス」だったりします。そこで毎週数回、同士と集まって坐禅をするわけです。そこに畳を敷いて、小さな仏像をおいて、日本風の禅堂の雰囲気を作っているのもいれば、洋風の部屋を片付けて、一輪の花だけを飾る人もいます。形には特にこだわっていません。 “Antaiji Sangha” のそういう小さなグループはドイツ・オランダ・フランスやポーランドなど、あちらこちらにあります。
また、禅と職業を結びつけて、「ライフ・コーチ」をやっている二人の弟子はカナダとスウェーデンにいます。ユダヤ系のエリーは得度名(いわゆる「戒名」)として「龍尾」を選んでいました。どうやら、ユダヤ教のことわざには「頭が龍でも、尻尾は蛇」というのがあって、自分はその反対を目指すといっていました。もう一人のソリヴァンはもともとドイツ系です。エリーと同じく、二十歳台の半ばで安泰寺で得度をしました。彼の新しい名前の当初の予定は「水月」でしたが、「すい」より「ずい」が発音しやすいということで「瑞月」になりました。二人はようするに、それぞれの国で人生相談を専門的にやっているのです。禅の立場から答を与えるのではなく、自分の生きかたを同じ地平線で問うってみようというアプローチだと思います。
ドイツ人のトーマスは私より何歳か年上ですが、今から十年前に出家得度をし「真龍」になりました。禅の世界でかなりポピュラーこの名前には由来があります。昔の中国には、竜の画が描かれている掛け軸を集めるのが大好きな人がいたそうです。その話を本物の竜の耳に入りました。
「そんなに竜のことが好きのなら、本物を見せて喜ばしてやろう」
ということで、その人の家の窓から首を突っ込んで見ました。ところが、その人が竜のせっかくのサービスを喜んだどころか、びっくり仰天して死にそうになったそうです。仏教のことをあれこれ本で学んだらい、美術品を見て感心するのではなく、自分が実践して「そのもの」にならなければダメだ、という意味合いで禅ではこのたとえ話が使われています。
その真龍は今ドイツで、坐禅の道場を開きながら心理学者として小さなクリニックを開いています。
やはりドイツ人のマルクスが「大心」として私の弟子になったのは今から八年前。料理が得意だったので、道元禅師の『典座教訓』という書物からつけました。道元禅師は僧堂で料理をする人の心構えとして「山のような大きな、海のような広い心」と説明していますが、大心はまさにそういう人でした。安泰寺で修行をしている間は付き合っていた彼女をドイツに残していました、今は旧被害ドイツの北部で二人で “Tenzo Gasthof” (「典座料理亭」)というホテルを営んでいます。安泰寺での経験を生かして、自分たちの庭で育てた無農薬の野菜を中心に精進料理にこだわらず世界じゅうの台所からヒントを得た料理を出しています。たまにはホテルでコンサートをやったり、シーズン・オフには坐禅会もやっていますが、彼はむしろ料理を禅の表現だと考えています。 今は、弟子たちの下でさらに弟子が育ちつつあります。二年前には、オーストラリアのメルボルンで禅・センターをやっている「聖観」(彼の名前の由来は、恐れ多く観音さん……ダライ・ラマに起られそうです)のところに行って、センターのメンバーの在家得度式をやりました。ようするに、正式に出家するのではなく、在家のままで仏道に生きていこうという意思表明です。このときにはお袈裟と衣ではなく、略式のお袈裟である絡子(らくす)と生きる方針としての戒律のみを授けます。ご存知のように、日本では戒律をかなりルーズに解釈しますがオーストラリアではメンバーのほとんど全員がベジタリアンであったことにびっくりしました。せっかくオーストラリアまで来たのだから、カンガルーのステーキくらい食べさせてもらえるのだろうと思いましたが、それもナシでした。いや、それは冗談で、ほかでもなくこの私は長年ベジタリアンにこだわっていたので、むしろ好感をもてます。
在家得度式の会場となったのは、なんとフットスクレイ・チャーチというメルバーンの教会でした。日本人は仏教徒でありながらチャペルで結婚しますが、オーストラリア人は今や教会の中で仏教の菩薩戒を受けています。私がいったときにはフットスクレイ・チャーチの中で一日の接心もやりましたが、「ストリート・セッシン」といって路上で坐禅をすることもあるそうです。屋根のない、壁もない、世間に完全に開かれた場所でただ坐る。私もかつて大阪城公園でやっていましたが、日本ではほかにはあまり聞かない接心です。
センターをやっている聖観はかなりユニークな人です。彼はチェコ生まれですが、プラハの春をきっかけに親は西ドイツに逃げたので、ドイツ語もネイティブなみに話せています。大学ではもともとは建築学を専攻したそうですが、卒業後に東洋医学の大学院に入りなおし、安泰寺に来たときはすでに博士号を二つも持っていました。今はメルボルンで精神カウンセラーの仕事をやっていますが、禅・センターと平行して「禅・ホスピス」のプロジェクトにも没頭しているようです。そのホスピスには現時点では建物はないので、末期がんの患者などを病院または在宅で心のケアしています。言うまでもなく、無報酬のいわゆる菩薩行です。仕事はほかにあり、コストもほとんどかからないので、こういう活動が可能なのです。ホスピスの活動を彼にわせれば、人のために何かをする、何らかのサービスを提供するのではないそうです。
「ただ、同じ船に乗ることだけ」
もちろん、彼がいっしょに死ぬわけではありませんが、それまでは言葉を交わし、時間を共有し、その場にいっしょにいるのです。相手のためではなく、自分の修行にこそなっていると彼は言っています。ゆくゆくは、センターとホスピスが共存し、同じ建物の中で仏道に励もうとする人と死んでいく人が共生できる施設をつくりたちというのが彼の夢です。医療施設として認可してもらうためには何十万ドルもかかるので、医療施設ではなく同士が一緒に生活する「シェアハウス」として運営することを考えているとか。
東京にも、以前安泰寺で在家得度をした弟子「俊彦」がいます。いや、この場合は深い意味がまったくなく、親からもらった本名が「としひこ」から「しゅんげん」に変わっただけです。その彼も介護施設を立ち上げようとして、精神科のクリニックで実習をしたり、精神障害者のグループホームで働いたりします。
「坐禅が私を助けてくれている。自分をゼロにし、全ての物事を自分をいれずに考えるためには坐禅が必要だ」
と彼は言っています。助けるのは「自分」、助かるのは「相手」という壁を打ち破っていくのが大事です。ゆくゆく施設を立ち上げるかどうかは別として、一方的に介護をするのではなく、いっしょに生活することはポイントになるでしょう。
「ビハーラ」と称して、日本でも同じ活動をしているお坊さんがいますが、聞いた話では必ずしも周辺の理解を簡単に得られるわけではないようです。
「病院に行ったら、こういわれた。『死んでもいないの、どうして坊主が?縁起でもない!』。まだ死んでいないうちに話を聞きに行きたいのにね」 オーストラリアの聖観は見取った相手のメモリアル・サービスをすることもあります。しかし、外国の禅・センターではお葬式より仏前結婚式をよく目にします。メンバーは若い人が多いので、センターで知り合ったもの同士で「いっしょに仏道を歩んでいこう」と誓うわけです。いくらウェッディング・ドレスがかわいいからといって、日本人のように信じてもいない神に誓おうとは思わないわけです。そもそも、仏前結婚式だからといって、ウェッディング・ドレスが着れないと言う決まりがありません。
私がメルボルンにいたとき、聖観に “Lentil as anything” というレストランに連れてもらいました。“Lentil” はレンズ豆のことで、もちろんベジタリアン・レストランです。このレストランは、ペイ・アズ・ユー・キャン( “pay as you can” )という珍しい経営方針をとっています。珍しいというより、よくもそれで商売がなりたつのだという人もいるでしょう。なにしろ、いくら飲んでもいくら食べても「ただ」なのです。
厳密うに言えば、材料費も人件費もかかっていますから、提供する側として「ただ」というわけがありません。しかし、毎日変わるおいしいバフェーの料理には値段がありません。レストランにはレジもありません。カウンターの上に、一個のマジック・ボックスがおいてあるだけです。
「あなたが今日、ここで食事ができるのはこの不思議な箱のおかげだ」
という一枚の紙が張っているだけです。ようするに、お寺で言えば賽銭箱です。昨日入ったお金で、今日の料理が賄われている。今日入ったお金で、明日の料理が賄われるであろう……、そういう哲学です。二〇〇〇年にこのレストランを設立させたのは私と同じ年、スリランカ生まれのシャナカ・フェルナンドです。もともと法律の勉強のためにオーストラリアに来ていたはその当時、川原のテントの中で過ごしていたそうです。
「お金があってもなくても、同じ食卓でたべよう」
という彼のアイデアは成功し、今はレストランがチェーンになっています。今はオーストラリアの郵便局我が彼の記念切手も発行し、マジック・ボックス第一号は首都キャンベラにある「ミュジアム・オフ・デモクラッシー」で呈示されています。思わんところで、思わん形で「お布施」の精神が実を結んでいます。仏教国であったはずの日本の「仏壇」も、ぼさぼさとしてはいられません。