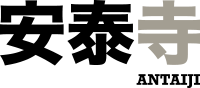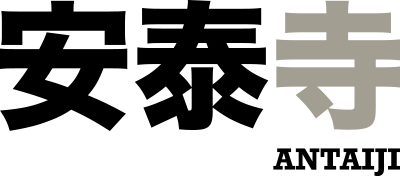キリスト教、仏教、そして私・その30
愛の〝コペルニクス的〟回転
キキリスト教と仏教はいかにして「作成」されたかキリスト教はイエス・キリストを中心に作られましたが、イエス自身が作ったわけではないのです。イエスはキリストであっても、クリスチャンではなかったからです。釈尊と仏教のケースを考えた場合も、それは同じです。釈尊はブッダになりましたが、ブッディストになろうとは夢に思っていなかったはずです。イエスに時代にキリスト教がなかったように、釈尊に時代には仏教がなかったのです。
釈尊が八〇歳で亡くなったあと、その教えは四〇〇年ものあいだ伝言ゲームのごとく伝播され、グループ(部派)に別れていた仏弟子がそれぞれ勝手な解釈をするようになりました。そこでブッダの教えがあまりにもバラバラにならないため、結集【けつじゅう】と言われる宗教会議が行われました。伝承によれば、一回目の結宗は釈尊の滅後すぐ、二回目は一〇〇年後に行われました。そのつど弟子たちは教義について議論し、教えの内容を確認したはずですが、紀元前二五〇年頃に行われたとされる第三結集について、それぞれのグループの記録はすでに異なっております。その時議論されたトピックの一つは、「阿羅漢と言われる完成された修行者が夢精するかどうか」。こんな微細な問題を仏弟子たちが大真面目にディスカッションをし、それぞれのグループは自分のポジションを譲ることがありませんでした。
時代は紀元前三世紀頃、まだキリストがこの世に生を享ける前の話。世界史の教科書に必ず登場するヘレニズム文化が隆盛の頃です。地中海からはるか西のインドまで勢力を伸ばしていたヘレニズム世界は、インドとすでに盛んに交流をしていました。その頃のインドはアショーカ王によってほぼ統一されていて、王は残虐な戦争を反省し、仏教に傾倒、仏教を守護したと言われています。そして王は、インド国内やスリランカにとどまらず、遠くシリアやエジプト、ギリシアにまで仏教の宣教団を送ったそうです。
初期のキリスト教以上に偶像作成に否定的だった仏教も、アレクサンダー大王がその勢力を北インドまで伸ばしてから、急に仏像が多く彫られるようになりました。ギリシア・ヘレニズム文化では、偶像崇拝はタブーではなく、神々を模した多くの彫像が作られています。「自己をよりどころとせよ」という仏教の考え方からして、初期仏教では仏像を彫りそれを拝む風習はありませんでした。仏教とギリシア文明の出会いがなければ、私たちにも馴染みの深い仏像を拝むことができなかったかもしれません。
また、仏教には『弥蘭陀王問経』というお経がありますが、その主人公はギリシア人のメナンドロス一世です。メナンドロス一世は西北インドにあるヘレニズム系王朝の国王で、彼が紀元前二世紀頃、ナーガセーナという仏教僧と交わした問答がこのお経の内容となっています。
そして釈尊の教えがようやく文字で書き留められたのは、紀元前一世紀のスリランカで行われた第四結集の時でした。しかしこの会議に参加したのは、テーラワーダの比丘(修行僧)のみで、大乗仏教では紀元後二世紀頃に北インドのクシャーナ朝で行われたとされる会議を「第四結集」と呼んでいます。大乗仏教の場合は、これらの結集で編集された経典の他にも新しい経典制作が精力的に行われました。空の思想を説く般若経典も、永遠のブッダの物語であり法華経も紀元前後に制作されたとされています。
以前にもパーリ経典『起世因本経』と聖書の『創世記』の類似について触れましたが、この場合は相互影響というよりも、互いに共通したテキストを下敷きに、それぞれそれを発展させたものであると考えられます。それより時代はくだって、新約聖書の「放蕩息子」と大乗仏教の『法華経』の類似も指摘されますが、こちらの場合は、互いに直接影響を与えた可能性もあります。日本の浄土宗と浄土真宗に多大な影響を及ぼした浄土三部経の成立は一世紀から二世紀ころまでとされています。こちらはシルクローダあたりで一神教の影響を受けて制作されたとする学説もあります。 第一回目の教会会議
かように仏教とキリスト教の相互影響はいろいろと噂されているようですが、イエス自身の口からは、ユダヤ教を否定するものが一言も出てきません。彼からインドの匂いがあまりしないどころか、イエスの教えを全てユダヤ教に還元できるとすら思います。イエスはユダヤ教の原理主義者だったといっても過言ではないでしょう。彼はまさか、いつか新たな世界宗教の教祖に祭り上げられるとは思わなかったでしょう。
イエスの一二人の使徒を見ても、その中には新しい教団を立ち上げるほどの力量を持った人はいなかったと私は思います。
一番優秀と言われていたユダは師匠を裏切りましたし、それ以外の一一人はイエスを頼りに集まっていただけの烏合の衆。ボンクラの仲良しグループと言ったら、言葉はすぎるでしょうか。イエスの十字架のあと、彼らは世界中に散らばり宣教しようとしたようですが、この連中にどうやってキリスト教を世界に広めよというのですか。
そこで初期クリスチャンを少しでもまとめやすくするために、、「教会会議」が行われっました。キリスト教宣教師の先駆者が、エルサレムで最初に会議したのは紀元五十年より早い時点だとされています。その頃には、新約聖書で大事な「福音書」すら、まだ書かれていません(諸説ありますが、一番成立が早いとされているマルコによる福音でも紀元七十年前後、マタイとルカが八十~九十年、イオハネは百年頃と言われています)。
この最初の会議の狙いは、ユダヤ教クリスチャンと異邦人のクリスチャンの溝を埋めることでした。「ユダヤ教クリスチャン」とは聞きなれない言葉ですが、その当時のクリスチャンたちはまだユダヤ教の一派だと思われていたのです。なにしろイエス自身が生涯、ユダヤ教徒だったのですから。当時のキリスト教徒たちは自分たちのことを「ユダヤ教と違う」とは思っていなかったはずです。他のユダヤ教徒からは、過激な「ユダヤ教の新興宗教」に思われていたのでしょうが、彼らは「イエスこそユダヤ教のメシア(救世主)、我々はユダヤの救世軍」という自意識を持っていたと想像します。彼らのアジテーション(宣教)も、最初はもっぱらユダヤ教徒を相手に行われていたはずです。なぜなら、イエス自身はイスラエル以外の地で宣教を望んでいなかったからです。
「異邦人の道に行くな。またサマリヤ人の町にはいるな。むしろ、イスラエルの家の失われた羊のところに行け。行って、『天国が近づいた』と宣べ伝えよ」(マタイ10:5~8)
イエスは福音を異邦人に説くことを「子供たちのパンを取って小犬に投げてやるのは、よろしくない」なんて、ひどいことを言いました。しかしどういうわけか、弟子たちは師匠の言葉に背いて、やがて世界中に教えを広めました。トマスはインド、シモンとタダイはバビロニアやペルシアで活躍しました。西の方でヤコブはスペインで宣教したと伝えられています。北へ向かったヨハネは現在のトルコ西岸にあるエフェソスに、フィリポは黒海を渡り現在のウクライナに、そしてバルトロマイはアルメニアに拠点を置いた。マルコはエジプトのアレクサンドリア、マタイはエチオピアまで足を運んだそうです。ペテロの弟だったアンデレはコンスタンティノポリス、ペテロ自身はローマへ赴きました。命がけの宣教で、殉死を遂げた者も少なくありませんでした。
彼らはユダヤ教徒ではなく、イスラエルから見れば「異邦人」を相手に宣教していたわけです。そこで一番問題になったのが「クリスチャンの条件」についての議論でした。
クリスチャンになるために、クリスチャンとして認められるためには、どのような条件を充たせばよいのか――。
ユダヤ教には昔から、「割礼」といって男の子の陰茎包皮を切除するという習慣がありました。今ではユダヤ教やイスラム教圏を越えて、衛生上の理由からアフリカやアメリカでも広く行われているようですが、当時の「異邦人」にはその習慣がありません。そこで当然、「異邦人にも割礼を施し、またモーセの律法を守らせるべきだ」と主張する保守的なユダヤ教徒が現れました。その時のことは聖書の「使徒行伝」に詳しく書いてあります。そこで発言するのはかつてのイエスの一番弟子、ペテロです。
激しい争論があった後、ペテロが立って言った、「兄弟たちよ、ご承知のとおり、異邦人がわたしの口から福音の言葉を聞いて信じるようにと、神は初めのころに、諸君の中からわたしをお選びになったのである。そして、人の心をご存じである神は、聖霊をわれわれに賜わったと同様に彼らにも賜わって、彼らに対してあかしをなし、また、その信仰によって彼らの心をきよめ、われわれと彼らとの間に、なんの分けへだてもなさらなかった。しかるに、諸君はなぜ、今われわれの先祖もわれわれ自身も、負いきれなかったくびきをあの弟子たちの首にかけて、神を試みるのか。確かに、主イエスのめぐみによって、われわれは救われるのだと信じるが、彼らとても同様である。(使徒行伝、15:7~11)
つまり、「ユダヤ人であれ異邦人であれ、神を信じるものは神の恵みよってのみ救われる。それ以外の条件は何もない」とペテロが主張していたのです。しかしこのペテロも、教団をまとめるほリーダーシップのあった人物とはとうてい思えません。なぜなら、ガラテヤ人への手紙によれば、ペテロはイソップ寓話に出てくる卑怯なコウモリにも負けないくらいの日和見主義者だったようです。
「ケパがアンテオケにきたとき、彼に非難すべきことがあったので、わたしは面とむかって彼をなじった。というのは、ヤコブのもとからある人々が来るまでは、彼は異邦人と食を共にしていたのに、彼らがきてからは、割礼の者どもを恐れ、しだいに身を引いて離れて行ったからである」(2:11~12)
あれだけ異邦人の平等を解いていたケパことペテロが、ユダヤ人の見ている前では彼らと一緒に食事をしなくなったというのです。そこで手紙の著者であるパウロという人物が、イエスの一番弟子に腹を立てのです。
「…まっすぐに歩いていないのを見て、わたしは衆人の面前でケパに言った、「あなたは、ユダヤ人であるのに、自分自身はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活していながら、どうして異邦人にユダヤ人のようになることをしいるのか」。
人の義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただキリスト・イエスを信じる信仰によることを認めて、わたしたちもキリスト・イエスを信じたのである。それは、律法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら、律法の行いによっては、だれひとり義とされることがないからである」(2:14・16)
さて、ペテロに物言いをしたパウロとは一体何ものだったのでしょうか。。
迫害者からリーダーへキリスト教を世界宗教として成功させたのは、そのパウロという一人の使徒の功績だと私は考えています。そう、パウロこそキリスト教を作り上げた天才的な宗教家なのです。それを聞いて、「え?」と思われる方もおられるでしょう。ご説明しましょう。
パウロはほかの使徒と違い、実は一度もイエスのお目にかかったことがありませんでした。それどころか、パウロはもともとサウロと名乗り、初期クリスチャンの迫害に関わっていたと『コリント人への第一の手紙』の中で告白しています。
「実際わたしは、神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中でいちばん小さい者であって、使徒と呼ばれる値うちのない者である」(15:9)
それではどうして、迫害者であったサウロが使徒パウロへ転身したのか。そのいきさつをパウリ自身が晩年、当時のイスラエルの支配者であったアグリッパ王に語ります。大事なエピソードなので、やや長く引用します。
「わたし自身も、以前には、ナザレ人イエスの名に逆らって反対の行動をすべきだと、思っていました。そしてわたしは、それをエルサレムで敢行し、祭司長たちから権限を与えられて、多くの聖徒たちを獄に閉じ込め、彼らが殺される時には、それに賛成の意を表しました。それから、いたるところの会堂で、しばしば彼らを罰して、無理やりに神をけがす言葉を言わせようとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまで、迫害の手をのばすに至りました。
こうして、わたしは、祭司長たちから権限と委任とを受けて、ダマスコに行ったのですが、王よ、その途中、真昼に、光が天からさして来るのを見ました。それは、太陽よりも、もっと光り輝いて、わたしと同行者たちとをめぐり照しました。わたしたちはみな地に倒れましたが、その時ヘブル語でわたしにこう呼びかける声を聞きました、『サウロ、サウロ、なぜわたしを迫害するのか。とげのあるむちをければ、傷を負うだけである』。
そこで、わたしが『主よ、あなたはどなたですか』と尋ねると、主は言われた、『わたしは、あなたが迫害しているイエスである。さあ、起きあがって、自分の足で立ちなさい。…【中略】…わたしは、この国民と異邦人との中から、あなたを救い出し、あらためてあなたを彼らにつかわすが、それは、彼らの目を開き、彼らをやみから光へ、悪魔の支配から神のみもとへ帰らせる…【中略】…ためである』」(使徒行伝26:9~18)
クリスチャンをあれだけ苦しめていたサウロの目からうろこが落ちたのはその時でした。現代の日本人も度々使うこの表現の元ネタは、実は聖書にあったのです。回心してから、彼がパウロとしてやがて初期クリスチャンを実質的にリードをする形になったのですが、パウロの主張はイエスの教えと正反対だった部分もあります。
例えば、イエスは山上の垂訓のなかで「わたしは律法を廃止するためではなく、完成させるために来た」と言い、また「あなたがたの義が律法学者やパリサイ人の義にまさっていなければ、決して天国に、はいることはできない」と主張するまで、律法を守ることを大切だと考えていたようです。
一方でパウロは律法を不要と考えていたようです。
「律法によっては、罪の自覚が生じるのみである…【中略】…人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるのである」(ローマ人への手紙3:20・28)
この言葉がターニングポイントとなって、キリスト教の爆発的な普及が始まったと私は考えています。
イエスは「人の子」と自称していましたが、だからこそ同じ人の子である弟子たちへの期待も高かったはずです。しかし、「自分の十字架をとってわたしに従ってこない者はわたしにふさわしくない」という言葉で現れているように、そのハードルはあまりにも高すぎていたのではないでしょうか。その人間イエスに弟子たちがついていけなかったのは無理もありません。パウロの目からウロコが落ちたということは、「イエスは神を説く人間ではなく、神そのものだった」というひらめきではなかったでしょうか。このひらめきがなければ、今日のキリスト教はなかったはずです。
ここで今一度、イエスとパウロの宗教観の違いをはっきりさせましょう。そのためには三つの問題領域に注目したいと思います。その三つというのは、イエスの人間性と神性、原罪と義認の関係、そして神の国の実現です。ここでは「義認」について説明しましょう。
その意味は読んで字のごとく「義と認める」ことですが、神が「義」すなわち「よい」と認めた者だけが天国にいけるのです。いかにして「義」とされ、神に認められるかがキリスト教において重要なのです。
「義認」を仏教的にいえば、救いへの道です。
ユダヤ教とイスラム教では、神は最後の審判において正しい者とそうでない者を振り分けます。その判断基準のひとつとなっているのは、その人の一生涯を通しての行為です。まるで家計簿に収入と支出を記するように、神は一人ひとりの行いを事細かに記し、トータルで黒字なら天国、赤字なら地獄行きです。
しかしキリスト教の場合は少し違うのです。一生涯を通して正しいことをしても、救われないこともあります。逆に、悪いことばかりをした者でも、信じれば救われるというのがキリスト教です。カトリック教会とプロテスタント教会において、「義認」の細かい解釈に差異があり、それが双方の分裂の原因にもなっています。しかしここではまず「義認」のベーシックな考えについてみておきましょう。
すでに見てきたように、旧約聖書の中にはアダムとイブが禁じられた木の実を口にしたというエピソードでは、「原罪」という言葉は出てきません。ユダヤ教徒の考えでは、その罪はアダムとイブだけのもので、全人類のものではありません。ですから、律法さえ守れば、人間は神の前で「義」とされる、つまり正しい人間として認められると考えられていたのです。
自分のことを人間と考えていたイエスは、自分はもちろんのこと、弟子たちにも律法の厳守を課していました。ただでさえ厳しい律法の戒めの内容を、イエスはさらに独自な仕方で解釈します。たとえば、「殺してはならない」という戒めについて、こう説明します。
「昔の人々に『殺すな。殺す者は裁判を受けねばならない』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。しかし、わたしはあなたがたに言う。兄弟に対して怒る者は、だれでも裁判を受けねばならない。兄弟にむかって愚か者と言う者は、議会に引きわたされるであろう。また、ばか者と言う者は、地獄の火に投げ込まれるであろう」(マタイ5:21・22)
「ばか者」という一言で地獄行きとはあまりにもひどすぎます。イエス自身は自分の気に食わないものに「ヘビ」や「マムシの子」とそしったりしているのではありませんか。そこで私が思うのですが、イエスは天国と地獄を今のクリスチャンのように、死後の別世界として捉えていなかったのではないでしょうか。つまり、兄弟に向かって「バカ」という一言を言ったその時が地獄、隣人を心から愛したその時が天国。イエスは福音書の中で、天国のことを「神の国」と表現しています。
「神の国は何に似ているか。またそれを何にたとえようか。一粒のからし種のようなものである。ある人がそれを取って庭にまくと、育って木となり、空の鳥もその枝に宿るようになる。…【中略】…パン種のようなものである。女がそれを取って三斗の粉の中に混ぜると、全体がふくらんでくる」(『ルカによる福音書』13:18~21)
イエスのメッセージは明快です。神の国は「あの世」的な別世界ではなく、この世で実現させるべきものです。イエスの言う「パン種」とは、天然酵母のことでしょう。では、誰がそのパンの生地を捏ねるのでしょうか。
「神の国は、見られるかたちで来るものではない。また『見よ、ここにある』『あそこにある』などとも言えない。神の国は、実にあなたがたのただ中にあるのだ」(17:20・21)
問題は、神の国を誰が実現させてくれるか、ということです。イエスの答えは、ほかでもなく今ここで生きている私たちなのです。イエスのような生き方をすれば、この世が神の国になるのです。それならば、イエスの次の言葉もうなずけます。
「わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない」(『ヨハネによる福音書』14:6)
現在のキリスト教では、仏教と違い、自分をよりどころとしません。イエスをよりどころとします。しかしイエスをよりどころとすることは、イエスのように生きることではありませんか。イエスが神への通路ならば、イエスのように生きている者は自らイエスとなり、神の子であると気づくはずです。少なくとも、私はそういうふうに読むしかありません。そしてこの一人称のアプローチを、私は宗教の本来のあり方と考え「宗教A」と呼んでいます。しかし、今日のクリスチャンは口が曲がっても「私は神の子」とは言わないでしょう。それはなぜか。
パウロの新しい発想その責任はパウロにあると思います。パウロはイエスを神とし、律法を無効と見なしたからです。それには神の子であるイエスが磔刑になることによって、それまでの人類の罪をすでに贖ったという理由がありました。パウロの考えでは、そもそもの人間は逆立ちしても、罪のない生き方をすることができない。原罪を贖うことは、神にしかできない、文字通りの〝神業〟だからです。そのロジックを成り立たせるためには、パウロはアダムだとイブという二人が起こした過ちを、全人類に擦り付けました。『ローマ人への手紙』で、彼はこう書いています。
「ひとりの人の不従順によって、多くの人が罪人とされたと同じように、ひとりの従順によって、多くの人が義人とされるのである」(5:19)
「一人の不従順」とはアダムのことで、「一人の従順」はイエスの十字架。ここで、旧約聖書で神が人間と結んだ約束の内容がガラッと変わります。パウロ以降は、掟(律法)を守るかどうかではなく、イエスの実物見本に習うのでもなく、イエスによる贖いを信じるかどうかという一点だけが重要。「信じる者は救われる」というわけです。
使徒の中には、パウロと違う主義・主張を持った人々もいたはずです。例えば『ヤコブの手紙』では、信仰と行いが対比させられています。
「わたしの兄弟たちよ。ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったら、なんの役に立つか。その信仰は彼を救うことができるか。
ある兄弟または姉妹が裸でいて、その日の食物にもこと欠いている場合、あなたがたのうち、だれかが、「安らかに行きなさい。暖まって、食べ飽きなさい」と言うだけで、そのからだに必要なものを何ひとつ与えなかったとしたら、なんの役に立つか。信仰も、それと同様に、行いを伴わなければ、それだけでは死んだものである。
しかし、「ある人には信仰があり、またほかの人には行いがある」と言う者があろう。それなら、行いのないあなたの信仰なるものを見せてほしい。そうしたら、わたしの行いによって信仰を見せてあげよう」(2:14~18)
しかし初期の教会でパウロ一人の影響があまりにも強かったため、そういう声はほとんどもみ消されてしまったと思います。ルターが新約聖書をドイツ語に訳した際も、『ヤコブの手紙』を「葦の書」すんわち取るに足りない軽薄なものとして扱いました。聖書の解釈にうるさいプロテスタントよりも、カトリック教会では今も善行が信仰の証として大事にされていますが、わたしたち人間が信仰のみによって救われるという点では、両者が一致しています。
復活という〝心のイベント〟パウロの主張をすんなりと読み込めない人々はヤコブの他にもいたはずです。前述したように、多くの使徒は生前のイエスにこそメシアとして働きを期待してようですが、死刑によってその期待は見事に裏切られました。イエスがメシアなら、いや神なら、十字架でもだえ苦しむハズはなかったと思ったものもいたのではないでしょうか。
しかしそこでパウロが神の概念を一八〇度回転させてしまったのです。神なのに十字架で死んだのではなく、神だからこそ磔になって、そして復活したのだ、と。厳格なキリスト教徒には怒られそうですが、私はイエスの復活は歴史的事実ではなく、フィクションだと思っています。イエスは仮死状態で墓に入れられ、三日目にコーマから目覚めたという説を唱える人もいるようですが、私はそんなことはなかったと思います。復活ではなくて、インスピレーションならあったと思います。イエスが亡くなったあと、その教えを世界の各地で広めようと奮闘し、殉死を遂げていた弟子たちの活動の中でしか、イエスは復活していないと思われていたではないでしょうか。
『コリント人への第一の手紙』では、パウロは復活したイエスについてこう書いています。
「ケパに現れ、次に、十二人に現れたことである。…【中略】…そののち、ヤコブに現れ、次に、すべての使徒たちに現れ、そして最後に、いわば、月足らずに生れたようなわたしにも、現れたのであ」(15:5~8)
ダマスコの手前でパウロが体験したのは、イエスの復活だったそうです。残されていた他の使徒たちも同じような形でイエスの復活を体験したかもしれません。それはつまり、復活は歴史的事実というより内心の出来事だったということを意味しています。私にそう確信させている理由はほかにもあります。クリスチャンなら誰しも一度は暗記させられる「信条」があります。私も堅信の授業で覚えさせられました。その日本語訳は教会ごとに微妙に違っていますが、ここでカトリック教会で使われているバージョンを引用してみましょう。
「天地の創造主、全能の父である神を信じます。
父のひとり子、わたしたちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によってやどり、おとめマリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられて死に、葬られ、陰府【ルビ よみ】に下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇って、全能の父である神の右の座に着き、生者【ルビ せいしゃ】と死者を裁くために来られます。
聖霊を信じ、聖なる普遍の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます。アーメン」
この誓いは正式には「使徒信条」と言われるように、イエスの使徒たちの信条を忠実に表していることになっています。しかし「父なる神・子なるイエス・聖霊」という三位一体のドグマが出来上がったのは、だいぶ時代を下ってからですから、この信条も二世紀後半で今の形になったと言われています。新約聖書の中にも信条のような言葉が度々出てきますが、そのもっとも簡潔なものが「イエスは主である」という一言です。『ぴリピ人への手紙』では、パウロは初期クリスチャンのあいだで使われていた信条を引用しています。
「キリストは、神のかたちであられたが、神と等しくあることを固守すべき事とは思わず、かえって、おのれをむなしうして僕のかたちをとり、人間の姿になられた。その有様は人と異ならず、おのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名にまさる名を彼に賜わった」(2:6~9)
ここで興味深いのは、イエスの人間性があえて強調されているところです。イエスは「人と異ならず」、神には従順であったが、神そのものだったとは言われていません。また「十字架の死に至るまで」のことは書かれていますが、復活や昇天の話はありません。それはどうしてだろうか。その理由は、初期クリスチャンはまだそんな話を考えついてもいなかったからだと私は思います。
「福音書の中ではイエスの復活と昇天の話はちゃんと書かれてあるのではないか」というふうに反論するクリスチャンもいるでしょう。しかし福音書の成立は、パウロの手紙よりはるかの遅かったことを忘れてはいけません。福音書の四人の著者は、イエスの直弟子だった可能性は極めて低いとされています。彼らはイエスその人を知らず、イエスをパウロのメガネを通して見ていたに過ぎないと私は思います。ようするに、復活・昇天はあとから付け足した福音のバージョンアップだったのです。
本来なら、そのバージョンアップなしでも、イエスのように生きて、イエスの復活を内心で体験すれば良かったはずですが、その復活を歴史的事実にしてしまえば、桁違いのインパクトがあることを、パウロは知っていたのではないでしょうか。ようするに、仏教で言えば「方便」。まんざら嘘でもありませんが、決して事実ではない。法蔵菩薩の物語と同じように、内心で信仰を起こりやすくするために、匠に編み上げたストーリだと私は思います。
いずれの福音書でもイエスの復活を最初に目撃したのはマグダラのマリアだとされています。彼女がイエスの配偶者であったという説があるくらい、マリアが初期クリスチャンのグループの中で重要な役わいを持っていた可能性については前述したとおりです。ところが、それ以外のマリアの活躍については触れられておらず、彼女の言動を伝える『マリアによる福音書』なども外典とされてしまいました。その影にもやはりパウロがあったのでは…、というのは私の勘ぐりすぎでしょうか。何しろ、パウロは大の女嫌いだったようです。
「女は静かにしていて、万事につけ従順に教を学ぶがよい。女が教えたり、男の上に立ったりすることを、わたしは許さない。むしろ、静かにしているべきである。
なぜなら、アダムがさきに造られ、それからエバが造られたからである。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされて、あやまちを犯した。しかし、女が慎み深く、信仰と愛と清さとを持ち続けるなら、子を産むことによって救われるであろう」(『テモテヘの第一の手紙』2:11~15)
マグダラのマリアの声を聖書からもみ消した犯人はパウロだったかもしれない。その代わりにといっていいかどうか、復活という〝キリスト教的な方便〟に仕掛け人とされました。女は自ら語ることは望まれないが、パウロの嘘(失礼、方便でした)を裏付ける証人の役くらいなら任せてもよいだろうとなっていたわけです。
パウロと心身問題パウロの思想にはイエスには見られない心身の二元論があります。神の国がこの世で、「この身のまま」で得られるわけがないとパウロが考えていたようです。
「からだの訓練は少しは益するところがあるが、信心は、今のいのちと後の世のいのちとが約束されてあるので、万事に益となる」(『テモテヘの第一の手紙』4:8)
パウロは身体の実践を完全に否定するまではいっていませんが、むしろ「後の世」への期待を込めて、信心を説いているのです。このあたりの逆転も、仏教における浄土思想に非常に近いです。『ローマ人への手紙』では、パウロはさらに語気を荒げています。
「肉の思いは死であるが、霊の思いは、いのちと平安とである。なぜなら、肉の思いは神に敵するからである。すなわち、それは神の律法に従わず、否、従い得ないのである。また、肉にある者は、神を喜ばせることができない。
しかし、神の御霊があなたがたの内に宿っているなら、あなたがたは肉におるのではなく、霊におるのである。もし、キリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。もし、キリストがあなたがたの内におられるなら、からだは罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに生きているのである」(8:6~10)
パウロが持っていた身体へ懸念は、彼の女嫌いと関係していたかもしれません。『コリント人への第一の手紙』の中で、かれはこう書いています。
「男は、神のかたちであり栄光であるから、かしらに物をかぶるべきではない。女は、また男の光栄である。なぜなら、男が女から出たのではなく、女が男から出たのだからである。また、男は女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのである。それだから、女は、かしらに権威のしるしをかぶるべきである」(11:7~10)
パウロの中ではどうやら男性はより精神的、女性はより肉体的な生き物だったようです。そしてその肉体こそ諸悪の根源とみなしたのは、パウロなのです。私たち人間が互のことを本当の意味で愛せないのも、身体へのとらわれがあるからだとパウロが考えていたようです。
「律法の全体は、『自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ』というこの一句に尽きるからである。気をつけるがよい。もし互にかみ合い、食い合っているなら、あなたがたは互に滅ぼされてしまうだろう。
わたしは命じる、御霊によって歩きなさい。そうすれば、決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら、肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。こうして、二つのものは互に相さからい、その結果、あなたがたは自分でしようと思うことを、することができないようになる」(『ガラテヤ人への手紙』5:14~17)
イエスが愛(アガペー)を第一の戒めとし、人々に神を愛し・隣人を愛することを説いたのはすでに見て来たとおりです。その愛の方向は、まず人から神へ、それから人から人へという方向です。しかしその方向は新約聖書の中では、ガラッと変わってきます。先のパウロの言葉で、「神を愛せよ」という第一の戒めの前半が抜け落ちていたことに気づいていたのでしょうか。それは決して偶然ではないと思います。新約聖書の中では、愛のいわば〝コペルニクス的転回〟が起こっています。その回転がもっとも明確に現れているのは、『ヨハネの第一の手紙』です。
ヨハネがそもそもどういう人物だったのも明らかにされていませんが、福音書の中でイエスの最愛の弟子と言われている使徒の名前が「ヨハネ」です。同じ名前の著者の手による福音書と三通の手紙も新約聖書にあります。そのヨハネがいずれも同一人物なのかどうかのについては諸説があります。伝承では一二使徒の一人だったヨハネの作とされてきましたが、最近の研究では『ヨハネの第一の手紙』は紀元一〇〇年前後に書かれたとされていることから、著者は別人とのこと。手紙の最初に「神は光であって、神には少しの暗いところもない」という言葉が出てきます。それを理由に、著者は光を崇拝するグノーシス派に近かったという説もあります。それはともかくとし、神を「光」としていた著者は、手紙の後半でこう語ります。
「愛さない者は、神を知らない。神は愛である。
神はそのひとり子を世につかわし、彼によってわたしたちを生きるようにして下さった。それによって、わたしたちに対する神の愛が明らかにされたのである。
わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して下さって、わたしたちの罪のためにあがないの供え物として、御子をおつかわしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ。神がこのようにわたしたちを愛して下さったのであるから、わたしたちも互に愛し合うべきである。神を見た者は、まだひとりもいない。もしわたしたちが互に愛し合うなら、神はわたしたちのうちにいまし、神の愛がわたしたちのうちに全うされるのである」(ヨハネの第一の手紙4:8~12)
ここで愛のベクトルの方向は一八〇度代わり、神から人間に向かっています。
イエスの場合、「神を愛せよ」という愛のベクトルはまっすぐ上に向いています。それから隣人も、自分と同じように愛せよとイエスは命令していますが、どうして隣人を愛しなければならないのかというと、隣人は自分と同じように神からいただいた命を生きているからです。自分も隣人も神の子、神の下の兄弟というのがユダヤ・キリスト教的です。その割に兄弟喧嘩ばかりをしているのが、ユダヤ・キリスト教のとほほなところですが……。
ヨハネの場合、上からの命令が「愛する者たちよ、互に愛し合う」というエールに変わっています。そしてその呼びかけを可能にしているのが、「愛そのもの=神」という新しい方程式なのです。あれだけ憎しみに満ちていた神は、いつの間にか愛そのものに代わり、私たち人間も空気を吸うようにその中で生きていることになっています。
「神がわたしたちの罪のためにおつかわしになった御子」というのは、言うまでもなくイエスのこと。「地獄に落ちるぞ!」という脅し文句もためらっていなかったイエスの何とも言えないイメージ・チェンジ。彼が厳しい戒めを施行する体育系教師から、人のために身を投げ出すマザーテレサ的な立場に変わったのがこの時です。
それは法華経における釈迦像の変容にも似ています。一人でブッダになっていた歴史上の釈尊は弟子たちに「犀の角のごとく、一人で歩め」に説いていましたが、そのスタンスはいつの間にかトイレ掃除にも付き合う優しいお父さんの慈愛に変容しました。
「神を愛せよ」と命令していたイエスも同じように、いつのまにか、神から人類へのプレゼントに変わってしまったのです。イエスすなわち神の愛。そういうアプローチを、私は「宗教B」と呼びたいと思います。そのベクトルは大きなる他者から、自分へと向けられています。イエスがいずれそういうふうに利用されること知っていたら、どんな顔をしたのでしょうか。
さて、パウロの愛をどう語ったかについて、最後に検討しましょう。
信仰のみで救われると主張していた彼が愛を重要と思っていなかったかよ言えば、決してそうではありません。初期クリスチャンの間では、「アガペー」という言葉は聖餐の同義語としても使われていたようです。シェア・ミール(聖餐)に参加することがすなわち愛の実践と考えられていました。しかし皆がそれぞれ、自分だけの弁当を教会に持ち込んだのでは、愛もなにもない聖餐になってしまうのです。どうやら、コリント人はシェア・ミールの精神でもあるアガペーを忘れていたので、パウロが怒っていました。
「あなたがたが一緒に集まるとき、主の晩餐を守ることができないでいる。というのは、食事の際、各自が自分の晩餐をかってに先に食べるので、飢えている人があるかと思えば、酔っている人がある始末である。…【中略】…わたしはあなたがたに対して、なんと言おうか。あなたがたを、ほめようか。この事では、ほめるわけにはいかない」(『コリント人への第一の手紙』11:20~22)
同じ手紙の中で、パウロは愛を信仰に準ずるものどころか、「信仰よりも大いなるもの」としてその重要性を力強い言葉で説いています。
「たといまた、わたしに預言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また、山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ、わたしは無に等しい。たといまた、わたしが自分の全財産を人に施しても、また、自分のからだを焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、いっさいは無益である。愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない……[中略]……すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも絶えることがない。……[中略]……いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。(コリント人への第一の手紙13:2~13)
無償で与える愛こそ、アガペーの典型です。パウロのこの言葉では、愛のベクトルは上でも下でもなく、むしろ横を向いているようです。寛容で情深い、ねたむことをせず高ぶらない、誇らないというその愛は神ではなく、むしろ隣人に向かっているのではないでしょうか。ですから、そこにユダヤ教の神を想定していなくても、パウロの愛の言葉には大きなインパクトがあります。神も必要としない、横のつながりのみを問題にするアプローチを私は「宗教C」と呼びたいと思います。このアプローチは宗教の枠をも超えるもので、もっとも普遍的です。イエスの教えからキリスト教という世界宗教が発展できた理由はここにあると思います。また一九世紀のマルクス主義のようなユートピア思想も、「宗教C」の影響なしには考えられないと思います。
律法より信仰が大事というアプローチは一見優しそうですが、強い口調で無私の愛を訴えているパウロはハードルを高くしています。信仰があっても、無償の愛を実践しなかれば全ては無駄だというくらいですから。気がかりなのは、パウロ自身の愛の表現です。彼は果たしてその愛をどう実践していたのでしょうか。
『コリント人への第一の手紙』では、パウロはこう言います。
「実際わたしは、神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中でいちばん小さい者であって、使徒と呼ばれる値うちのない者である。しかし、神の恵みによって、わたしは今日あるを得ているのである。そして、わたしに賜わった神の恵みはむだにならず、むしろ、わたしは彼らの中のだれよりも多く働いてきた。しかしそれは、わたし自身ではなく、わたしと共にあった神の恵みである」(15:9・10)
自分の中に働いているのが神の恵みでしかなく、その愛を差し引けばパウロは値打ちがないと自分でいいます。ところが、同じコリント人に宛てた『第二の手紙』では口調が少し違います。
「もしある人がきて、わたしたちが宣べ伝えもしなかったような異なるイエスを宣べ伝え、あるいは、あなたがたが受けたことのない違った霊を受け、あるいは、受けいれたことのない違った福音を聞く場合に、あなたがたはよくもそれを忍んでいる。
事実、わたしは、あの大使徒たちにいささかも劣ってはいないと思う。たとい弁舌はつたなくても、知識はそうでない。わたしは、事ごとに、いろいろの場合に、あなたがたに対してそれを明らかにした。それとも、あなたがたを高めるために自分を低くして、神の福音を価なしにあなたがたに宣べ伝えたことが、罪になるのだろうか」(11:4~7)
パウロは自分が説いている「イエス」がほかの使徒とは異なっていることを認めたた上で、自分の方が縦お口下手であっても、ほかの使徒には優っていると主張しています。ここでは卑下するどころか、今まで卑下したことを後悔しているように見えます。
「わたしは他の諸教会をかすめたと言われながら得た金で、あなたがたに奉仕し、あなたがたの所にいて貧乏をした時にも、だれにも負担をかけたことはなかった。…【中略】…なぜであるか。わたしがあなたがたを愛していないからか。それは、神がご存じである。しかし、わたしは、現在していることを今後もしていこう。それは、わたしたちと同じように誇りうる立ち場を得ようと機会をねらっている者どもから、その機会を断ち切ってしまうためである。こういう人々はにせ使徒、人をだます働き人であって、キリストの使徒に擬装しているにすぎないからである。しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天使に擬装するのだから。だから、たといサタンの手下どもが、義の奉仕者のように擬装したとしても、不思議ではない。彼らの最期は、そのしわざに合ったものとなろう」(11:8~15)
サタンまで持ち出して、貶める必要のあった使徒たちの名前は明記されていないため、想像するしかありません。しかしそれにしても、今までの兄弟愛の話は一体どこへ消えてしまったのでしょうか。私のようなひねくれものでなくても、彼のいう愛には矛盾を感じるでしょう。「愛は寛容であり、愛は情深い。また、ねたむことをしない。愛は高ぶらない、誇らない…【中略】…すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える」と言っていたのは、誰か?
「繰り返して言うが、だれも、わたしを愚か者と思わないでほしい。もしそう思うなら、愚か者あつかいにされてもよいから、わたしにも、少し誇らせてほしい。…【中略】…彼らはヘブル人なのか。わたしもそうである。彼らはイスラエル人なのか。わたしもそうである。彼らはアブラハムの子孫なのか。わたしもそうである。彼らはキリストの僕なのか。わたしは気が狂ったようになって言う、わたしは彼ら以上にそうである。
苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、むち打たれたことは、はるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から四十に一つ足りないむちを受けたことが五度、ローマ人にむちで打たれたことが三度、石で打たれたことが一度、難船したことが三度、そして、一昼夜、海の上を漂ったこともある。
幾たびも旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、にせ兄弟の難に会い、労し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢えかわき、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった…」(11:16~27)
パウロの自慢話はそのあとも続きますが、彼もやはり人間だったようです。あまりにも人間臭いがゆえに、神を求めずにいられませんでした。イエスにもそういう人間臭いところは多々ありますが、イエス以上に人間だったパウロだからこそ、彼のビジョンはイエスの垂訓よりもインパクトがあったと私は感じています。
(2014年8月22日、ネルケ無方)