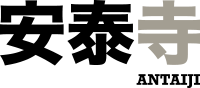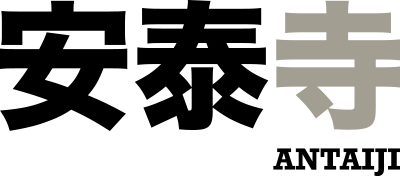Ⓠ7 とうていはく、「この坐禅の行は、いまだ仏法を証会(しょうえ)せざらんものは、坐禅辨道してその証をとるべし。すでに仏正法をあきらめえん人は、坐禅なにのまつところかあらん。」
Ⓐ7 しめしていはく、「痴人のまへにゆめをとかず、山子(さんす)の手には舟棹(しゅうとう)をあたへがたしといへども、さらに訓をたるべし。
それ修証はひとつにあらずとおもへる、すなはち外道の見なり。仏法には、修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆゑに、初心の辨道すなはち本証の全体なり。かるがゆゑに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指の本証なるがゆゑなるべし。すでに修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし。ここをもて、釈迦如来、迦葉尊者、ともに証上の修に受用せられ、達磨大師、大鑑高祖、おなじく証上の修に引転せらる。仏法住持のあと、みなかくのごとし。すでに証をはなれぬ修あり、われらさいはひに一分の妙修を単伝せる、初心の辨道すなはち一分の本証を無為の地にうるなり。
しるべし、修をはなれぬ証を染汚せざらしめんがために、仏祖しきりに修行のゆるくすべからざるとをしふ。妙修を放下すれば本証 手の中にみてり、本証を出身すれば妙修通身におこなはる。
又まのあたり大宋国にしてみしかば、諸方の禅院みな坐禅堂をかまへて、五百六百、および一二千僧を安じて、日夜に坐禅をすすめき。その席主とせる伝仏心印の宗匠に、仏法の大意をとぶらひしかば、修証の両段にあらぬむねをきこえき。このゆゑに、門下の参学のみにあらず、求法の高流(こうる)、仏法のなかに真実をねがはん人、初心後心をえらばず、凡人聖人を論ぜず、仏祖のをしへにより、宗匠の道をおふて、坐禅辨道すべしとすすむ。
きかずや祖師のいはく、「修証はすなはちなきにあらず、染汚することはえじ。」又いはく、「道をみるもの、道を修す」と。しるべし、得道のなかに修行すべしといふことを。」
Ⓠ8とうていはく、「わが朝の先代に、教をひろめし諸師、ともにこれ入唐伝法せしとき、なんぞこのむねをさしおきて、ただ教をのみつたへし。」
Ⓐ8しめしていはく、「むかしの人師(にんし)この法をつたへざりしことは、時節のいまだいたらざりしゆゑなり。」
Ⓠ9とうていはく、「かの上代の師、この法を会得(えとく)せりや。」
Ⓐ9しめしていはく、「会(え)せば通じてん。」
ただ静かに坐禅する―このことだけが、今や私に残された、ただ一つの道でした。
まだ初秋とはいえ、すっかり秋らしくなってしまった信州の寺の、ガランとした僧堂の中に、外からさしこむ月光を受け、しげくすだく虫の声を聞きながら、ただ一人坐禅していたあの夜のことを、今でも思い出します。
それは何か大変すばらしいことを思いついたような派手な快感ではありませんでした。むしろただ求めにもとめたかけずりまわり、疲れはてたあげく、「まあひとやすみ」とホコをおさめて静かに坐ったとき、かえってそこに何か、ホノボノとした安らぎを、――もし「感覚以上の感覚」「覚知以上の覚知」といったものがありとすれば、そんなもので、わずかにそれを見出したとでもいえましょうか。…〈中略〉…今にして思えば、たしかこのころから私には、そこに何か、あるものが熟しつつあったようです。
それから一、二年たち、舞台は信州から京都にうつり、京都でも臘八接心のあるとき、本師老師は「仏法は無量無辺。小さなお前の思わくを、物足りさすものであろうわけがない」と。
――まさにこの言葉こそ、青天の霹靂、迅雷のごとく、私の身内(しんない)に轟(とどろ)きわたり、にわかに通じられた電流によって、従来の私はひっくりかえされてしまいました。…〈中略〉…「坐禅はサトリを『手籠め』にしたいという『思い』の手段となるべきではなく、かえって、坐禅とは本来『手放しの身構え』である。それでこの『無量無辺』を『無量無辺』ならしめる『手放しの身構え』に、ただまかせてゆくことが坐禅というものであり、また真実の自分というものでなければならない。つまり『私が坐禅をする』のではなく、『坐禅で私をする』ことこそが、真実というものなのだ」と。(1959年秋、ラジオ放送) ―内山興正著『自己』(1965)
1 人情・世情ではなく仏法のために仏法を学し、仏法のために仏法を修すべきこと。
2 坐禅こそ本尊であり正師である。
3 坐禅は具体的に「得はマヨイ、損はサトリ」を実行し、二行(懺悔行、誓願行)、三心(喜心、老心、大心)として生活の中に働く坐禅でなければならない。
4 誓願を我が生命とし深くその根を養うこと。
5 向上するのも堕落するのも自分持ちであることを自覚して修行向上に励むこと。
6 黙って10年坐ること、さらに10年坐ること、その上10年坐ること。
7 真面目な修行者達が悩まないでいいような修行道場であることを願って互いに協力すべきこと。
(内山興正「安泰寺へ残す言葉」)
芙蓉山の楷祖、もはら行持見成の本源なり。國主より定照禪師號ならびに紫袍をたまふに、祖、うけず、修表具辭す。國主とがめあれども、師、つひに不受なり。米湯の法味つたはれり。芙蓉山に庵せしに、道俗の川湊するもの、僅數百人なり。日食粥一杯なるゆゑに、おほく引去す。師、ちかふて赴齋せず。あるとき衆にしめすにいはく。
夫れ出家は、塵労を厭い、生死を脱することを求めんが為に、心を休め、念を息め、攀縁を断絶す、故に出家と名づく。豈、等閑の利養を以て、平生を埋没す可けんや。直に須く両頭撒開し、中間放下して、声に遇い色に遇うも、石上に華を栽えるが如く、利を見、名を見るも、眼中に屑を著くるに似たるべし。況んや無始より以来、是れ、曾て経歴せざるにはあらず、又、是れ次第を知らせざるにはあらず、頭を翻じて尾と作すに過ぎず。止だ此の如くなるに於いて、何ぞ須く苦々として貪恋すべけん。如今歇まずんば、更に何れの時をか待たん。所以に先聖は、人をして只、要ず今時を尽却せしむ。能く今時を尽さば、更に何事か有らん。若し、心中の無事なることを得れば、仏祖も猶、是れ冤家なるがごとし。一切の世事、自然に冷淡にして、方に始めて那辺に相応せん。
Our Ancestor Dōkai of Mount Fuyō manifested a pure wellspring of ceaseless practice. When the ruler of the nation tried to bestow upon him the title of Meditation Master Jōshō along with a purple kesa, our Ancestor would not accept them and wrote a letter to the emperor politely declining his offer. Although the ruler of the nation censured him for this, the Master, to the end, did not accept them. His rice broth has passed down to us the taste of the Dharma. When he built his hermitage on Mount Fuyō, the monks and laity streamed to his refuge by the hundreds. Because he served them only one bowl of gruel as a day’s rations, many of them left. The Master, upon a vow, did not partake of any meals offered by donors. One day he pointed out the Matter to his assembly, saying the following:
To begin with, those who have left home behind to become monks have a distaste for the dust and troubles stirred up by defiling passions and seek to rise above birth and death. And they do so in order to give their hearts and minds a rest, to abandon discriminatory thinking, and to eradicate entanglements, which is why it is called ‘leaving home’. So, how can it possibly be all right for monks to indulge in conventional ways of living by being neglectful and greedy?
Straight off, you should discard all dualistic notions and let neutral ones drop off as well. Then, whenever you encounter any sights or sounds, it will be as if you were trying to plant a flower atop a stone, and whenever you encounter gain or fame, it will resemble getting dirt in your eyes. Moreover, it is not that, since beginningless time, no one has ever done this, or that no one has ever known how. Simply, we just stop reversing our head and making a tail out of it.62 If we stop our training at this point, we will suffer from our cravings and greeds, but why do we need to do so? If we do not bring them to a halt right now, when will we deal with them? Therefore, the saintly ones of the past, who were ordinary human beings, invariably and thoroughly exhausted these cravings in each moment of the present. If we can exhaust them in each moment of the present, what more is there to do? If we are able to be calm in heart and mind, it will be as if even ‘the Buddhas and Ancestors’ become our enemy. When everything in the world has become naturally cooled down and impermanent for us, then, for the first time, we will be in accord with the Other Shore.
(www.thezensite.com/ZenTeachings/Dogen_Teachings/Shobogenzo/029gyoji.pdf)
Gudo Nishijima’s translation can be found here (scroll down to “[241] Patriarch [Do]kai…” ): www.thezensite.com/ZenTeachings/Dogen_Teachings/Shobogenzo_2_NC.pdf