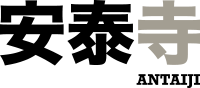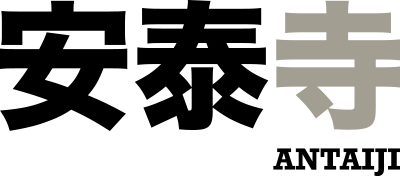新著『ありのままでもいい、ありのままでなくてもいい』・動画:摩訶迦葉の頭陀行と、欧米と日本の葬式について(英語)、2015年3月6日
新しい著書が21日に出版されます:
前書きより:
『仏教がすすめている生き方とはどういうものなのか?
その問に答えるためには、まず「生きることは苦しい」という思いの原因を突き詰めなければなりません。一言で言えば、執着があるから生きることが苦しくなるのです。誰しも「あれが欲しい、これが欲しい」とあれこれを追い求めて生きています。しかしそれが手に入るとは限りません。また、「あれがしたい、これがしたい」と思っても、いつも好きなことができるというわけではありません。むしろ、自分の思う通りにならないことが大半ではないでしょうか。「物足りない」という思いが募ると、人間が苦しくなります。
「夢」「前向き」「プラス思考」なども、私たちの鼻の前にぶら下がっているニンジンのようなものです。それを必死になって追い求めているうちは生きる苦しさを忘れることができるかもしれませんが、求めているそのものがいつまでたっても手に入らないということがわかれば、その絶望感がなおさら大きいです。
人間は周りの物ごとばかりに執着しているのではありません。一番厄介な執着は、自分自身に対する執着です。「別に自分に生まれ変わりたい」とか、「ありのままの自分を表現できない」という思いで苦しむ人も少なくないでしょう。あるいは、今はよくても「年をとりたくない」「死が怖い」などという執着もあります。「執着をするのは悪い」という人もいますが、逆に「私には執着がなさすぎて、生きることがつまらない。何かに執着がしたいけど、何もない!」という複雑な執着の持ち主もいます。
私がこの本で皆さんに送りたいメッセージはごく簡単なものです。
「執着はあってもいいし、なくてもいい。生きることで悩まなくてもいいし、悩んでもいい」
「自分」「愛」「仕事」「親と子」「老と死」など、執着の対象となる物ごとは数えきれません。「執着があってはならない」というのも、ひとつの執着に過ぎないから、執着があるならあったで、その執着と上手に付き合いながら生きていきましょう。しかし執着がなければないほど、悩みの種も減りますう。執着がないからといって、それで悩む必要はないでしょう。』
以下は、摂心明けの放参、本堂の裏と表で撮影した動画です。堂頭が英語で、提唱で話していた正法眼蔵・行持の摩訶迦葉の頭陀行と、欧米と日本の葬式について説明しています。
二〇〇二年、アメリカのジョージア州の火葬場の事件について、ウィキペディナの英語版が詳しいです:
en.wikipedia.org/wiki/Tri-State_Crematory
覚安の出家得度、2015年2月11日
2012年から安泰寺で安居しているアメリカン人の覚安は四度目の春を前にして、いよいよ出家得度に踏み込みました。写真はこちら:
覚安の出家得度
マイクの電源が入っていなかったため、音声はありません。式の最後の数分間:
安泰寺でダンマパダ(法句経)の輪講:最終章「バラモン」、2015年2月11日
安泰寺では毎冬、広間のストーブを囲んで輪講を行っています。今年のテーマはダンマパダ(法句経)でした。安居の修行者は交代で岩波文庫のテキスト(中村一注「真理の言葉」)を読み、自分で解釈をしてから毎日の生活に照らし合わせています。今日は最終回、「バラモン」についての話でした:
ネットでもダンマパダは読めます。例えば青空文庫にも収められています。
輪講の席で最初はテキストを読み上げ、注釈を述べるだけですから、出だしはやや退屈です:
さて、ここからが勝負:テキストの「バラモン」と自分自身の生活態度を比較した場合、はたしてどうなるのか?
お正月休みの過ごし方から始まります:
ある時とつぜん、両親の口からお墓の相談が・・・
安泰寺の山で「樹木葬」というオプションもあったのに、もったいない!
安泰寺の修行仲間に切磋琢磨されながら、先輩の姿勢に学んでいくというのが修行道場の大前提です。そこではパッとしない先輩であっても、一応立てておきましょう。
仏法の問題は癒しの言葉を語るのではなく、いかに偽りのない実践をするか、です。最近売れている仏教書の話。
寒行托鉢中に、不良おばちゃんに「あんたは幸せか?」と絡まれたエピソード。修行僧といえども、汚ければいいというわけではありません。
ダライ・ラマに聞いてみました:「性欲をどうすればいいか?」
そこからさらに話が脱線して、修行生活の様々な裏事情が表に・・・
愛欲と修行の狭間で苦しむ安泰寺の安居者の話。
「お寺と温泉」って、そんな関係があったのでしょうか。
その話は嘘っぽくても、以外に本当かも?
「切り離せないものを、できれば切ったほうが・・・」
またまた、修行仲間のネタで盛り上がりました。
このあとも話は続きましたが、残念ながらメモリーカードはこの時点でイッパイになってしまいました。
本堂をぐるっと、叢林全体で法戦式の慣らし、ついでに本を紹介:「禅の言うとおりにやってみよう」「私が感動したニッポンの文化」「ニッポンを発信する外国人たち」「大学生に語る 資本主義の200年」「MON-ZEN」、2015年2月9日
星覚さんって、どんな人?実は、喫茶店のマスターでもあるのだそうです:
「雲水喫茶」
ベルリンにある星覚さんの禅道場「UNDO」のフェイスブックはこちら:
facebook.com/undoinberlin
「Monzen」はドイツの映画通の間、かなり話題になりました。
この映画の監督は大の日本好きで、他にも日本を題材とした作品を作っています:
ドーリス・デリエ (ウィキペディア)
実は「Monzen」でカメラマンを勤めていたWerner Penzelという日本在住のドイツ人は去年、安泰寺で新たな映画を撮り、今年が来年から映画館で上映される予定です。日本でも見れると思います。
こちらにその映画の撮影風景がご覧になれます:
英語でトークと問答:ネルケ無方がインターネット禅堂 “Treeleaf” の坐禅会に参加
先月、安泰時の住職はバーチャルな禅堂 Treeleaf Zendo (木之葉禅堂)に招待され、坐禅のあとにトークをし、参加者とネットを通じて問答を交わしました。30分の坐禅に続き、90分の英語の話です:
接心開けの放参の朝、無心さんの写真をアップ、2015年2月6日
去年の春に安泰寺を訪れていたオーストラリアの無心さんの写真をアップしました:
Sitting Duck
今から三年前に書いた文章の続きです:
四大(しだい)の性(しょう)おのずから復(ふく)す。子の其の母を得(う)るがごとし、火は熱(ねっ)し風は動揺(どうよう)、水は湿(うるお)い地は堅固(けんご)、眼(まなこ)は色(いろ)、耳は音声(おんじょう)、鼻は香(か)、舌は鹹酢(かんそ)。(参同契)
世の嬰児(ようじ)の五相完具(ごそうがんぐ)するが如し。不去不来(ふきょふらい)、不起不住(ふきふじゅ)。婆婆和和(ばばわわ)、有句無句(うくむく)、ついに物を得ず、語未(ごいま)だ正しからざるが故に。(宝鏡三昧)
私の三人の子供は 「赤ちゃんに優しい病院」に生まれました。「赤ちゃんに優しい病院」は日本を含む先進国では意外と少ないです。二〇〇〇年の時点では世界中で一万五千の病院がUNICEFのWHOの認定を受けていましたが、「先進国」といわれている三十ヶ国には合わせて二六二ヶ所の赤ちゃんに優しい病院しかありません。二〇〇〇年のリストにはフィリピンの病院が一二五〇、中国は六〇〇〇も載っていますが、日本の病院が当時十四ヶ所しかありませんでした。幸いブレストフィーディング(母乳による育児)は今日本で見直されつつあり、現在で日本の「赤ちゃんに優しい病院」は四十ヶ所を超えました。
「赤ちゃんに優しい病院」の条件は何か?
WHOの規定は全部で十ケ条ありますが、たとえば、
「母親が分娩後、三十分以内に母乳を飲ませられるように援助すること」
「医学的な必要がないのに母乳以外のもの、水分、糖水、人工乳を与えないこと」
「母子同室にする。赤ちゃんと母親が一日中二十四時間、一緒にいられるようにすること」
「赤ちゃんが欲しがるときに、欲しがるままの授乳を進めること」
「母乳を飲んでいる赤ちゃんにゴムの乳首やおしゃぶりを与えないこと」などです。
上の二人の子供の場合、私は出産に立ち会いました。子供が生まれてすぐ、赤ちゃんの体を洗うこともなく、まず母親の胸の上に置くのです。こうして母と子はまずさぐり合い、一緒にしばらく休みます。そして始めて母乳を飲ませます。そのあとに赤ちゃんの体は拭かれたり、体重は量れたりします。赤ちゃんがまず大きな声で「おぎゃー」と泣きわめくというイメージを持っていましたが、意外と赤ちゃんは泣かないのです。心配になっていた私を看護師が諭しました。
「大丈夫。お母さんのお腹の上に置いたら、安心して泣かないのが普通」
二月に新しく誕生した次男「泉(いずみ)」は二〇〇〇グラムにも満たない未熟児で、緊急手術で生まれたので、母子同室も分別後すぐの授乳も不可能でした。息子と妻は別々の階で寝かされていて、それぞれ点滴や人工呼吸、麻酔のチューブが身体につけられていました。三日目から妻がようやく歩けるようになって、初めて保育器の中の子供に面会できました。最初のころの赤ちゃんはしんどそうで、医師も気をもんでいたようです。出血しやすい体質のため、一時期は輸血の必要もありました。しかし、日にちがたつにつれて、泉はすくすく元気になり、母乳デビューもはたせました。
妻は約一週間で退院できましたが、泉は一ヶ月くらいNICUで養育しなければなりませんでした。ですから、三週間の間は母乳を届けに病院に通わなければならなかったのです。天気の日でも車で片道一時間、大雪の日などでは二時間もかかる道のりなので、一日に一回しか往復できません。 それでは、どうして赤ちゃんのために母乳を届けるかといいますと、搾乳(さくにゅう)して、冷凍パックにいれてもって行くのです。昼ごろの面会のときだけ、直接に与えられるのです。
病院いは最先端の搾乳機(さくにゅうき)はおいてありますが、自宅ではどうしたらよいか?退院のときに悩んでいた妻を、私は安心させようと思いました。
「大丈夫だ、俺は安泰寺のヤギ係りだったよ。四つんばいになってもらえば、なんぼでもしぼってやる。俺は名人さ」
相手にされませんでした(当然です)。妻はインターネットで携帯用の搾乳機を購入しました。一日二十四時間、いつでもどこでも使えるタイプです。
病院はどうしてそこまで母乳にこだわるのか。医療技術の進歩に伴い、未熟児に最適な、先端のミルクフォーミュラがあってもおかしくありません。いや、フォーミュラがあるに違いないと思いますが、病院はあえて「母乳を持ってきてください」というのに、理由があるはずです。
さて、そこで今回の仏教参究です。参同契と宝鏡三昧というのは曹洞宗の多くのお寺で毎日の朝課で読誦される二つのお経です。セットで読まれることが多いようです。「お経」といっても、お釈迦さまが説いたわけではありません。中国・朝鮮半島や日本に伝わっている大乗仏教の経典はすべてそうですが、釈尊の直伝ではないのです。そのために「大乗非仏説」といって、大乗の経典は本当の仏教ではないと批判している人もいます。そこでまず大乗仏教の弁解を言わせてもらいますが、釈尊ではなくても、目を覚ますことはできるはずです。そのときに見えたものを言語化もできます。サンスクリットやパリ語ではなくてもいいはずです。ですから、お経はこれからも生産されていいものです。現に、曹洞宗には作成してから百数年しか経っていない「修証儀」という最新のお経もあります。これからは英語やドイツ語にもスートラが作成されるかもしれません。それでいいのです。
多くの経典の場合、その作者名は分かりません。最初のブロードウェイ・ミュージカルとも評されている「法華経」もそうです。釈尊がなくなってから、だいぶ後に作られた分厚いお経ですが、誰がいつごろ、どういうふうに作成したかは不明です。
参同契と宝鏡三昧の場合は違います。作者ははっきりしています。石頭希遷(700~790)と洞山良介(807~869)です。二人とも禅が形式主義に陥る前の唐代の禅僧ですから、原文は中国語です。お経も短く、参同契は二二〇文字、宝鏡三昧は三七六文字。洞山は石頭の曾孫弟子に当たりますが、石頭の表現を洞山がさらに高めたという人もいますが、参同契にしても宝鏡三昧にしても、その内容の解釈には悩まされます。
四大(しだい)の性(しょう)おのずから復(ふく)す。子の其の母を得(う)るがごとし、火は熱(ねっ)し風は動揺(どうよう)、水は湿(うるお)い地は堅固(けんご)、眼(まなこ)は色(いろ)、耳は音声(おんじょう)、鼻は香(か)、舌は鹹酢(かんそ)。
(地・水・火・風の四大元素は自ずと、それらの性質に従い、それらの働きをする。火は熱い。風はつかみどこがない。水は潤う。地は硬い。同じように、目は形を見、耳は音を聞く。鼻はにおいを嗅ぎ、舌は味をみわける。それらの働きは、赤子がその母を見分け聞き分けし、母と子が自ずと求め合っているようなことだ。)
「誰一人もいない深い山の奥で木が倒れたときには、音がするか、音がしないか」とようなことが大真面目に議論されるのは哲学の世界。音は空気の震度なのか、主体の意識なのか。
「ぽつん、ぽつん」という雨の音を聞いているのは、窓の外で聞いているのか、耳で聞いているのが、意識の中で聞いているのか、というのも赤ちゃんには通用しない問題のはずです。なぜならば、赤ちゃんはその「ぽつんぽつん」という音になりきっているからです。「窓の外の、雨の音を、鼓膜が受け止めて、脳神経のシナプスの働きによって、私が意識している」といった、小難しいことを赤ちゃんは考えたりしません。
世の嬰児(ようじ)の五相完具(ごそうがんぐ)するが如し。不去不来(ふきょふらい)、不起不住(ふきふじゅ)。婆婆和和(ばばわわ)、有句無句(うくむく)、ついに物を得ず、語未(ごいま)だ正しからざるが故に。
(世の中の赤ちゃんはみんなそうだ。五感はちゃんと備わっている。主体と客体が行き来したり、インプットによってアウトプットが起こるというような関係が成立つ以前に、ちゃんと機能している。「ばばわわ」という赤ちゃん言葉は、言葉になっていなくても、物事を分析することにいたっていなくても、[だからこそ母親には的確に伝わる])
赤ちゃんと大人と、どちらがだまされやすいか。
パソコンの画面に向かって、バーチャルな「リアリティー」の中で浮き沈みし、窓の外の「ぽつんぽつん」という音すら聞こえてこなくなった大人。ファーストフードで間に合わせている大人。人と自分を給料で比べている大人。人生を数値に置き換えている大人。赤ちゃんの鋭い感覚を見失っている大人。
赤ちゃんはそういう大人にはだまされない。
自身の貧富を顧みず。偏(ひとえ)に吾子の長大ならんことを念ふ。
自の寒きを顧みず、自の熱きを顧みず、子を蔭(おほ)ひ子を覆(おほ)ふ。
以て親切切切の至りと爲す。
其の心を發(おこ)す人、能く之を識る。其の心に慣ふ人、方に之を覺る者なり。 (典座教訓)
「喜心・老心・大心」というのが僧堂の台所に立つ典座の三つの心です。上の言葉は道元禅師の典座教訓の「老心」、つまり親心の説明からの引用です。
「親は自分の財産を省みることなく、ただただわが子の成長を願うのだ。暑い時は、自分がいくら熱くても、子を自分の陰に置く。寒い時は、自分がいくら寒くても、子を自分の身体で抱きしめる。これを「親切、切々のいたり」という。老心を起こした人なら、この気持ちがよく分かる。老心を実践している人はみな、親の気持ちに気づく。」
大乗の菩薩は家族などへの執着を断ち切るというのではなく、むしろその執着の環を無限に広げることを目標としていると私は確信します。菩薩の修行は「スキンシップ」から始まらなければならないのです。「スキンシップ」という言葉は、一九五三年に開催されたWHOのセミナーであるアメリカ人が使っていたのは最初だそうですが、「分類上は和製英語になっている」(ウィキペディア)。英語には「スキンシップ(Skinship)」という言葉は元々ありません。ところが、今は「スキンシップ」という言葉は逆輪入され、英語のウィキペディアにものっています。どうやら「母親と子供が身体的な接触」というよりも「ハダカの付き合い」という意味で使われること多いようですが、“Skin(はだ)”と“Kinship(親族)”を合わせてできたこの言葉のそもそもの意味は、肌で触れ合うからこそ親子の絆が育ち深まる、ということでしょう。英語でも、いまやスキンシップをテーマにした赤ちゃんや子育てのサイトやブログがあることを知りました。ある英語のブログでは母親と赤ちゃんの絆(“Bond”)を作るために、母乳栄養のほかに“Co-sleeping”や“Family bed”は勧められています。日本と違い、西洋に親が子供と同じ蒲団で寝るという週間はありませんが、もっと良い親になるために、日本から“Skinship”を見習いなさい、というのです。
西洋の親は早い時点から赤ちゃんを親の寝室から離し、子供が夜中に泣き出して放置することは昔よくあったことです。小さい子供を寝かすときも、お母さんは「おやすみ」といって電気を消すだけで部屋を後にすることが決して珍しくありません。子供が寝るまで一緒に蒲団やベッドに入るという習慣はありません。子供が勝手に泣き寝入りすればいい、という考えです。私のドイツの家族もそうです。上の子供がまだ二歳と一歳だったころ、実家に帰ったことがあります。ドイツの父親に孫の顔を見せるためでもあるのです。ところが、子どもが寝てから父親と話をしているときに、妻は絶えず子供部屋から泣き声が聞こえてこないかと、聞き耳を立てていました。会話に参加しない妻をみて、父親は笑っていました。
「子供が泣き出したって、どうせいずれは泣き疲れる。そして再び寝付くだけだよ。ほっておけ。」
子供はほっておいた方が楽だし、ほっておかなければ親の「プライベート」な時間は全くなくなるというのです。
昔のドイツでは赤ちゃんを檻のような「赤ちゃんベッド」に入れたり、外出の時はベビーカーに入れて連れて行くのが普通だったので、親と子供の体が触れ合うことはあまりありませんでした。「だっこ紐」がはやりだしたのは、ごく最近です。そもそも、近隣の子供をベビーシッターとして雇い、親だけで外出する人も珍しくありません。そのくせ大人になると、欧米人は公の場でもやたら異姓への接触をもとめ、手をつなぐのはいいとしても人前でハッグやキッスまでしている姿に多くの日本人は違和感を感じているのではないでしょうか。ひょっとしたら、それは欧米人の多くが子供の頃に肌で感じ得なかったスキンシップを大人になって、異姓に求めているだけのでは、と私が思うこともあります。
どうして西洋で今まで「スキンシップ」をあまり大事にしてこなかったのでしょうか。早い時点から「個人の確立」を強調しているあまりではないかと思います。つまり、歩きもできないような赤ちゃんですら、なるべく早く「独立」させて、親に極力頼らさせないというのです。しかし、赤ちゃんから「個の確立」を期待しても、無理があります。逆に、思い切り親子の絆を感じさせてからではないと、大人になっても「自信」をもった生き方はできないと思います。一般社会でも個人の独立と強調しすぎるあまり、個々人と孤立させてしまう危険を感じます。仏教の教えでは、縁起でしか成り立っていないこの世の中では完全な「個の確立」は最初から甚だしい幻想です。
私自身も「ほって置かれた」という子どものころ記憶は今も根強く残っています。母は私が七歳の時になくなって、父は再婚しませんでした。しかし、まだ三十代後半だった彼が異性に惹かれていないわけもなく、いつもガールフレンドの一人くらいはいたようです。ある日曜日の朝のことです。前の夜遅くまで出かけていた父より、私と二人の妹が早く目を覚ましてしまいした。それぞれの寝室からリビングに来ると、そこには持ち主の知らないブラが脱ぎ捨てられていました。そして昼前になると、遅れた朝食で新しいガールフレンドと気まずい初顔合わせになりました。
「あなたたちはだれなの?」
・・・・・・。
今から考えると「異常」としかいえないこの風景は当時の私子供たちにとっていたって「普通」でした。父親といえども、父は個人として独立し、好きな女性とデートするのは彼の自由だと、私たち子供も考えていました。親を独占したいと気持ちはどの幼い子供も持って入るのですが、それができないというきびしい現実をこんな形で早い時点から学びました。
私の育った家庭はある意味では特殊かも知れませんが、欧米人はたいがい親子の絆より、愛し合う男女の絆を大事にしていると思います。子供をいち早く「独立」させようという心理も、ひょっとしてそれと関係しているのではないでしょうか。本当に子供の独立を考えているというより、親が子供と一緒に過ごしている時間を「面白くない時間」「自分の時間ではない」と思っているから、子供から無理に「独立」を要求しているという一面もあると思います。
別の要因は「性的解放」という六〇年代の終わりころからはやりだした考え方です。自立した男女は「結婚」や「家庭」といった古典的な概念に縛られず、自由に愛し合うべきものだというのは、父の世代では常識になっていました。ただ、その考えの犠牲となるのがじゃまもの扱いされる子供だと、人々は今ようやく気づき始めています。
「子供に早く自立してほしい、私だって遊びたいし、自分を実現できるチャンスがほしいわけ」
と育児に疲れているといいながら、自分のブログにつぶやいているママは日本にもいそうです。子育てを自分の実現として捉えていない大人は残念ながら、今の日本で増えているかもしれません。自立と自己表現をあるだけ大事にしてきた欧米では、いまや逆にSkinshipやBonding(きずな作り)といった育児方法は大流行しています。
ところが「きずな、きずな」を呪文のように唱えるのもいかがなものでしょうか。スキンシップの行き過ぎで、過保護になりはしないかと心配する人もいるでしょう。それもそのとおりです。愛着はなくてはならないと思いますが、執着であってはいけません。適時に親離れ・子離れができなければ、Bond(絆)がBondage(束縛)になってしまうのです。
日本ではあまり名前を聞かないですが、ハリール・ジブラーンというレバノン出身の詩人はご存知ありませんか。一九三一年にニューヨークでなくなるまでにはあまり注目を集めなかったようですが、彼の著した『預言者』は一九六〇年代のカウンターカルチャーに愛読され、いまやハリール・ジブラーンはシェークスピアと老子に続く、世界でで三番目に売られている詩人だといわれています。作品の中でももっとも有名になったのは「子供について」という詩ではないでしょうか。一部のみですが、原文とともに拙訳を紹介したいと思います。
Your children are not your children.
They are the sons and daughters of life’s longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you, yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts.
For they have their own thoughts.・・・[中略]・・・
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
あなたの子は、あなたの子ではない
いのちがいのちを求める、その息子であり娘である
あなたを通してこの世に出てきたにすぎず、あなたから来たものではない
あなたと共にいるものだが、あなたのものではない
自分の愛を与えても、自分の考えを与えるな
彼らには、自分の考えがあるのだから・・・
あなたは、子供という生きる矢を放つ弓なのだ
赤ちゃんは赤ちゃんとして、幼児は幼児として存分に甘えさせたほうがいいと思いますが、中学生になっても、高校生になっても、親が我が子をなお赤ちゃんのようにかわいがってはいけないでしょう。自主性も主体性も与えないことによって、引き籠もりなってしまった人はどれくらいいるでしょうか。これはおそらく日本でしかみられない現象です。ドイツだったら、部屋から出ない子供は親から引っ張り出され、場合によって勘定され家からたたき出されるのがオチでしょう。安泰寺によく中学生や高校生を連れてくる親がいます。「どうぞ、うちのバカ息子を存分に教育してください。ビシバシでいいから、宜しく・・・」と私に言います。親の気持ちよりここで修行するはずの本人の気持ちが聞きたいのです。
「君自身はどうなの?君は本気で修行したいと思っているのか。」
と聞くと、やはり親が子供にかわって答えるのです。
「もちろん本人も修行したいと思っています、そうですよね○○さん?」
今までの経験で、自分で電話の受話器を取って参禅の申し込みもせず、バス停から自分の足で山を登ることもなく安泰寺に来た人のなかで、修行が長続きした人はひとりもいません。
「帰るときは迎えに来ないで、自分の力で家まで帰ってこさせてください」
と親に説明をしても、
「いやいや、全くそのとおりだと思うんですが、まだ子供ですし、私たちも心配ですから。やはり帰りの時も迎えに上がります」
というのです。ああ、それではまるで幼児の保育所への送り迎えではありませんか。
孤立と束縛の間、自立をも絆をも大事にすることは難しいことです。しかし、その両方のあり方が根本的に問い直されないかぎり、この社会の崩壊が目に見えています。
(ネルケ無方著 「生きるヒント33」より)