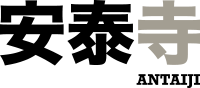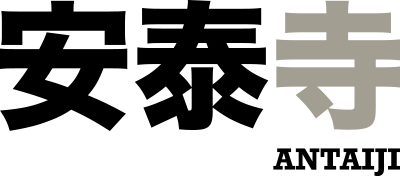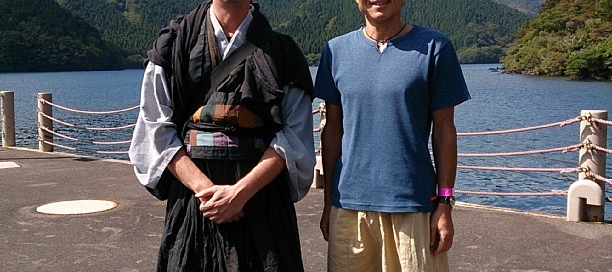献本された二冊を紹介します。一冊目を書いた星覚さんは山陰生まれで、今はベルリンで活躍しています。私とはベクトルが真逆に向いている方ですが、これから注目したい禅僧の一人です。
ネット上の情報は:
彼岸寺 http://higan.net/apps/mt-cp.cgi?__mode=view&blog_id=58&id=25
ベルリンの「雲堂」のFB https://www.facebook.com/undoinberlin
雲水喫茶 http://unsui.net/
日本でも、定期的に「禅の旅」を開催しています: http://www.higan.net/topics/2013/09/1011.html
アマゾンへのリンク:


坐ればわかる


身体と心が美しくなる禅の作法


内山興正老師いのちの問答
内山老師のその他の本:
坐禅の意味と実際―生命の実物を生きる
道元禅師・沢木興道老師一筋に生き抜いた内山興正老師が、禅を求める欧米人のために、平易に説いた坐禅入門書。アタマの中の“思い”を手放し、生命の実物に目覚めて生きる深い坐禅の内的体験も明かす。名著『生命の実物』に「道元禅師の祇管打坐」を加えて新装改訂。
AMAZONで注文:
坐禅の意味と実際
自己―ある禅僧の心の遍歴
いのちがけの恋、真実を求めての若き日の苦悩、恋人・妻の死、そして出家。悟りをも求めないという道元禅師の説いた坐禅への疑い・葛藤、…。七転八倒の心の遍歴とともに、たどり致いた道元・沢木興道の「祇管打坐(しかんたざ)」の禅と、女学生に説いたキリスト教の話を併載。1965年柏樹社刊の復刊。
AMAZONで注文:
自己
観音経・十句観音経を味わう
観音に願いをかけ妻子を失った若き日、南無観世音菩薩と念じた辛い山仕事の日々、その自らの体験を経て、ついに禅者が出逢った観音の正体とは。
AMAZONで注文:
観音経・十句観音経を味わう
正法眼蔵八大人覚を味わう
八大人覚とは、大人(だいにん・おとな)として覚り知るべき(少欲・知足など)八っのことの意で、ブッダ最後の教えといわれています。
その教えを、日本曹洞宗の開祖・道元禅師もまた『正法眼蔵』の一巻として書き遺しました。
本書で内山老師がユーモアを交えて平易に「大人の修行」の原点を解き明かす。原文はこちらでご覧になれます。
AMAZONで注文:
正法眼蔵八大人覚を味わう
正法眼蔵生死を味わう
生死の中に仏あれば生死なし。つまり生死の何から何までが仏なのだから、生死というものはないということです。すべて一切、天地一杯、生も死もひっくるめたものが、仏なのです。
道元の原文は、ストレートで分かり易い、詩的な情感漂う、900字足らずの散文です。
内山興正師著の本書は,『生死』を若い女性向きに分かり易く解説した物で気難しい古文読解の手引きではなく、内山師自身の生死への処し方を語り掛けた気軽なエッセイと云える。
原文はこちらでご覧になれます。
AMAZONで注文:
正法眼蔵生死を味わう
正法眼蔵現成公案・摩訶般若波羅蜜を味わう
「現成公案」の卷は、いわば正法現蔵の総論であると同時にエキスでもあるとは、古来から言われております。優しい言葉で書かれ短い卷でありながら、その美しいひびきのあるご文章は、分からぬながらもそこに限りない深さを感じさせ、これが誰をもひきつけてやまないのでしょう。よく禅の話と言えば、あっちへすっとびこちへすとびして、人の意表外をつけばいいくらいに考えている人が多いわけですが、少なくともこの卷では決してそんなことはありません。わたしはかねてから仏法とは「分からないからただ座れ」「ただ信ぜよ」というのではなく、本当の宗教としての仏法である限り「仏法とは分からないものだとよく分かったから信ずる」「分からないところがよく分かったから座る」のではなくてはならないといつも言ってきております。(内山興正)
現成公案の原文はこちらでご覧になれます。
AMAZONで注文: 正法眼蔵現成公案・摩訶般若波羅蜜を味わう
正法眼蔵仏性を味わう
仏性とは行きつく処へ行きついた生き方。仏性とは「仏になれる可能性」などという、痛くも痒くもない他人事ではない。道元禅師の『正法眼蔵』の中でも最高峰とされてきた「仏性」の巻の真意を解き明かす。
AMAZONで注文: 正法眼蔵―仏性を味わう
普勧坐禅儀を読む―宗教としての道元禅
仏祖正伝の坐禅とは何か? その真髄を得て帰朝した若き道元の最初の著作「普勧坐禅儀」を、いま現代語で明かす。1977年柏樹社刊に「正法眼蔵に学ぶ生きる態度」「坐禅の中味」の2編を加える。
曹洞禅を行じてる方は、この本と「坐禅の意味と実際―生
命の実物を生きる」を読み、自分の坐禅を一度チェックしてみてはいかが?原文はこちらでご覧になれます。
AMAZONで注文:
普勧坐禅儀を読む―宗教としての道元禅
内山興正法話集・天地一杯の生命(全10枚)[CD]
「どこまでも純粋に、自己のいのちの深さに向かう」
「生きる」ことと徹底的に対峙し、その真実を生涯追及し続けた内山興正師。人生科講義(第一巻~第五巻)では「何のために生きるのか」その真理をひもといて丁寧に解説。お釈迦様の遺言でもあり、道元禅師の遺言でもある『正法眼蔵』「八大人覚」(第六巻~第九巻)は、自らの修業体験も交えて分かりやすく手ほどきしています。貴重な音源である、師の晩年の説法(第十巻)も収録致しました。
※【おことわり】尚、この法話集は古い貴重な音源を使用している為、音質上で一部でお聴き苦しい部分がございます。予めご了承下さい。
AMAZONで注文:
内山興正法話集