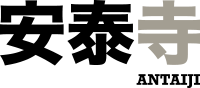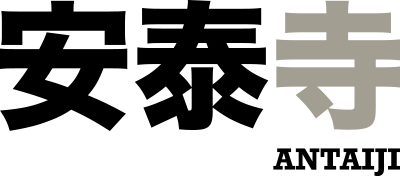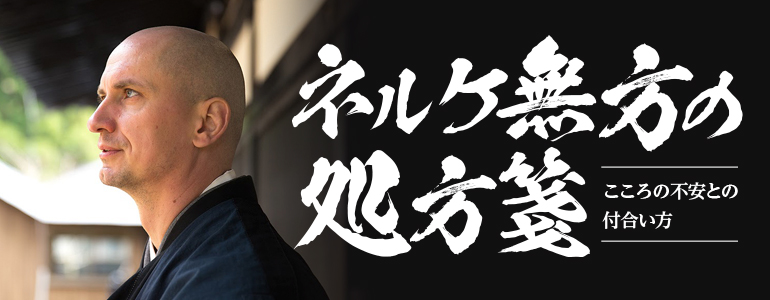弁道話講義&本堂回り、2018年4月18日
資料:
辨道話
諸佛如來ともに妙法を單傳して、阿耨菩提を證するに、最上無爲の妙術あり。これただ、ほとけ佛にさづけてよこしまなることなきは、すなはち自受用三昧、その標準なり。この三昧に遊化するに、端坐参禪を正門とせり。
この法は、人々の分上にゆたかにそなはれりといへども、いまだ修せざるにはあらはれず、證せざるにはうることなし。はなてばてにみてり、一多のきはならんや。かたればくちにみつ、縦横きはまりなし。
諸佛のつねにこのなかに住持たる、各各の方面に知覺をのこさず。群生のとこしなへにこのなかに使用する、各各の知覺に方面あらはれず。
いまをしふる功夫辨道は、證上に萬法をあらしめ、出路に一如を行ずるなり。その超關脱落のとき、この節目にかかはらんや。
予、發心求法よりこのかた、わが朝の遍方に知識をとぶらひき。
ちなみに建仁の全公をみる。あひしたがふ霜華、すみやかに九廻をへたり。いささか臨濟の家風をきく。全公は祖師西和尚の上足として、ひとり無上の佛法を正傳せり。あへて餘輩のならぶべきにあらず。
予、かさねて大宋國におもむき、知識を兩浙にとぶらひ、家風を五門にきく。つひに大白峰の淨禪師に參じて、一生參學の大事ここにをはりぬ。それよりのち大宋紹定にのはじめ、本鄕にかへりし。すなはち弘法救生をおもひとせり、なほ重擔をかたにおけるがごとし。しかあるに弘通のこころを放下せん、激揚のときをまつゆゑに。しばらく雲遊萍寄(うんゆうひょうき)して、まさに先哲の風をきこえんとす。
ただしおのづから名利にかかはらず、道念をさきとせん、眞實の參學あらんか。いたづらに邪師にまどはされ、みだりに正解をおほひ、むなしく自狂にゑふて、ひさしく迷鄕にしづまん。なにによりてか般若の正種を長じ得道の時をえん。貧道はいま雲遊萍寄をこととすれば、いづれの山川をかとぶらはん。これをあはれむゆゑに、まのあたり大宋國にして禪林の風規を見聞し、知識の玄旨を禀持(ぼんぢ)せしをしるしあつめて、參學閑道の人にのこして、佛家の正法をしらしめんとす。これ眞訣ならんかも。
学道用心集 第九 道(どう)に向って修行すべき事
右、学道の丈夫(じょうぶ)は、先(ま)づ須(すべか)らく道に向うの正と不正とを知るべきなり。夫(そ)れ、釋雄調御(しゃくゆうちょうご)、菩提樹下に坐して、明星を見ることを得て、忽然(こつねん)として頓に無上乗の道を悟る。其の悟る所の道は、声聞、縁覚等の能(よ)く及ぶ所に非ず。佛能く自から悟りて、佛、佛に傳へて、今に断絶せず。其の悟を得る者は、豈に佛に非ざらんや。
三世諸仏、依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提。
わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない。―『ヨハネによる福音書』
この世で自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとせずにあれ。―中村一訳『ブッダ最後の旅』
大人の修行について、2018年3月30日
一箇半箇(いっこはんこ)の接得
大人の修行: antaiji.org/archives/jap/muho-otona.shtml
学道用心集 講義@智源寺、2018年3月26日
第九 道(どう)に向って修行すべき事
右、学道の丈夫(じょうぶ)は、先(ま)づ須(すべか)らく道(どう)に向うの正(しょう)と不正(ふしょう)とを知るべきなり。
夫(そ)れ、釋雄調御(しゃくゆうちょうご)、菩提樹下(ぼだいじゅげ)に坐して、明星(みょうじょう)を見ることを得て、忽然(こつねん)として頓(とん)に無上乗(むじょうじょう)の道(どう)を悟る。其の悟る所の道は、声聞(しょうもん)、縁覚(えんがく)等の能(よ)く及ぶ所に非ず。
佛(ほとけ)能く自(みず)から悟りて、佛、佛に傳へて、今に断絶(だんぜつ)せず。其の悟を得る者は、豈(あ)に佛に非(あら)ざらんや。
所謂(いわゆる)道に向うとは、佛道の涯際(がいさい)を了ずるなり。佛道の様子(ようす)を明(あきら)むるなり。
佛道は人人(にんにん)の脚踉下(きゃくこんか)なり。道に礙(さ)えられて当處(とうじょ)に明了(めいりょう)し、悟(ご)に礙(さ)えられて当人(とうにん)円成(えんじょう)す。是(こ)れに因りて縦(たと)え十分(ぶん)の會(え)を挙(こ)すと雖も、猶(な)お一半(ぱん)の悟に落(おつ)るか。是れ則ち道に向うの風流なり。
而今(にこん)、学道の人は、未だ道の通塞(つうそく)を辨ぜず、強(し)いて見驗(けんげん)の有らんことを好む。
錯(あやま)らざるは阿誰(たれ)ぞ。
父を捨(す)て逃逝(とうぜい)し、宝を捨(す)てて令并(れいへい)す。長者(ちょうじゃ)の一子たりと雖も、久しく客作(かくさ)の賤人(せんにん)と作(な)る。良(まこと)に以(ゆえ)あり。
夫(そ)れ、學道の者は、道(どう)に礙(さ)えらるることを求む。
道に礙えらるるとは、悟跡(ごしゃく)を忘(ぼう)ずるなり。
佛道を修行する者は、先づ須(すべか)らく佛道を信ずべし。
佛道を信ずる者は、須(すべか)らく自己本(もと)道中に在りて、迷惑せず、妄想せず、顛倒(てんどう)せず、増減(ぞうげん)なく、誤謬(ごびゅう)なしということを信ずべし。是(かく)の如くの信を生じ、是の如くの道を明め、依(よ)って之を行ず、乃ち學道の本基(ほんき)なり。
其の風規(ふうき)たる、意根(いこん)を坐断(ざだん)して、知解(ちげ)の路(みち)に向(むか)わざらしむるなり。
是れ乃ち初心(しょしん)を誘引(ゆういん)するの方便(ほうべん)なり。
其の後(のち)、身心を脱落(だつらく)し、迷悟を放下(ほうげ)す、第二の様子なり。
大凡(おおよ)そ自己佛道に在りと信ずるの人、最も得難きなり。
若し正(まさ)しく道に在りと信ぜば、自然(じねん)に大道の通塞(つうそく)を了じ、迷悟の職由(しょくゆう)を知らん。
人試みに意根(いこん)を坐断せよ、十が八九は、忽然(こつねん)として見道することを得ん。
第十 直下承当の事
右、身心を決択(けつちゃく)するに、自(おのず)から両般(りょうはん)あり、参師聞法(さんしもんぽう)と、功夫坐禅(くふうざぜん)となり。
聞法は心識を遊化(ゆげ)し、坐禅は行證を左右にす。
是を以て佛道に入るに、尚ほ一を捨てて承当すべからず。
夫、人は皆な身心あり、作は必ず強弱あり。勇猛と昧劣となり。也(ま)たは動、也たは容、此の身心を以て、直に佛を證す、是れ承当なり。所謂従来の身心を回転せず、但だ他の證に随い去るを、直下(じきげ)と名ずくるなり、承当と名ずくるなり。唯だ他に随い去る、所以(ゆえ)に旧見に非ざるなり。
唯だ承当し去る、所以に新巣に非ざるなり。
『正法眼蔵・生死』
ただわが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなわれて、これにしたがひもてゆくときちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ仏となる。たれの人か、こころにとどこほるべき。
仏となるにいとやすきみちあり。
もろもろの悪をつくらず、生死に著するこころなく、一切衆生のためにあはれみふかくして、かみをうやまひ、しもをあはれみ、よろづをいとうこころなく、ねがふこころなくて、心におもうことなく、うれうることなき、これを仏となづく。またほかにたづぬることなかれ。