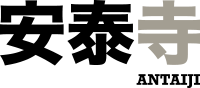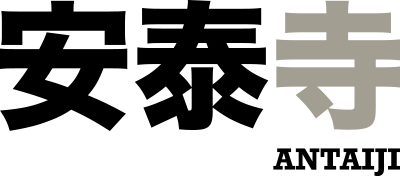無上甚深微妙法 (むじょうじんじん みみょうほう)
百千万劫難遭遇 (ひゃくせんまんごう なんそうぐう)
我今見聞得受持 (がこんけんもん とくじゅじ)
願解如来真実義 (がんげにょらい しんじつぎ)
(開経偈)
衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)
煩悩無尽誓願断(ぼんのうむじんせいがんだん)
法門無量誓願学(ほうもんむりょうせいがんがく)
仏道無上誓願成(ぶつどうむじょうせいがんじょう)
(四弘誓願)
安泰寺では一月から三月までの冬安居(ふゆあんご)の間、起床時間はいつもより一時間遅い四時四十五分となっています。五時から七時までは暁天坐禅(ざぜん)をし、その後は掃除です。みなが掃除をしている間、台所係りの典座は薪ストーブでもちを焼いて、朝食の用意をします。材料は、穴倉で貯蔵しているサツマ芋と里芋、それからジャガイモ、白菜、大根・ごぼうとニンジン、あと腐りかけのかぼちゃもあります。いずれも去年の秋に収穫したものです。
いつもの安泰寺なら、朝食の後から自給自足のための作務にかかりますが、三月の末まで安泰寺は豪雪に埋もれて、畑や田んぼの作業はできません。その代わり、毎日伝統的な経典の参究もしますし、現代書の勉強をもします。仏教の教学にとまらず、哲学の難問を考えたり、他方では安泰寺で自然エネルギーによる自家発電の可能性を探ったり、不耕起の農法に取り組んでみたりもします。
安居者の一人ひとりは自分で研究テーマを決めて、期間の最後に五〇ページのリポートを提出しなければなりません。それと平行して行われているのが、毎日の輪講です。日本の内外から集まってくる参禅者は当番制で道元禅師のテキストを読み、現代日本語と英語に訳し、自分の日ごろの暮らしに照らし合わせて発表します。自分の修行の問題点、叢林(そうりん)のあり方の問題点、はてや道元禅師や修行仲間まで批判が及んだりします。その後のディスカッションに火花が飛ぶこともしょっちゅうあります。お互いに遠慮なく意見が言えるというのは安泰寺の特色の一つでしょう。
安泰寺の冬安居で今もよくテキストとして使われている「永平清規」(えいへいしんぎ)は、道元禅師が永平寺の叢林生活のために定めたルールブックです。その中で特に有名なのは、料理の心構えが丁寧に説明されている「典座教訓」と、雲水のコミュニティーにおけるリーダーたちのロールモデルとしての「知事清規」(ちじしんぎ)です。
近日中に、内山興正老師がかつて安泰寺で提唱された「知事清規」の改訂版が大法輪閣より出版される予定です:
www.daihorin-kaku.com/book/b193473.html
動画は安泰寺にある薪ストーブです。
所謂喜心とは、喜悦の心なり。想ふべし我れ若し天上に生れば、樂に著め間(ひま)無く、發心すべからず。修行未だ便(べん)ならず。何かに況や三寶供養の食を作るべけんや。(典座教訓)
Bodhicitta、道心、菩提心。この心が道元禅師にとっていかに大事であったかは、正法眼蔵や典座教訓の数々の言葉で分かります。最初に人生の苦しみに気づいて、何とかしてそこから逃れたいという思いから出発して、「私一人なんてどうなってもいい」という燃えるような志まで、菩提心のスペクトルが広がっています。肝心なのは、それをいかに日常の実践に表すかです。禅寺の場合、監院、園頭や典座のように、大衆のために自分を忘れて、ただただ働くというのも菩提心の表現です。
実際に共同生活していれば、いうほど簡単なことではありません。冬の間、皆が薪ストーブの燃えている部屋で勉強しているときに、典座は一人で寒い台所で立たなければなりません。
「あいつらがぬくいところでのんびりしているのに、何でオレだけが寒い思いをしなければならないのか」
と思うときだって、あるのです。春から外での作務が再開しされると、今度は大衆が冷たい雨が降る中で雪囲いを取り外し、屋根に上ってかわらを修理したり、泥まみれになって田端を耕したりします。五月になれば三日連続の田植え、夏になれば炎天下の草刈三昧になります。その時には逆に、典座にあたってない人が思ったりします。
「典座はいいな。雨も風も当たらないところで、ゆったりのったり・・・。俺たち、死にものぐるいでやっているのに」
修行をしに山に上った私たちがそう思うのは、菩提心が足りないからです。
典座教訓の最後に、道元禅師は菩提心を「三心」という形で、三つの要素に分けて分かりやすく説明しています。喜心(きしん)・老心(ろうしん)・大心(だいしん)です。冒頭の引用で、禅師は「喜心」を定義します。
「喜心とは喜びのこころ。考えてもみなさい。もしあなたが今天国にいたら、楽しみばかりにこころを奪われて、発心することはありえない。修行しようとも思っていなかっただろう。ましてや仏・法・僧の三宝に帰依し、供養し、叢林のために料理をさせていただくなんて、夢のまた夢であったはずだ。」
この発想が面白いと思います。
天国ではなくて、この世に生まれてよかった。不平不満の多い今の状況、今の自分でよかった。けっしてモテモテではない、天才頭でもない、だれにもあこがれていない、この自分で。
なぜなら、ぱっとしないこの自分に酔いようがないからだ。自分に酔っていなければ、目を覚ませる。現に今こうして自分と向き合っているのも、しょぼい人間に生まれたおかげで、天国ではありえなかったはず。真実の道を捜し求められているのも、たいした人間ではないからだ。たいした人間でなくて、よかった。
ここで思い出すのが、道元禅師の「知事清規」の冒頭に出てくる難陀(なんだ)の話です。難陀は釈尊の義母弟にあたり、釈尊の出家した後に代わって王子即位していたのです。ゆくゆくは釈尊と彼の血を分けた実父、浄飯王(じょうぼんのう)の後を継ぐはずの人物でした。ところが、ある日ブッダとなった釈尊は托鉢をしに、難陀のところにもよります。乞食の応対を召使に任せていた難陀が、ブッダ本人が来ているときいて、自分で門まで出ようとします。女のカンが働いたのか、国中で一番の美人と評判の奥さん孫陀利(そんだり)はこれの袖を引いていいました。
「いかないで」
「すぐ戻ってくるから」
「あたしの化粧が乾くまで、戻っておいでよ」
門まで出た難陀はブッダの鉢を受け取り、ご飯でいっぱいにしてあげましたが、再び門に戻ったときにはブッダの姿がありませんでした。ブッダに一番親しい弟子阿難(あなん)が通り過ぎていました。ブッダと難陀の従弟でもある人です。
「この鉢、ブッダに届けてもらえないか」
「ブッダから直接受け取った物は、直接返しなさい」
そういわれてしまった難陀はブッダの後を追い、結局は叢林(そうりん)まで行ってしまいました。鉢を返しに来ただけの難陀に、あろうことか、ブッダが頭を剃らせてしまうのです。
「僕は王位を継ぐものだよ」
難陀は抵抗しますが、やがて
《午前中はブッダに従い、午後は家に帰ろう》
と諦めるのです。
次には叢林の「知事」という立場を与えられます。
「知事って?」と聞く難陀に従弟の阿難は説明します。
「皆が托鉢に出かけている間、知事はそこらじゅうに落ちている牛糞を取り除いて、掃除をして水をまく。薪を運んで、警備にも当たる。皆が出た後には門を閉め、帰ってくるまでは再び門を開ける。トイレ掃除もよろしくたのむ。」
さあ、たいへんです。無理やり頭を丸めさせられた難陀はいきなり叢林の留守番や国・・・
皆がいなくなってから、東の門を閉めようと思ったら西の門が開いてしまい、西の門を閉めに行ったら東の門が開いてしまいました。何もかも、うまくいきません。
「僕が王様になってからでも、何百倍も立派な僧堂を建立するから、今日はこのへん、とんずらだ!」
大通りに出ればブッダに出会うかもしれないと思っていた難陀は勝手口から出ましたが、運悪く、ちょうど向うから托鉢帰りのブッダが近いづいてくるのではありませんか。難陀は木の枝に隠れようとするが、風が吹いて枝を揺らしてしまいました。そうじゃなくとも、ブッダにはすぐばれていたのでしょう。
「難陀、あなたはどこへ行こうとしたのか」
「嫁のところです」
実は、難陀と孫陀利はまだ新婚さんでした。そこでブッダは難陀をある高い山に連れて行きました。山の上には一本の果実の木が立っており、木下には片目しかないメスサルが坐っていました。
「このサルと孫陀利と、どちらが美しいとおもうか」
「僕の大好きな孫陀利に決まっているではないか」
次に、ブッダは難陀を天の三十三番街まで連れて行きます。そこのプレジャーガーデン(楽園)にひとりの美しい天女が音楽を弾いていました。
「君には彼氏がいないの」
と思わず声をかけた難陀に彼女は言いました。
「今はいないの。でも下界で一生懸命に修行しているナンダという人は来世このプレジャーガーデンに生まれ変わり、私の彼氏になるはずのよ。」
ブッダはまた難陀に聞きました。
「彼女と孫陀利と、どちらが美しいとおもうか」
「なにをいう!この天女さんと孫陀利のギャップは、孫陀利とあのメスサルのギャップよりも大きい」
将来この天女の彼氏になれれば、しばらく孫陀利にあえなくてもとにかく修行に没頭しようと決めました。ところが、今度は他の叢林のメンバーに仲間はずれにされてしまいました。従弟の阿難にまでが、難陀がそばに坐ろうとしたら席から立ち上がるのでした。
「従弟の君まで、どうして僕を相手にしないのか」
「それは君と僕と、志も修行の目標も違うからだ。君は天国に行こうとしているけど、僕たちはそんなところを目指さない」
わけが分からなくなってしまった難陀に、またブッダが問いかけました。
「地獄にいったことがあるか」
「いいえ、ないよ」
ブッダが連れて行った地獄の光景は恐ろしかったのです。苦しみにもがいている人たちでいっぱいでしたが、一箇所だけスペースが開いていました。
「ここにどうしてスペースが開いているの」
ときいていた難陀に見張り番が答えました。
「ここはナンダという人の指定席だよ。今は人間界にいて、次は天国に生まれ変わる予定になっているけど、天国の次にはこちらへ落ちてくることになっているのだ。」
恐ろしくなってしまった難陀はその後、天国行きの夢から目がすっかり覚めてしまったようです。そして、知事という仕事にも没頭できたようです。それはあのぱっとしない難陀ですら、道元禅師に「貴にして尊たり知事」と言わしめたくらいです。
ぱっとしないからこそ、自分に酔いようがない。自分に酔っていなければ、目を覚ませる。個人のレベルで考えても、国単位で考えても、同じかもしれません。自分自身に酔わないように、浮かれないように気をつけなければならないと思います。
私が最初に日本に来たのが今から二十五年前、一九八七年の夏でした。大学に入学する前の三ヶ月間のホームステイでした。当時の日本はバブル経済の最中、皆は私にこういいました。
「どうだ、すごいだろ。日本はドイツより豊かにもなったし、もうすぐアメリカよりも豊かになるのだぞ。そのためにがんばっているのさ。」
今から思えば、あの難陀の浅はかな夢とどこか似てはいないでしょうか。バブルがはじけて、いざ地獄に向かおうとしている日本・・・いや、「長い長い箸」の話を持ち出すまでもなく、今の社会が天国か地獄かということは、しょせんは見方次第、生きる態度次第です。
「天国じゃなくて、よかったかも。解決口の見えない、問題だらけの今の社会にこそ、私の働き場があるのでは」
この希望から、この気づきから、新たな道も開けるのではないでしょうか。
いわゆる為公とは無私曲なり。無私曲とは稽古慕道なり。 (知事清規)
「知事」とは日本の都道府県の首長ですが、もともとは仏教用語です。サンスクリット語の「Karma-dana」が語源で、事を司るという意味です。ちなみに、「大衆」ももとは仏教用語で、集僧という意味です。古来の叢林(仏教の修行道場)には大衆(だいしゅ)の面倒をみるために、4人の知事がいたのです(後に六知事に増えます)。
寺の総監にあたる「監院(かんにん)」、修行僧の世話人である「維那(いの)」、台所で大衆の料理を作る「典座(てんぞ)」と伽藍の修理などの作務を司る「直歳(しっすい)」です。
この四つの役職の心構えとして、道元禅師は「知事清規」というマニュアルを著しています。監院については次のように書いています。
監院の職は為公(いこう)これ務む。いわゆる為公とは無私曲(むしきょく)なり。無私曲とは稽古慕道なり。慕道は以(も)って道に順うなり。
(監院が公のために務めなければなりません。そのため、私事を忘れなければなりません。私事を忘れるということは、「道」の忠実な実践です)
キーポイントは「為公」です。道元禅師はその内実を具体的に表しています。
事大小と無く人と商議してすなわち行事するは、すなわち為公なり。商議すといえども他語を容(い)れずんば、議せざるに如(し)かず。
(事の大小に関わらず、人と相談してから行動すること。相談といっても、人の意見を聞かないのであれば、相談したことにはならない)
監院が持たなければならない「道心」の説明で、道元禅師も気合が入ります。
黄金を糞土(ふんど)に比し、声誉を涕唾(ていだ)に比し、真を瞞(あざむ)かず偽に順はず。
(お金を糞<くそ>とし、名誉をツバとし、真実を偽りとせず偽りを真実としない)
どうしてそこまで言葉を荒くする必要があったのでしょうか。
おそらく、昔の寺院の中で自分を忘れて大衆のために務める監院ばかりではなかったからでしょう。
権勢に倚持して、大衆を軽ばくすることを得ざれ。また意に任せて事を行い、衆をして不安ならしむることを得ざれ。
(権力者の顔色を伺い、大衆を軽く見るようなことをしない。独断で行動し皆を不安にさせてはいけない。)
知事の中でも一番えらいのは「監院」です。監院が一番えらいのですが、自分をえらいと思ってはいけません。一番えらいからこそ、無私曲でなければなりませんし、無私曲でなければ、本当にえらいとは言えません。監院にとって、一番えらいのは「公」ですが、この「公」は決して権力(権勢)という意味ではなく、「大衆」です。監院のまなざしは、常に大衆に向けられていなければなりません。だから皆と相談をし、人の意見を聞かなければ監院とは言えないのです。
世の中の政治家などにも、大いに反省してもらいたい、と言いたいところですが、ひとごとではありません。
以降、私の話の続きです。
私の師匠である宮浦信雄老師がが不慮の事故でなくなったのは、今から十三年前、二〇〇二年のバレンタインデーのことでした。ブルドーザーでバス停まで四キロの道のりを除雪し、Uターンして山に戻ろうとした際に重機ごと冷たい川に落ちしまったのです。
事故当時、安泰寺には二、三人しか雲水が残っておらず、留守番役として呼び戻されたのは私でした。
「どうせ、ホームレスとして暇を持って余しているのだろう」
というのは先輩の言い分でした。確かに、当時の私は暇でした。先輩に逆らうわけにも行きません。しかし、春になって「住職として安泰寺を守ってくれ」と言われたときには、さすがに驚きました。弟子の中でも一番若い、経験も浅い、しかも外国人の私がどうしたら一ヶ寺の住職に?
これをきっかけに、当時付き合っていた彼女にプロポーズをしました。
「俺について、山寺に来ないか?」
寺には檀家(だんか)が一軒もない、住職の給料はゼロ。米や野菜、かまどで使う薪を自給自足でまかなっている。そんなことを彼女に伝えました。
「そのお寺の住職は、何年くらいするの?」
「まぁ、まず十年だな」
「無理かもしれないけど、がんばってついていくわ」
二人の間に、子どもが三人も生まれました。一方、私の元で出家得度(しゅっけとくど)した仏弟子も十数人います。彼らの指導に当たることがこの山寺での私の使命です。ところが、十一年たった今、後を継げそうな弟子はまだ育っていません。これから育つかどうかも、心配です。嫁にはこう言われています。
「約束の十年はもうとくに過ぎたけど、どうするの? 子どもの教育や、私たちの老後はどうなるの?」
弟子も知りたいようです。
「僕たちは安泰寺で何年修行をすれば、ちゃんとした檀家寺の住職になれるのですか? それまで、小遣いは出ないのですか?」
おいおい、オレのことを誰だと思っているのだ。オレが誰のために寿命を減らしているのか、分かっているのか。ついついこう叫びたくなるのも事実です。
一ヶ寺を管理・監督する立場で道元禅師に学び、初心に帰らなければならないのは、他でもなくこの私なのです。
(ネルケ無方著 「生きるヒント33」 より)
より)
より)