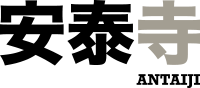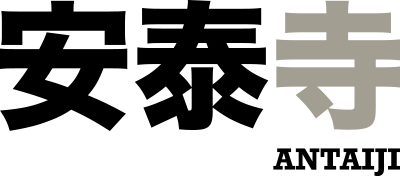典座教訓(13回目の輪講)、2020年2月12日
典座教訓の全文はこちら: antaiji.org/archives/jap/ten.shtml
今日のテキストの原文は:
大宋國の諸山、諸寺、知事頭首の職に居るの族(やから)を見るが如きんば、一年の精勤爲りと雖も、各三般(さんぱん)の住持を存し、時と與(とも)に之を營み、縁を競ふて之を勵む。
已に他を利するが如く兼て自利を豐にす。叢席を一興し高格を一新す。肩を齋(ひとし)うし頭を竸ひ踵を繼ぎ蹤を重んず。
是に於て應に詳(つまびらか)にずべし。自を見ること佗の如くなるの癡人(ちにん)有り。佗を顧ること自の如くなるの君子有りことを。
古人云く、「三分の光陰二早く過ぐ、靈臺一點も揩磨(かいま)せず。生を貧り日を遂ふて區區(くく)として去る。喚(よ)べども頭を囘らさず爭奈何(いかん)せん」と。
須(すべから)く知るべし未だ知識に見(まみ)えんざれば、人情に奪は被(る)ることを。
憐むべし愚子長者所傳の家財を運出(うんすい)して、徒(いたづら)に佗人面前の塵糞と作すことを。
今は乃ち然かあるべからざるか。
嘗(かつ)て當職を觀るに前來の有道、其の掌其の徳自から符す。
大イの悟道も、典座の時なり。洞山の麻三斤も、亦た典座の時なり。
若し事を貴ぶべき者ならば、悟道の事を貴ぶべし。若し時を貴ぶべき者ならば、悟道の時を貴ぶべき者か。
事を慕ひ道を耽(たのし)むの跡、砂(いさこ)を握て寶と爲する、猶ほ其の驗(しる)し有り。形を模して禮(らい)を作す。屡(しばし)ば其の感を見る。
何(いか)に況(いわん)や其の職是れ同じく、其の稱(しょう)是れ一なるをや。
其の情其の業、若し傳ふべき者ならば、其の美其の道、豈に來らざらんや。
ネットでも、典座教訓の英訳がご覧になれます。奥村正博老師とは別バージョンです:
Instructions for the Cook (Stanford translation)
INSTRUCTIONS FOR THE TENZO (translated by Anzan Hoshin & Yasuda Joshu)