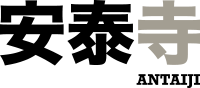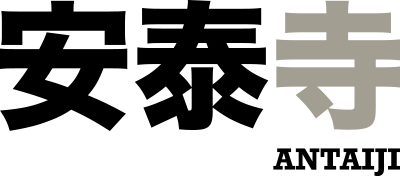先住忌&涅槃会、2016年2月15日
釈尊の入滅から2500年。先代の遷化からもはや14年。
雪は降ったり、溶けたりして、積雪の量は例年より少なめです。
妙賢の輪講「重雲堂式」、2016年2月14日
原文:
一 大小の事、かならず堂主にふれて、をこなふべし。堂主にふれずして、ことををこなはんひとは、堂をいだすべし。賓主の禮みだれば、正偏あきらめがたし。
一 堂のうちならびにその近邊にて、こゑをたかくし、かしらをつどえて、ものいふべからず。堂主これを制すべし。
一 堂のうちにて行道すべからず。
一 堂のうちにて珠數もつべからず。手をたれて、いでいり、すべからず。
一 堂のうちにて、念誦看經すべからず。檀那の一會の看經をせんはゆるす。
大河の輪講「重雲堂式」、2016年2月13日
原文:
一 堂中の衆は、乳水のごとくに和合して、たがひに道業を一興すべし。いまは、しばらく賓主なりとも、のちにはながく佛祖なるべし。しかあればすなはち、おのおのともにあひがたきにあひて、をこなひがたきををこなふ、まことのおもひをわするることなかれ、これを佛祖の身心といふ。かならず佛となり祖となる。すでに家をはなれ、里をはなれ、雲をたのみ、水をたのむ。身をたすけ、道をたすけむこと、この衆の恩は父母にもすぐるべし。父母はしばらく生死のなかの親なり、この衆はながく佛道のともにてあるべし。
一 ありきを、このむべからず、たとひ切要には一月に一度をゆるす。むかしのひと、とをき山にすみ、はるかなる、はやしに、をこなふし。人事まれなるのみにあらず、萬縁ともにすつ、韜光晦跡せしこころをならふべし。いまはこれ頭燃をはらふときなり、このときをもて、いたずらに世縁にめぐらさむなげかざらめや、なげかざらめやは。無常たのみがたし、しらず露命いかなるみちのくさにかをちむ、まことにあはれむべし。
一 堂のうちにて、たとひ禪冊なりとも文字をみるべからず、堂にしては究理辨道すべし。明窓下にむかふては古教照心すべし。寸陰すつることなかれ、專一に功夫すべし。
一 おほよそ、よるも、ひるも、さらむところをば、堂主にしらすべし。ほしいままに、あそぶことなかれ。衆の規矩にかかはるべし、しらず今生のおはりにてもあるらむ。閑遊のなかにいのちをおはん、さだめてのちにくやしからん。
越智の輪講:学道用心集「直下承当の事」&正法眼蔵「重雲堂式」、2016年2月12日
~トピックス~
各々の坐禅:ネルケ無方・南直哉・藤田一照のアプローチ。国家・家族・叢林における調和の意味。四馬(しめ)と大道の話うんぬん・・・
原文:
右、身心を決択(けつちゃく)するに、自(おのず)から両般(りょうはん)あり、参師聞法(さんしもんぽう)と、功夫坐禅(くふうざぜん)となり。
聞法は心識を遊化(ゆげ)し、坐禅は行證を左右にす。
是を以て佛道に入るに、尚ほ一を捨てて承当(じょうとう)すべからず。
原文:
夫、人は皆な身心あり、作は必ず強弱あり。
勇猛と昧劣となり。
也たは動、也たは容、此の身心を以て、直に佛を證す、是れ承当なり。
所謂従来の身心を回転せず、但だ他の證に随い去るを、直下(じきげ)と名ずくるなり、承当と名
ずくるなり。
唯だ他に随い去る、所以(ゆえ)に旧見に非ざるなり。
唯だ承当し去る、所以に新巣に非ざるなり。
原文:
一 道心ありて名利をなげすてんひといるべし。いたづらに、まことなからんもの、いるべからず。あやまりていれりとも、かんがへていだすべし。しるべし道心ひそかにをこれば、名利たちどころに解脱するものなり。おほよそ大千界のなかに、正嫡の付屬まれなり。わがくにむかしよりいまこれを本源とせん。のちをあはれみて、いまをおもくすべし。
坐禅の説明と、「なりきっているかどうか」の基準、2016年2月11日
かすんでいる中で、堂頭が英語で坐禅の足と手の組み方を説明しています:
日本語のアーカイブにも詳しい説明があります:
正しい坐り方
正しい坐り方(2)
正しい坐り方(3)
正しい坐り方(4)
正しい坐り方(5)
正しい坐り方(6)
正しい坐り方(7)
正しい坐り方(8)
正しい坐り方(9)
正しい坐り方(10)
正しい坐り方(11)
正しい坐り方(12)
正しい坐り方(13)
正しい坐り方(14)
足の組み方について:
足を組む
足を組む (2)
足を組む (3)
足を組む (4)
足を組む (5)
足を組む (6)
手の組み方について:
その他:
ただ坐る
「坐禅しても、何もならない」
「ならば、なぜ坐禅をするのですか?」
この問いから出発して、坐禅に向かう姿勢、環境の整理、身・息・心のととのえ方から、坐禅と実生活の結び付きまで説明している一冊です。
書評:finalvent.cocolog-nifty.com
AMAZONで注文: ただ坐る
雲堂の坐禅インストラクション:
今朝の輪講の質疑応答では、ノブが神田に「なりきっているかどうか」の基準を聞いてみました:
縦横無尽に広がる「ノブ・ワールド」、2016年2月9日
ノブが学道用心集「禅僧の行履の事」について発表します。
いきなり手塚治虫の「火の鳥」や、漫画太郎の「珍遊記」から、話はスタートしています。
原文:
右、仏祖(ぶっそ)より以来(このかた)、直指(じきし)単傳(たんでん)、西乾(さいけん)四七、東地(とうち)六世(ろくせ)、絲毫(しごう)を添(そ)えず、一塵(じん)を破(やぶ)ること莫(な)し。衣(え)は曹渓(そうけい)に及び、法は沙界(しゃかい)に周(あま)ねし。
職人の心構え、「守破離」などについて話は続きます。
原文:
時に如来の正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)、巨唐(きよとう)に盛んなり。其の法の體(てい)為(た)らくは、摸索(もさく)するも得ず、求覓(ぐみゃく)するも得ず。見處(けんじょ)に知(ち)を忘(ぼう)じ、得時(とくじ)に心を超(こ)ゆ。面目(めんもく)を黄梅(おうばい)に失(しつ)し、臂腕(ひわん)を少室(しょうしつ)に断(だん)ず。髄(ずい)を得、心(しん)を飜(ひるが)えして風流(ふうりゅう)を買ひ、拜(はい)を設(もう)け、歩(ほ)を退(しりぞ)いて便宜(べんぎ)に墮(お)つ。然(しか)れども、心に於ても身に於ても、住(じゅう)するなく著(じゃく)する無(な)し。留(とどま)らず滞(とどこお)らず。
「趙州無字」について。安心してください、ネタバレはしません。
原文:
趙州(じょうしゅう)に僧問(と)う、狗子(くす)に還(かえ)つて仏性(ぶっしょう)ありや無なしやと。
州云く、無(む)と。
無字の上に於いて、擬量(ぎりょう)し得てんや、擁滞(ようたい)し得てんや。全く巴鼻(はび)なし。請(こ)う試みに手を撒(さっ)せよ。且(しば)らく手を撒して看(み)よ。身心は如何、行李(あんり)は如何ん、生死(しょうじ)は如何ん、仏法は如何ん、世法は如何ん、山河(さんが)大地、人畜(にんちく)家屋(かおく)、畢竟(ひっきょう)如何ん。
最後の「祈祷、祈祷!」まで、丁寧に説明してもらいました。
原文:
看来り(みきた)り看(み)去って、自然(じねん)に動静(どうじょう)の二相(にそう)了然(りょうねん)として生ぜず。此の不生(ふしょう)の時、是れ頑然(がんねん)にあらず、人之れを證する無く、之れに迷うもの惟(こ)れ多し。参禅の人、且(しば)らく半途(はんと)・半迷(はんめい)にして始めて得たり、全途(ぜんと)・全迷(ぜんめい)にして辞(じ)すること莫れ。
祈祷(きとう)、祈祷(きとう)。
雪隠の輪講:学道用心集「佛法を修行し出離を欣求する人は須らく参禅すべき事」、2016年2月8日
安泰寺の広間にて。最初の20分の様子です:
原文:
右、仏法は諸道(しょどう)に勝(すぐ)れたり。所以(ゆえ)に人之(こ)れを求む。
如来(にょらい)の在世(ざいせ)には、全く二教(にきょう)なく、全く二師(にし)なし。大師釈尊、唯だ無上(むじょう)菩提(ぼだい)を以つて、衆生(しゅじょう)を誘引(ゆういん)するのみ。
迦葉(かしょう)、正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)を傳へてより以来(このかた)、西天(さいてん)二十八代、東土(とうど)六代、乃至五家(ごけ)の諸祖(しょそ)、嫡々(てきてき)相承(そうじょう)して、更に断絶(だんぜつ)なし。
然れば則ち梁(りょう)の普通(ふつう)中以後(いご)、始め僧徒(そうと)より、及び王臣に至るまで、抜群(ばつぐん)の者は、帰(き)せずといふこと無し。
誠に夫(そ)れ、勝(しょう)を愛すべき所以(ゆえん)は、勝(しょう)を愛すべきなればなり。葉公(しょうこう)の龍を愛するが如くなるべからざるか。
神丹(しんだん)以東(いとう)の諸国、文字の教網(きょうもう)、海(うみ)に布(し)き山に遍(あま)ねし。山に遍(あま)ねしと雖も雲心(うんしん)なく、海に布(し)くと雖も波心(はしん)を枯(から)す。愚者(ぐしゃ)は之を嗜(たしな)む。譬(たと)えば魚目(ぎょもく)を撮(とっ)て以て珠(たま)と執(しゅう)するが如し。
迷者(めいしゃ)は之を翫(もてあそ)ぶ。譬(たと)えば燕石(えんせき)を蔵(ぞう)して玉と崇(あが)むるが如し。多くは魔坑(まきょう)に堕(だ)して、屡(しばし)ば自身を損(そん)す。哀(かなし)む可(べ)し、辺鄙(へんぴ)の境(きょう)は邪風(じゃふう)扇(あお)ぎ易(やす)く、正法は通じ難し。
然りと雖も、神丹の一国は、已(すで)に仏の正法に帰す。我が朝(ちょう)、高麗(こうらい)等は、仏の正法未だ弘通(ぐづう)せず。何(なに)が為ぞ、何(なに)が為ぞ。
高麗国は猶(な)お正法の名を聞くも、我が朝(ちょう)は未だ嘗(かつ)て聞くことを得ず。前来入唐((にゅつとう)の諸師、皆な教網(きょうもう)に滞(とどこ)るが故なり。仏書を傳うと雖も、仏法を忘るるが如し。其の益(えき)是れ何ぞ。其の功(こう)終に空し。是れ乃ち学道の故実(こじつ)を知(し)らざる所以なり。哀(あわ)れむ可し、徒(いたず)らに労(ろう)して一生の人身(にんしん)を過すことを。
夫れ仏道を学ぶに、初め門に入る時、知識の教(おし)えを聞き、教えの如く修行す。此の時知る可き事あり。
所謂(いわゆる)法(ほう)我(われ)を転(てん)じ、我(われ)法を転(てん)ずるなり。我(われ)能く法を転(てん)ずるの時は、我は強く法は弱きなり。法還(かえ)って我(われ)を転(てん)ずるの時は、法は強く我は弱きなり。
仏法従来(じゅうらい)此の両節(りょうせつ)あり、正嫡(しょうてき)に非ずんば、未だ嘗(かつ)て之を知らず。
衲僧(のうそう)に非ずんば、名(な)すら尚お聞くこと罕(まれ)なり。
若し此の故実(こじつ)を知(しら)ずんば、学道未だ辨(べん)ぜず、正邪奚為(なんすれ)ぞ分別(ふんべつ)せん。
今、参禅学道の人、自(おのず)から此の故実を傳授(でんじゅ)す。所以(ゆえ)に誤(あやま)らざるなり。餘門(よもん)には無し。仏道を欣求(ごんぐ)するの人、参禅に非ずんば眞道(しんどう)を了知(りょうち)すべからず。
最後に「法、我を転じ、我、法を転じる」からくりについて、無為から質問がありました: